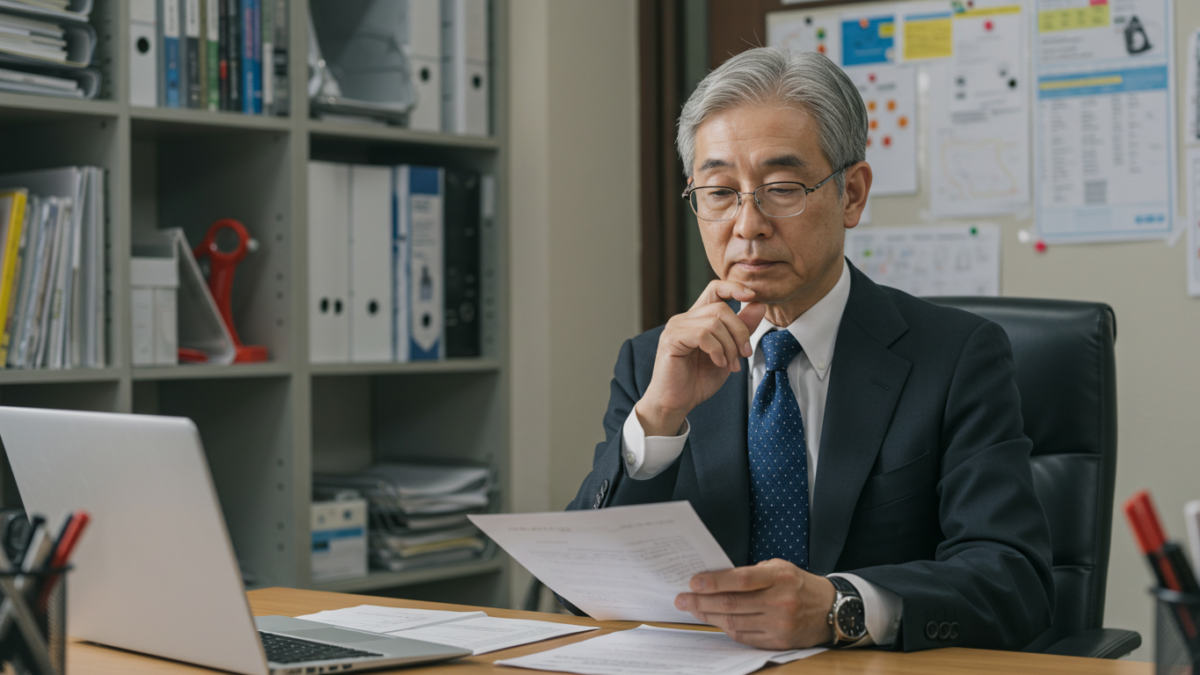1. はじめに
企業経営を続けていくうえで、事業規模の拡大や収益の最大化はもちろんのこと、株主や従業員への責任、次世代への事業承継、事業存続のための再編など、さまざまな観点から最適な経営判断を下す必要があります。こうした状況の中で、M&A(合併・買収)は企業の将来を左右する重要な選択肢のひとつとして年々注目度が高まっております。
特に日本国内では、少子高齢化や経営者の高齢化、後継者不足、事業承継問題といった課題が顕在化しており、事業を後世に残すためにM&Aが果たす役割は一段と大きくなってきております。また、外部の資本やノウハウを導入することで、事業成長を加速させる手段としてのM&Aも急増傾向にあります。
本記事では、M&Aの譲渡企業(売り手)の観点から、どのような流れでプロセスが進むのかを中心にご説明いたします。M&Aは、従来からハードルが高いと見られていましたが、今や中小企業にとっても一般的な選択肢となっています。とはいえ、M&Aは多額の資金と多くのステークホルダーが関係する大きな意思決定であるため、慎重かつ計画的に進めなければなりません。本記事が、譲渡を検討中の経営者やご担当者の方々にとって、具体的なイメージ形成の一助となれば幸いです。
2. M&Aの概念と譲渡企業のメリット
2-1. M&Aの概念
M&A(Mergers and Acquisitions)とは、文字通り「合併と買収」を指す用語です。企業間の統合手法や、株式・事業の取得などを通じて、経営戦略上の目的を達成するために用いられる包括的な手段を表します。具体的なスキームとしては、株式譲渡、事業譲渡、合併、会社分割、株式交換・移転など、複数の手法が存在します。
2-2. 譲渡企業のメリット
譲渡企業(売り手)にとって、M&Aによるメリットは以下のように多岐にわたります。
- 後継者問題の解決
経営者が高齢化し、後継者が見つからない場合でも、買い手企業に事業を引き継ぐことで企業の存続を図ることができます。 - 事業の成長加速
自社だけでは成し得ない設備投資や海外展開など、買い手企業との統合を通じて事業成長のスピードを上げることが可能になります。 - 経営者のキャッシュ化
株式譲渡の場合、経営者自身が保有する株式を売却することで、経営者の個人資産を現金化(キャッシュアウト)することができます。事業承継だけでなく、個人のライフプランに合わせた資金確保としても意義があります。 - リスク分散
単独での事業運営には多くのリスクが伴いますが、大手企業やファンドなどが買い手となった場合には、経営リスクを分散できる可能性があります。 - 従業員や取引先の安定
事業承継の観点だけでなく、従業員や取引先との関係を維持しながら企業活動を継続させられる点も、M&Aを選択する大きなメリットです。
こうしたメリットがある一方で、M&Aを円滑に進めるためには、買い手企業との情報共有やデューデリジェンスなど、多くの準備・手続きが必要となります。以下では、その具体的な流れを時系列で見ていきましょう。
3. 譲渡企業がM&Aに踏み切る理由
譲渡企業がM&Aを選択する理由は、企業の置かれた状況や経営者の考え方によってさまざまです。ここでは一般的によく見られる理由をいくつかご紹介いたします。
- 事業承継問題
中小企業の経営者の高齢化が進むなか、後継者不在というケースは珍しくありません。自社を継いでくれる適任者がいない場合、社内昇格や親族内継承が難しく、かといって廃業するには事業や従業員の将来が不安というジレンマがあります。その解決策としてM&Aによる第三者承継が注目されています。 - 経営資源の限界
自社の経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報など)が限られているため、これ以上の成長が見込みにくい、あるいは競争が激化する市場の変化に対応できないといった状況に陥ることがあります。そこで、より大きな資本力や販売チャネルを持つ企業に事業を譲渡し、成長を継続させるという選択がなされます。 - 事業の選択と集中
事業ポートフォリオの見直しによって、収益性の高い分野に資源を集中させるために一部事業を売却するケースもあります。本業にリソースを集中することで、経営効率を高める狙いがあります。 - 個人資産の確保
経営者が引退後の生活を見据えて資金を確保したい場合や、別のビジネスを立ち上げるための資金調達を目的に、株式譲渡による現金化を図ることがあります。 - 新規市場への参入やスピードアップ
自社としては進出が難しい新規市場や海外市場への参入にあたり、大手企業やグローバル企業との統合を検討することがあります。事業シナジーが期待できる分野であれば、両社にとってウィンウィンの結果が得られます。
このように、譲渡企業がM&Aを検討する理由は多種多様ですが、いずれにせよ経営者が「将来をどう設計したいか」というビジョンと合致しているかを見極めることが大切です。次章では、実際にM&Aを進めるうえで必要となる準備段階について解説いたします。
4. M&Aの準備段階:経営戦略の見直しと会社概要の整理
M&Aを成功させるためには、事前準備が非常に重要です。急に買い手候補を探し始めるのではなく、自社の経営戦略を見直し、どのようなスキームや相手先が望ましいかを明確にしておく必要があります。
4-1. 経営戦略の見直し
- 譲渡の目的・ゴールを整理する
まずは、なぜM&Aを行いたいのか、その目的とゴールを明確にしておく必要があります。後継者問題の解決なのか、個人資産の現金化なのか、それとも企業価値向上のための投資リソース獲得なのか。目的によって、最適なM&Aスキームや交渉条件が異なります。 - ビジョンやバリューの確認
自社の経営理念やビジョンを踏まえたうえで、どのような相手企業と一緒になるのがベストなのかを考えます。従業員や取引先との関係を継続したい場合、買い手企業の企業文化や経営方針に関するマッチングが重要です。
4-2. 会社概要の整理
- 財務・税務デューデリジェンスを想定した書類の整備
将来的に買い手企業がデューデリジェンスを行うことを考慮し、財務諸表や納税申告書、登記情報などの書類をきちんと整備しておきます。経理処理や税務処理が不透明だと、買い手の評価に悪影響が出る場合があります。 - 組織図や人員構成の把握
組織の構造や、役員・従業員の役割・スキル・契約形態などを明確にしておくと、買い手側にとって会社を理解しやすくなります。特にキーパーソンの処遇や退任予定などは、早めに社内で方針を固めておくことが望ましいです。 - 事業内容や顧客ポートフォリオの整理
自社が持つ商品・サービス、主要顧客層、地域や業種などの営業エリアなどを整理しておき、資料としてまとめるとスムーズです。また取引条件(売上高、取引金額、支払い条件など)を一覧にしておくと、デューデリジェンス時に役立ちます。 - 許認可や知的財産権の整理
業種によっては許認可が必須となる場合があります。これら許認可の有効期限や更新状況、特許・商標などの知的財産権の保有状況も確認し、整理しておきましょう。
以上の準備段階がしっかり行われていると、買い手との交渉が円滑に進みやすくなります。一方で、情報が不備だと買い手候補の不信感を招き、交渉が破談になってしまうこともありますので、慎重に進めることが大切です。
5. アドバイザー選定
M&Aは、多額の資金や契約上のリスクが伴う高度な取引です。そのため、自社だけで進めるのではなく、専門家の力を借りることが一般的です。ここでは、アドバイザー選定のポイントを解説いたします。
5-1. アドバイザーの種類
- M&A仲介会社
売り手と買い手の仲介を行い、両者の間に立って交渉や資料準備をサポートします。手数料は成立報酬型(成功報酬)が多く、比較的小規模から中規模のM&Aで利用されるケースが多いです。 - M&Aアドバイザリー(FA)
売り手もしくは買い手の片側のみを支援し、相手方と利益相反が起きにくい形で取引を進める役割を担います。大手証券会社やコンサルティングファーム、会計事務所などが提供していることが多いです。 - 弁護士・公認会計士・税理士
デューデリジェンスや契約書の作成など、専門的な法律・会計・税務のサポートが必要となります。M&A仲介会社やアドバイザーと連携しながら実務を進めることが一般的です。
5-2. アドバイザー選定のポイント
- 専門分野や実績の確認
自社の業種・規模に合った実績を持つかを確認しましょう。業種特有の規制や取引慣習を理解しているか、過去に似た案件を扱った経験があるかは重要な判断材料です。 - 担当者の力量とコミュニケーション
アドバイザー選定で最も重要なのは「担当者の力量」と言っても過言ではありません。M&Aには長期のプロセスがかかるため、担当者との信頼関係や相性も見極める必要があります。 - 報酬体系の確認
成功報酬型なのか、着手金や月額報酬があるのか、また成功報酬率は何%程度なのかなど、費用面の条件もしっかりと確認しておきましょう。
アドバイザーの役割は、買い手候補の探索、交渉支援、デューデリジェンスのコーディネート、契約書作成支援など多岐にわたります。自社のリソースだけでは対応しきれない部分を補ってもらい、最適な条件でM&Aを実現するためのパートナーとして、慎重に選定することが重要です。
6. 買い手候補のリストアップとアプローチ
準備段階が整い、アドバイザーを選定したら、いよいよ買い手候補を探索し、アプローチを行う段階に入ります。
6-1. 買い手候補のリストアップ
- 業種・事業特性のマッチング
まずは自社の強みや事業領域に近い業種や、市場で相互シナジーが生まれそうな分野の企業を洗い出します。アドバイザーが保有するネットワークやデータベースを活用できるケースも多いです。 - 企業規模や財務状況の確認
M&Aの成立には、買い手側に十分な資金力や信用力があることが重要です。規模感が合わない企業が相手だと、交渉が難航したり破談したりする恐れがあります。 - 買い手の目的や戦略の分析
買い手が自社に求めているもの(市場拡大、技術力、顧客基盤など)を事前に分析し、買い手候補ごとにどのような統合シナジーを描けるのかを整理しておきます。
6-2. アプローチ方法
- テーザー(概要書)やプロファイルの提示
買い手候補に対し、自社の概要や強み、財務状況などをまとめた「ノンネームシート」や「テーザー」と呼ばれる資料を提示する場合があります。これは企業名を伏せた状態で、買い手に興味を持ってもらうための第一歩です。 - ファーストミーティング(初期面談)
興味を示した買い手候補と初回のミーティングを行い、事業内容や経営方針などを大まかに説明します。ここでお互いのM&Aに対する考え方やシナジーが見込めるかを判断します。 - 情報交換と条件のすり合わせ
初期段階で買い手側が大きな問題意識や懸念を示した場合、早い段階で解消できるよう対応します。条件面(希望売却価格、株式譲渡か事業譲渡かなど)の大枠をすり合わせることも重要です。
買い手候補とのコミュニケーションで大切なのは、「自社の事業価値を正しく伝えること」と「相手のニーズを的確に把握すること」です。ここでの情報交換が不十分だと、後々のデューデリジェンスや価格交渉の段階でトラブルが生じる可能性があります。
7. 秘密保持契約(NDA)の締結
買い手候補との初期面談を経て、より踏み込んだ情報交換を行う際には、秘密保持契約(NDA: Non-Disclosure Agreement)の締結が必要となります。
7-1. NDAの重要性
M&Aでは、機密情報や経営戦略の核心に触れる内容が議論されます。これらの情報が外部に流出すると、競合に対する優位性の喪失や信用リスク、取引先との関係悪化など、重大な問題を引き起こす恐れがあります。そこで、両社間で秘密保持契約を結ぶことで、情報漏洩を防ぐ仕組みを作ります。
7-2. NDAの内容
- 秘密情報の定義
具体的にどの範囲の情報が「秘密情報」に該当するのかを明確にします。財務資料、顧客リスト、営業計画などは一般的に秘密情報とされることが多いです。 - 利用目的と禁止事項
開示された情報をどのような目的で使用し、どのような行為が禁止されるのかを明示します。通常は「本件M&A検討のため」という利用目的が定められます。 - 契約期間・損害賠償
NDAの有効期間や、違反があった場合の損害賠償の有無についても定める必要があります。一般的にはM&A交渉が終了した後も、一定期間秘密保持義務が継続するようになっています。
NDAを締結することで、より詳細な財務情報や顧客情報などを安心して開示し、具体的な交渉を進めることが可能となります。ただし、NDAはあくまで「契約上のルール」であり、完全な情報漏洩防止を保障するものではありません。相手先企業の信頼性やコンプライアンス体制もしっかりと見極めることが大切です。
8. 意向表明書(LOI)・トップシートの取り交わし
秘密保持契約の締結後、買い手との協議を重ねて一定の合意形成が進んだ段階で、意向表明書(LOI: Letter of Intent)やトップシートと呼ばれる簡易的な契約書を取り交わすことがあります。
8-1. LOI・トップシートの位置づけ
LOIやトップシートは、買い手と売り手が初期的に合意した条件を文書化するもので、最終的な契約と比べて拘束力は弱いことが一般的です。しかし、主に以下のようなポイントを整理しておくことで、デューデリジェンスや本格的な価格交渉に進む準備を整えます。
- 取引スキーム
株式譲渡や事業譲渡、合併など、どのスキームでM&Aを進めるかを明示します。 - 暫定的な売却価格・条件
買い手が提示するおおよその買収価格や支払いスケジュール、譲渡後の経営体制などの条件を整理します。 - 独占交渉権
一定期間、売り手が他の買い手候補と交渉しない「独占交渉期間」を設ける場合もあります。これは買い手側がデューデリジェンスに注力できる環境を整えるための措置といえます。
8-2. LOI・トップシート作成の注意点
LOIの段階では正式な契約ではないため、細部が流動的であっても構いません。ただし、あまりに曖昧なままだと後の交渉で大きなズレが生まれることがありますので、主要な条件(価格や支払い条件、雇用継続方針など)はできる限り具体的に示しておくと良いでしょう。
また、独占交渉権を設定する場合には、期間や解除条件を明確に取り決めることが重要です。独占交渉中は他の買い手候補と接触しないルールとなるため、万が一交渉が決裂した場合のリスクも考慮して決める必要があります。
9. デューデリジェンス(DD)の実施
LOIやトップシートが交わされ、おおまかな条件合意が得られたら、買い手は売り手の実態を詳細に調査するデューデリジェンス(DD)を実施します。デューデリジェンスは、M&A取引の成否を左右する重要な工程です。
9-1. デューデリジェンスの種類
- 財務デューデリジェンス
売り手企業の財務状態や会計処理を検証し、将来の収益性やリスクを分析します。売り手企業が提供する財務諸表だけでなく、原価計算の妥当性や在庫評価の適切性などを確認することもあります。 - 税務デューデリジェンス
税務申告の正確性や未払税金の有無、税務調査で問題が発生する可能性などをチェックします。過去の損益計算や税金の繰延資産など、詳細に調査されます。 - 法務デューデリジェンス
契約書や許認可、訴訟リスク、知的財産権など、法的リスクを洗い出す工程です。労働関連の契約や不動産契約など、多岐にわたる書類の確認が必要です。 - ビジネス・商務デューデリジェンス
顧客基盤や製品・サービスの競合優位性、市場シェアや将来性など、事業内容に関する調査を行います。買い手が統合後にどのような成長が見込めるかを検証する段階です。 - 人事・労務デューデリジェンス
従業員の雇用形態や給与体系、福利厚生、労働組合との関係などを調査し、潜在的な人事リスクを把握します。経営者の退任やキーパーソンの処遇についても議題となります。
9-2. 売り手が注意すべきポイント
- 正確かつタイムリーな情報提供
デューデリジェンスでは多数の書類提出依頼が来ます。求められた情報をできる限り正確に、期限内に提供することが重要です。不十分や遅延が続くと、買い手側の不信感を招き、取引が破談になるリスクがあります。 - リスク情報も隠さず開示
企業には少なからず問題やリスクが存在します。これを意図的に隠蔽すると、後に重大なトラブルに発展しかねません。買い手が把握したうえで契約条件を調整することが望ましいです。 - 専門家のサポートを活用
デューデリジェンス対応は専門的な知見が求められます。弁護士や会計士などの専門家に相談しながら資料を整備し、正確性を高めることが大切です。
このように、デューデリジェンスは買い手にとっても大きなコストと時間がかかる作業ですが、売り手も協力的な姿勢を示すことでスムーズな交渉を進められるでしょう。
10. 価格交渉と最終契約書の締結
デューデリジェンスを経て、買い手が把握したリスクや追加情報を踏まえて、最終的な譲渡価格や取引条件の交渉が行われます。
10-1. 価格交渉のポイント
- 企業価値評価の根拠
買い手は、デューデリジェンスの結果をもとに企業価値(株式価値)を算出します。売り手側も自社の強みや将来キャッシュフローなどを積極的にアピールしつつ、合理的な根拠を提示することが重要です。 - リスク要因に対する調整
デューデリジェンスで発見された潜在的な債務や訴訟リスクなどが価格に影響する場合があります。買い手が提示する価格減額要請に対し、売り手は反論材料やリスク低減策を提示することで、価格交渉を有利に進めることができます。 - 支払い条件・エARNOUT
大手企業による買収などでは、一部をアーンアウト(買収後の業績に連動した追加支払い)に設定する例があります。これは、買収後に事業が順調に成長すれば追加報酬が得られる仕組みであり、両社のモチベーションを一致させる効果があります。
10-2. 最終契約書(SPA)の内容
最終的な価格や取引条件が合意に達したら、正式な契約書(SPA: Share Purchase Agreement もしくは事業譲渡契約書など)を締結します。主な内容は以下のとおりです。
- 取引スキーム・株式数・価格
株式譲渡であれば「譲渡株式数と譲渡価格」、事業譲渡であれば「譲渡する資産・負債の範囲や対価」が明記されます。 - クロージング条件
許認可の取得や融資の実行など、取引が成立するための条件を設定します。条件が満たされない場合には取引が中止となる場合もあります。 - 表明・保証(レプ&ワラント)
売り手が自社に関して「訴訟がない」「財務資料が正確である」などを表明・保証します。違反があった場合の損害賠償や補償についても定めます。 - 違反時の救済措置
万が一、契約違反が起きた場合の救済措置(解除権、損害賠償請求など)を定めます。
契約書の作成や精査には、弁護士をはじめとする専門家のサポートが必須です。表明・保証の範囲や違反時の責任追及など、細部にわたって取り決めておくことが、将来的なトラブル回避につながります。
11. クロージングと引き継ぎ
最終契約書を締結した後、クロージング(実行)に向けて最終的な手続きを進めます。クロージングには、通常以下のような作業が含まれます。
- 各種許認可の取得
業種によっては、譲渡に伴う行政への届出や許可の再取得が必要となる場合があります。これらを円滑に進めるため、行政手続きのスケジュールを事前に把握しておきましょう。 - 資金決済
譲渡代金の支払いおよび株券(実際には電子化が進んでいるため、株主名簿の書換え)が行われ、正式に株式が買い手へ移転します。銀行口座を指定する、支払いのタイミングを確認するなど、細やかな調整が求められます。 - 会社書類の名義変更や引き継ぎ
代表印や銀行口座名義など、企業運営に必要な名義変更手続きが発生します。重要書類の保管場所やパスワードなど、日常のオペレーションに関わる情報も適切に引き継がなければなりません。 - 従業員・取引先への周知
クロージング後は、従業員や主要取引先、金融機関などに対し、オーナーや経営体制が変わった旨を正式に知らせる必要があります。従業員には雇用条件や新体制での役割、取引先には取引条件の継続や変更点などを誠実に説明しましょう。
これらのクロージング作業が完了すれば、譲渡企業は法的・実務的にも買い手のもとへ移行したことになります。とはいえ、この段階で「M&Aがすべて終了」というわけではなく、買い手企業とスムーズな連携を図るためのPMI(Post Merger Integration)など、その後のフォローが重要になります。
12. PMI(Post Merger Integration)と統合プロセス
PMIとは、M&A成立後に両社の経営資源や組織、人事制度などを統合し、シナジーを最大化するプロセスを指します。譲渡企業(売り手)の視点では、PMIがどのように進められるかを理解し、スムーズな移行に協力することが求められます。
12-1. PMIの重要性
M&Aの目的を達成するためには、クロージング後の統合プロセスが極めて重要です。買い手企業が期待する「事業の拡大」や「技術・ノウハウの獲得」「コストシナジー」などは、統合の進め方次第で大きく変わってきます。PMIがうまくいかず、従業員のモチベーション低下や顧客離れが起きてしまうと、せっかくのM&Aが失敗に終わる可能性もあります。
12-2. PMIにおける主な課題と対応
- 組織文化の違い
買い手企業と売り手企業では企業文化や価値観が異なる場合があります。組織文化を丁寧にすり合わせ、従業員が安心して働ける環境づくりが大切です。 - 人事・労務制度の統合
給与体系や福利厚生、評価制度などが異なる場合、公平性とモチベーション維持の観点から適切な統合方法を検討します。経営者や管理職、キーパーソンの処遇についても明確にする必要があります。 - システム・ITの統合
基幹システムや顧客管理システムの統合は、両社の業務プロセスを効率化するうえで欠かせません。短期間で統合が進まない場合、社員の負担が大きくなる可能性があるため、スケジュールと予算を十分に確保しながら進めることが望ましいです。 - ブランドや営業戦略の統合
買い手企業のブランドを前面に出すのか、売り手企業のブランドを残すのか、または新たに統合ブランドを立ち上げるのかなど、マーケティング戦略を含めた統合の進め方を検討します。既存顧客が混乱しないよう、周知方法やタイミングに配慮が必要です。
PMIの進め方は、M&Aのスキームや企業規模、事業内容によってさまざまです。譲渡企業の経営者やキーパーソンも、買い手企業と適切にコミュニケーションを取り、協力的に統合を進めることで、M&Aの成功確率が大きく高まります。
13. M&A後の注意点
クロージングとPMIを経て、経営体制が新たなフェーズへ移行した後にも、売り手側が認識しておくべき注意点があります。
13-1. 表明・保証違反の可能性
最終契約書で定めた表明・保証に反する事実が、クロージング後に発覚した場合、買い手企業が損害賠償を請求する可能性があります。意図的な虚偽記載がなくとも、情報開示が不十分だった場合は注意が必要です。
13-2. 競業避止義務
契約によっては、譲渡後一定期間、同一または類似の事業を行わない「競業避止義務」が定められていることがあります。経営者が退任後に新たな事業を始める際には、この規定を順守する必要があります。
13-3. 非公表条件の遵守
M&Aの詳細条件や譲渡価格など、両社間で非公表とする契約がある場合、情報漏洩に気を配り続ける必要があります。特に株主やメディアへの公表範囲などは、契約で厳密に定められることがあります。
13-4. 売り手経営者の残留期間
M&A後に一定期間、旧経営者やキーパーソンが経営に携わることが想定されるケースも少なくありません。引き継ぎやPMI完了に向けたサポートを行うためですが、残留期間や役職、報酬などについては事前に明確に取り決めておくことが大切です。
14. まとめ
本記事では、譲渡企業(売り手)の視点から、M&Aの流れを時系列に沿って解説してまいりました。主なステップを振り返ると以下のとおりです。
- M&Aの目的・ゴールの整理
後継者問題の解決や事業拡大、個人資産の現金化など、M&Aを行う理由を明確化します。 - 準備段階での情報整理
財務諸表や組織図、許認可、知的財産など、デューデリジェンスを見据えた書類整備が欠かせません。 - アドバイザーの選定
M&A仲介会社やアドバイザリー、弁護士・会計士などの専門家のサポートを受けることで、スムーズな交渉を実現しやすくなります。 - 買い手候補の探索とアプローチ
自社の事業特性や市場シナジーを考慮しながら、適切な買い手候補に接触します。 - 秘密保持契約(NDA)の締結
機密情報を保護しながら、詳細情報を開示し交渉を続けます。 - 意向表明書(LOI)の取り交わし
初期合意として大枠の条件や取引スキーム、独占交渉権などを整理します。 - デューデリジェンス(DD)の実施
財務・税務・法務・ビジネスなど多岐にわたる調査に協力し、買い手の信用を高めます。 - 価格交渉と最終契約書の締結
DD結果を踏まえて最終的な価格や取引条件を詰め、SPAなどの契約書を取り交わします。 - クロージングと引き継ぎ
資金決済や名義変更、従業員・取引先への周知などを行い、正式にオーナーシップが移転します。 - PMIとM&A後のフォロー
組織統合やシステム連携、人事制度の整合などを進め、M&Aのシナジーを最大化します。
M&Aは、一朝一夕で進められる取引ではありません。ときには数カ月から1年以上をかけて交渉・検討を行い、最良の結果を追求していくことが求められます。また、売り手にとっては企業と従業員の未来を託す重大な決断でもあります。相手企業の文化やビジョンへの共感、従業員や取引先への配慮など、単に金銭的なメリットだけではない多角的な視点を持ち合わせることが重要といえます。
これまで培ってきた事業を新たなステージへと引き上げるためのM&Aは、決して「会社を手放す」だけの行為ではありません。むしろ、次の経営者や組織へバトンを渡し、事業を継続・発展させるための前向きな戦略的選択ととらえることができます。この記事が、譲渡企業の皆さまのM&A検討に少しでもお役に立てれば幸いです。今後の成功とさらなる発展を心よりお祈り申し上げます。

株式会社M&A Do 代表取締役
M&Aシニアエキスパート・相続診断士
東京都昭島市出身。慶應義塾大学理工学部を卒業後、大手M&A仲介会社にて勤務し、その後独立。これまで製造業・工事業を中心に友好的なM&Aを支援。また父親が精密板金加工業、祖父が蕎麦屋、叔父が歯科クリニックを経営し、現在は父親の精密板金加工業にも社外取締役として従事。