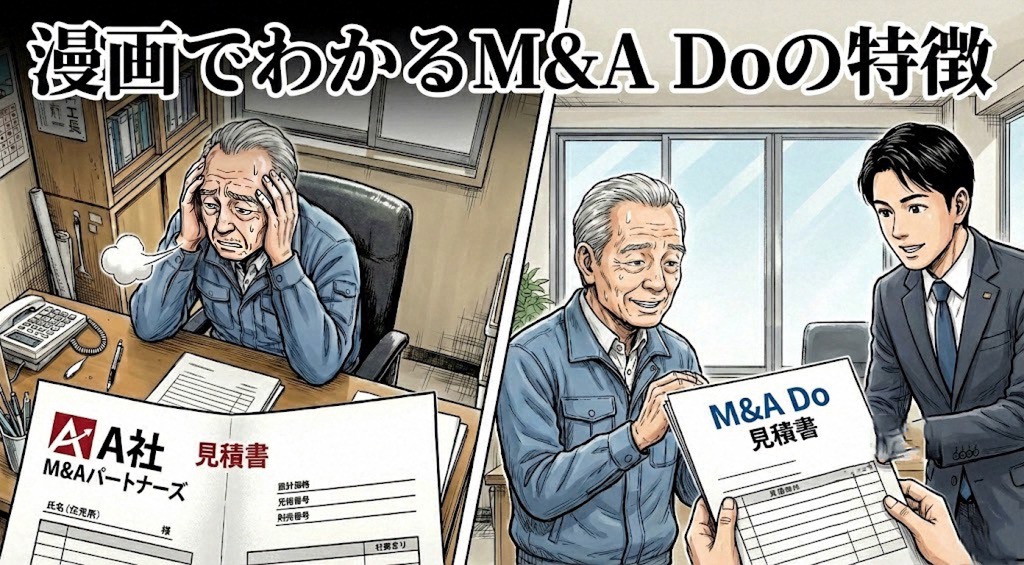第三者割当増資とは
第三者割当増資とは、企業が新たに発行する株式を特定の第三者(既存株主以外)に有償で引き受けてもらい資金調達する方法です。通常、取引先企業や役員、ベンチャーキャピタルなど、発行企業と関係の深い第三者に対して行われます。第三者割当増資で資金を受け入れることで、新たな資本提携関係を構築したり、経営再建の一環としたりするケースが多く見られます。第三者割当増資は広義のM&Aに含まれるスキームの一つでもあります。増資を引き受ける第三者が戦略的パートナーとなることで、通常の業務提携より強固な協力関係(資本業務提携)を築ける点が特徴です。特定の企業との資本・業務提携の強化、安定株主の確保、さらには敵対的買収防止(ホワイトナイトによる救済策)など、第三者割当増資は様々な目的で活用されます。例えば、敵対的TOBに対抗するために友好的な第三者に新株を割り当てて持株比率を変動させ、買収を阻止するといった防衛策として用いられることもあります。
他の資金調達手段との比較
第三者割当増資は、他の資金調達手段と比べて迅速かつ柔軟に行える点が魅力です。以下に主な手段との違いを比較します。
-
株式譲渡(M&A): 既存株主が保有株式を第三者に譲渡する方法です。株式譲渡では会社自体に資金は入りませんが、買い手企業は煩雑な新株発行手続きを経ずに経営権を直接取得できます。そのため完全子会社化など迅速に経営権を移転したい場合には適しています。一方、第三者割当増資は新株を発行することで資金調達も同時に実現でき、既存株主が残るため一度に100%の株式取得はできません。M&Aの場面では、相手企業を引受先として新株発行するだけで資本関係を構築できるため、比較的簡易に部分的な参加を得る手法と言えます。迅速に完全買収したい場合は株式譲渡の方が向きますが、戦略的提携目的であれば第三者割当増資が有効です。
-
公募増資(第三者割当以外の新株発行): 不特定多数の投資家に広く新株を募集する方法です。公募により多額の資金を集め株主数も増やせるメリットがありますが、誰が株主になるか選べないため場合によっては思わぬ企業に株式を握られるリスクもあります。例えば敵対的買収者が応募してくる可能性も否定できません。この点、第三者割当増資であれば引受先を発行企業が指定できるため、望ましいパートナーだけに出資を仰ぐことができます。資金調達のスピード面でも、公募増資は募集や審査に時間がかかるのに対し、第三者割当増資なら交渉がまとまり次第速やかに増資を実行できる利点があります。
-
銀行融資・社債発行(負債による資金調達): 金融機関からの借入や社債発行は返済義務のある資金調達です。利息負担や担保の提供が必要になる一方、株式の希薄化は起こらず既存株主の持分比率は維持されます。第三者割当増資は返済不要の自己資本を得られるため、財務体質を健全化しつつ成長資金を確保できる点が大きなメリットです。ただし、後述するように株主構成が変化する影響には注意が必要です。
以上のように、第三者割当増資は資金調達と戦略的提携を同時に実現できるユニークな手法と言えます。他の手段と比較した強み・弱みを理解し、自社の目的に合致する場合に選択肢となるでしょう。
国内IT企業におけるM&Aと第三者割当増資の活用事例
近年、国内IT業界では大企業とスタートアップ企業による資本業務提携が活発化しており、その多くで第三者割当増資が活用されています。以下に代表的な事例を成功・失敗の両面から紹介します(主に成功事例に焦点を当てます)。
-
楽天と日本郵政(2021年): 日本を代表するITサービス企業である楽天は、物流網を持つ日本郵政と約1,499億円の資本業務提携を締結しました。日本郵政は楽天の第三者割当増資を引き受けて約8.32%の株式を取得し、両社は物流、DX、モバイル分野での連携を強化しています。この提携により楽天は巨大な物流インフラとのシナジーを得て事業競争力を向上させ、日本郵政もEC分野での存在感強化を図りました。大規模な第三者割当増資による典型的な成功例と言えます。
-
伊藤忠商事とフリークアウトHD(2019年): 広告Tech企業フリークアウト・ホールディングスは、大手商社の伊藤忠商事から資本参加を受けました。伊藤忠はフリークアウトHDの第三者割当増資約377億円分を引き受けるとともに、創業者から株式の一部を買い取り、議決権ベースで18.0%を取得する第2位株主となりました。伊藤忠は顧客データ基盤の強化を目的に出資し、デジタルマーケティング領域で協業を開始しています。このケースでは大企業が新興IT企業に戦略出資し、自社バリューチェーンにテクノロジーを取り込む成功パターンとなりました。
-
コムチュアとセンシンロボティクス(2020年): 独立系SI企業のコムチュアは、産業用ドローン開発のスタートアップであるセンシンロボティクスとの資本業務提携で、第三者割当増資約3億円を引き受けました。さらにセンシン社は同時にENEOSや伊藤忠系企業など合計9社を引受先とする増資を実施し、総額22億円の資金調達に成功しています。この事例では、大手IT企業のみならず異業種の複数企業が出資者となり、ドローン技術の実用化に向けた幅広い支援体制が築かれました。ベンチャー企業が第三者割当増資によって複数の戦略投資家を呼び込み成長加速を狙う典型例です。
-
ロゼッタとオルツ(2020年): 機械翻訳のロゼッタは、パーソナル人工知能(P.A.I.)開発のベンチャー企業オルツに対し、2億5,000万円の第三者割当増資を引き受けました。ロゼッタは自社AI事業とのシナジーを期待し、オルツとの技術提携を深めています。比較的小規模ながら、先端技術領域での提携によってお互いのサービス強化につなげた例です。
-
LiveSmartとセコム(2021年): IoTスマートホーム企業のLiveSmartは、セキュリティ大手セコムと第三者割当増資による資本提携契約を締結しました。約3億円の出資を受け入れたと報じられており、以降両社は共同で賃貸住宅向けスマートサービスを開発するなど協業を進めています。大企業の資本参加によりスタートアップのサービス展開力が増し、出資企業側も新規事業領域を拡大できた好例です。
以上のような成功事例では、資本提携によるシナジー効果が明確である点が共通しています。大手企業は新興企業の技術やサービスを取り込むことで自社の競争力強化を図り、ベンチャー企業側も豊富な資金と信用力により成長スピードを上げています。一方で失敗事例も存在します。想定した効果が得られず資本提携が解消されたケースとして有名なのが、国内小売大手西友と米ウォルマートの提携です。ウォルマートは2002年に西友に資本参加(当初株式の一部取得)し経営再建を試みましたが、戦略のミスマッチにより業績は伸び悩みました。結局2008年に完全子会社化まで踏み切ったものの状況は改善せず、2020年にウォルマートは西友株の85%を楽天と投資ファンドに売却する結果となりました。提携から子会社化まで投じた約2,500億円に対し、西友売却時の企業価値は約1,725億円と目減りしており、この資本業務提携は失敗だったと言えます。この例は小売業界ですが、シナジーが発揮できなければ提携自体が価値を生まないことを示しています。IT業界でも、提携先との戦略の食い違いや市場環境の変化によっては、当初期待された成果が得られず出資を引き上げざるを得ないケースが起こりえます。
メリットとデメリット
第三者割当増資を活用することで得られるメリットは多い一方で、留意すべきデメリットやリスクも存在します。企業がこの手法を検討する際に重要なポイントを整理します。
メリット(利点)
-
迅速な資金調達: 第三者割当増資は必要な資金をスピーディーに確保できる手段です。公募増資のような募集期間を要さず、特定の引受先との交渉成立後すぐに実行できるため、資金繰りを急ぐ局面で有効です。資金繰り難や成長投資の機会に対し、タイムリーに資本注入できる点は大きなメリットです。
-
戦略パートナーの獲得とシナジー創出: 出資を受けることで、引受先企業との関係を強化し強力なパートナーシップを築けます。例えば上記事例のように、大企業からの出資はその企業との資本業務提携を意味し、営業協力や技術提供などさまざまなシナジー効果が期待できます。単なる業務提携に比べ資本の結びつきがあることで協業姿勢が強まり、ノウハウ共有や販路拡大など事業規模を加速的に拡大できます。
-
信用力・企業価値の向上: 引受先に信用力の高い企業を選定できる点も利点です。有力企業や著名な投資家からの出資は、発行企業に対する市場や取引先からの信用力アップにつながります。実際、将来性が評価され著名企業から出資を受けた場合、マーケットは成長期待を織り込んで株価が上昇傾向になることもあります。このように第三者割当増資は資本増強だけでなく企業価値向上の契機ともなりえます。
-
自己資本比率の強化(財務改善): 調達した資金は負債ではなく自己資本として計上されるため、返済義務がありません。借入では財務レバレッジが高まりますが、増資であれば自己資本比率が向上し財務体質の健全化に寄与します。自己資本の充実により将来的な追加借入の信用力も高まるなど、財務戦略上も有利です。また増資による資金は原則課税対象とならず(資本取引のため収益には計上されない)、全額を事業投資に充当できるのも利点です。
-
手続きの柔軟性: 公開会社であれば取締役会決議(場合によって株主総会決議)を経ることで実施でき、引受先との個別契約で調整可能なため、資本政策上の柔軟性があります。たとえば株式譲渡によるM&Aだと既存株主全員との契約が必要ですが、第三者割当増資なら発行会社と出資者との合意だけで済む場合が多く、スムーズです。発行価額や株数、払込日なども関係者間で自由に設計しやすい点で機動的な資金調達が可能です。
デメリット・リスク
-
既存株主の希薄化と株価下落リスク: 新株発行により発行済株式数が増加するため、既存株主の持株比率は低下します。株式が希薄化することで一株当たり利益や既存株主の影響力が減少し、場合によっては市場で株価下落を招くリスクがあります。特に発行価額が低い増資(有利発行)は既存株主の不利益が大きく、株主離れや訴訟リスクさえ孕みます。増資目的が消極的(財務悪化への対処など)と受け止められた場合、市場評価が悪化し株価にマイナス影響が及ぶ傾向も指摘されています。したがって既存株主への説明や発行条件の公正性確保が重要です。
-
経営権の希薄化・干渉リスク: 資本提携では通常、出資比率を経営支配に及ばない水準(例えば発行後議決権の1/3未満など)に抑えることが多いですが、それでも新たな大株主の存在は経営に影響を与えます。引受先が議決権上位に来れば、重要事項で反対されたり、取締役派遣を求められたりと意思決定に干渉を受ける可能性があります。最悪の場合、当初は少数出資だったパートナーが後に追加取得を図り経営権を奪われるリスクも考えられます。資本提携は完全買収ほどの支配権移転は伴わないものの、経営の独立性が低下し得る点はデメリットです。
-
提携関係の固定化と柔軟性欠如: 一度第三者割当増資を受け入れると、安易に資本関係を解消できない点にも注意が必要です。通常の業務提携なら契約解消で関係を断てますが、資本提携を解消するには相手が保有する株式を買い戻す等の手段が必要になります。しかし増資で得た資金は既に設備投資や成長投資に使ってしまっていることも多く、提携解消のための資金準備はハードルが高いのが実情です。このように資本提携は身動きが取りにくい側面があり、提携後に戦略変更や相手企業の事情変更があっても簡単には関係を見直せないデメリットがあります。
-
法規制への対応コスト: 第三者割当増資は既存株主の利益に重大な影響を及ぼすため、会社法・金融商品取引法・証券取引所の規則などで多くのルールが定められています。例えば有利発行に該当する場合の株主総会特別決議や、公正な払込金額の算定手続き、重要な資本異動に関する適時開示義務などです。これらの遵守には専門的な検討や事前準備が必要で、時間的・費用的コストが発生します。適切な手続きを怠れば増資の差止め請求や無効訴訟に発展するリスクもあるため、法務・財務面での慎重な対応が求められます。
以上のように、第三者割当増資にはメリットとデメリットが表裏一体の関係で存在します。資本提携による成長加速の魅力と、株主構成変化によるリスクを天秤にかけつつ、適切な条件設定とガバナンス体制の整備が重要です。
法的・会計的観点
会社法の規制と手続き
第三者割当増資を行うには、会社法上の厳格な手続きを遵守する必要があります。公開会社(譲渡制限のない株式会社)の場合、取締役会で募集事項(発行株数・価格・割当先など)を決定し、原則として株主総会の承認は不要です。ただし、発行価格が時価に比べ著しく低い有利発行に該当する場合や、割当先が支配株主となる恐れがある場合などは、株主総会の特別決議が要求されます。一方、非公開会社では第三者割当による新株発行は既存株主の持分比率変動を伴うため、常に株主総会特別決議が必要となります。発行手続き後は払込期日から2週間以内に増資の登記を行い、新株主名簿の整備など事務対応も求められます。さらに金融商品取引法上、上場企業が第三者割当増資を行う際には適時開示や大量保有報告などのディスクロージャー義務があります。不公正な増資による既存株主の権利侵害を防ぐため、証券取引所も独自の基準を設けており、大量の株式発行(一般に発行済株式数の25%以上など)の場合には第三者割当に頼らず株主割当増資(既存株主への権利割当)を優先するよう求めるガイドラインがあります※。加えて、第三者割当増資によって新たに筆頭株主や親会社が生じた場合には、取引所への報告書提出や一定の審査が及ぶことがあります。会社法上、手続きを踏まずに第三者割当増資を強行すれば、株主による差止め請求や発行無効訴訟のリスクがあります。実際に過去には増資差止め仮処分が認められた例もあり、経営陣には株主の利益を不当に害さないよう十分な注意義務が課せられています。従って、増資の必要性・合理性を株主や市場に説明し、法定のプロセスを丁寧に踏むことが不可欠です。
※ 東京証券取引所のルール:「25%ルール」として、希薄化率25%超の第三者割当増資を原則禁止し、やむを得ず行う場合は株主による事前意思確認や独立役員会での審議を要求する等の運用がなされています。
税務・会計処理のポイント
第三者割当増資で受け入れた資金は資本剰余金などとして計上され、企業の貸借対照表上の純資産が増加します。増資による資金受入れ自体は資本取引であり収益ではないため、法人税の課税対象にはなりません。そのため調達資金は全額を成長投資や運転資金に充当できる利点があります。ただし発行手続き時には登録免許税(増資額の0.7%等)の負担や、公証人による定款変更認証費用などが発生します。また増資により資本金が1億円以上になると地方法人課税の外形標準課税適用など税負担区分が変わる点にも留意が必要です。
一方で、発行価額が公正価値とかけ離れて低い場合(有利発行)は税務上の問題が生じる可能性があります。会社側には課税がなくとも、株式を引き受けた側(投資家側)では払込額と時価の差額が経済的利益とみなされ課税対象となり得ます。具体的には、引受人が個人なら一時所得(引受人が自社役員等なら給与所得)、法人なら受贈益として課税される可能性があります。そのため引受先に過度な利益を与えるような発行条件は避け、適正な時価算定に基づく払込金額設定が重要です。
会計上は、新株発行による払込資本のうち資本金への組入れ額と資本準備金への振替額を決定する必要があります(会社法では払込金額の1/2を超えない範囲で資本準備金に振り替え可能)。発行費用(証券代行手数料等)は原則として資本剰余金から控除して処理します。増資後は一株あたりの純資産が変動し既存株主の経済価値に影響するため、必要に応じて株式分割や併合、利益配分策の見直しなどで調整を図ることも検討されます。
株主や投資家への影響
第三者割当増資は発行会社・引受先・既存株主という三者それぞれに異なる影響を及ぼします。
-
**発行会社(資金調達者)**にとっては、前述の通り自己資本増強による財務改善と成長資金の獲得につながります。ただし同時に既存株主構成が変化し、新たな大株主との関係性が経営上の重要事項となります。場合によっては出資契約上、重要事項について引受先の事前同意条項や役員派遣契約などが盛り込まれることもあります。経営の自由度がある程度制約される点について、発行会社は株主間契約等で明確にルール設定を行うことが求められます。
-
**引受先(投資家・提携先企業)**にとっては、対象企業への一定比率の株式取得により議決権を得るため、経営に対して発言力を持つことができます。もっとも通常の資本業務提携では経営権取得に至らない範囲の出資が多く、あくまでマイノリティ出資である場合が一般的です。引受企業は出資先の将来成長によるキャピタルゲインや業務提携による事業シナジーを目的として参加しますが、思惑通りに成長しなかった場合は株価低迷や配当無しといった投資リスクを負います。また上場企業が他社に出資する場合、取得株式は財務諸表上投資有価証券として計上され、市場価格の変動によって評価損益が発生する可能性もあります。従って投資家側も、戦略目的だけでなく財務面での影響も考慮したうえで出資判断を下す必要があります。
-
既存株主にとっては、自身の持株比率低下による影響が最大の関心事です。特に経営支配権に関わる筆頭株主の地位が変動するケースでは、今後の経営方針に不安を感じる株主もいるでしょう。そのため発行会社は株主に対し、なぜ第三者割当増資が必要なのか、提携によって企業価値がどう向上するのかを丁寧に説明し理解を得る努力が欠かせません。また場合によっては既存株主に新株予約権を無償割当てする(いわゆるワラントによる希薄化緩和策)などの配慮が取られることもあります。増資後の株主構成の変化はIR上の重要事項であり、公平性と透明性をもって対処することが企業の信用維持に繋がります。
総じて、第三者割当増資は発行会社にとって強力な資金調達・提携手段ですが、その実行には多面的な利害調整と法的・会計的な専門対応が求められます。発行会社は株主価値の最大化という観点を常に念頭に置き、出資受入れのメリットがデメリットを上回るか慎重に判断することが大切です。
最新のトレンドと今後の展望
昨今の国内IT業界では、第三者割当増資を活用した資本提携がオープンイノベーションの主要な手段として定着しつつあります。特にAI、IoT、DX(デジタルトランスフォーメーション)などの急成長分野では、大企業がスタートアップに出資する動きが顕著です。変化の激しいIT技術をいち早く取り入れることが生命線となっており、自社開発にこだわらず外部の力を資本提携を通じて取り込む戦略が広がっています。例えば先述のセコムによるLiveSmart出資や、ENEOS・伊藤忠によるセンシンロボティクス出資などは、異業種企業がITベンチャーの技術を求めて資本参加する典型例です。投資家側の関心分野もAI解析、SaaS、フィンテック、ブロックチェーンなどデジタル新領域に集中しており、その分野の有望企業には国内外から資金が集まりやすい状況です。
IPOとの関係性という点では、第三者割当増資はしばしばIPO前のプレマネーファイナンス(上場前最終の資金調達ラウンド)として活用されます。ベンチャー企業にとって、上場前に戦略的投資家から出資を受けることで資本増強し事業規模を拡大するとともに、上場後の安定株主を確保する効果が期待できます。また、市場環境によってIPOを急がずに非上場のまま大型増資を行って成長資金を得るケースも増えています。近年ではメガベンチャーがユニコーン(企業評価額10億ドル超)に至るまで複数回の第三者割当増資を重ね、十分に企業価値を高めてから上場する傾向も見られます。
反対に上場企業が敢えて第三者割当増資による資金調達を行うのもトレンドです。楽天のように明確な提携相手が存在する場合や、ベンチャー市場から資金吸収するよりも戦略投資家からの出資を優先した方が長期的価値向上につながると判断されるケースが典型です。このようにIPOと第三者割当増資は競合する手法ではなく、企業成長ステージに応じて使い分けられる関係と言えます。
また事業承継や成長戦略においても、第三者割当増資は重要な役割を果たします。中堅規模のIT企業で後継者難に悩む場合、すぐに会社売却(株式譲渡)するのではなく、まず業界内外の有力企業に一部出資してもらい資本業務提携から始める例があります。そのメリットは、創業オーナーにとっては段階的に経営を引き継ぎつつ企業価値を高める猶予が得られ、出資企業にとっては将来の完全子会社化も視野に入れつつ相手企業を理解する時間を確保できることです。実際に資本提携を経て数年後に出資先を追加取得し子会社化するケースや、逆に提携段階で効果が上がらずそのまま資本関係を維持するケースなど様々ですが、柔軟な事業承継オプションとして第三者割当増資が用いられています。
スタートアップにおいても、創業者が自社株を売却せずに第三者割当増資によって資金調達することで、創業メンバーの持株比率を保ちつつ事業成長させる戦略が一般的です。これにより早期に経営権を手放すことなく会社を大きくし、将来的なエグジット(IPOやM&A)時点でより高いリターンを狙うことができます。最新の動向として、日本政府や産業界もスタートアップ支援策を推進しており、事業会社・VCによる出資件数は年々増加傾向にあります。IT業界では2020年代に入りDX需要の高まりから、大企業同士・大企業とベンチャーの資本提携発表が相次いでいます。「変化の激しい時代において、自社だけでなく他社の力を資本面から取り込むことが自社の持続的成長に不可欠」という認識が広がっているためです。今後もAI・ビッグデータ・Web3.0など新技術領域での提携や、地域老舗IT企業と新興企業の連携など、様々な第三者割当増資によるM&Aが続くと予想されます。その一方で、提携を成功させるには相互の強みを活かせる組み合わせであることが重要との指摘があります。単に資金を出す出されるの関係ではなく、双方の経営資源が噛み合うことで初めてシナジーが最大化されるからです。したがって提携相手の選定や提携スキームの設計はより戦略的に練られるようになるでしょう。
まとめると、第三者割当増資を活用したM&A(資本業務提携)は、国内IT業界において成長加速や新規事業創出のエンジンとして定着しています。企業にとっては、自社の課題を補完し将来の競争力を高めるための一手段であり、スタートアップから大企業まで幅広く選択肢となっています。その成功にはパートナー選びと提携後の協働が鍵を握りますが、適切に活用できれば企業価値向上とWin-Winの成果をもたらすでしょう。今後も市場の関心分野に応じて多様な資本提携が生まれ、この手法が日本企業のイノベーションと事業承継を支える重要な役割を果たし続けると期待されます。

株式会社M&A Do 代表取締役
M&Aシニアエキスパート・相続診断士
東京都昭島市出身。慶應義塾大学理工学部を卒業後、大手M&A仲介会社にて勤務し、その後独立。これまで製造業・工事業を中心に友好的なM&Aを支援。また父親が精密板金加工業、祖父が蕎麦屋、叔父が歯科クリニックを経営し、現在は父親の精密板金加工業にも社外取締役として従事。