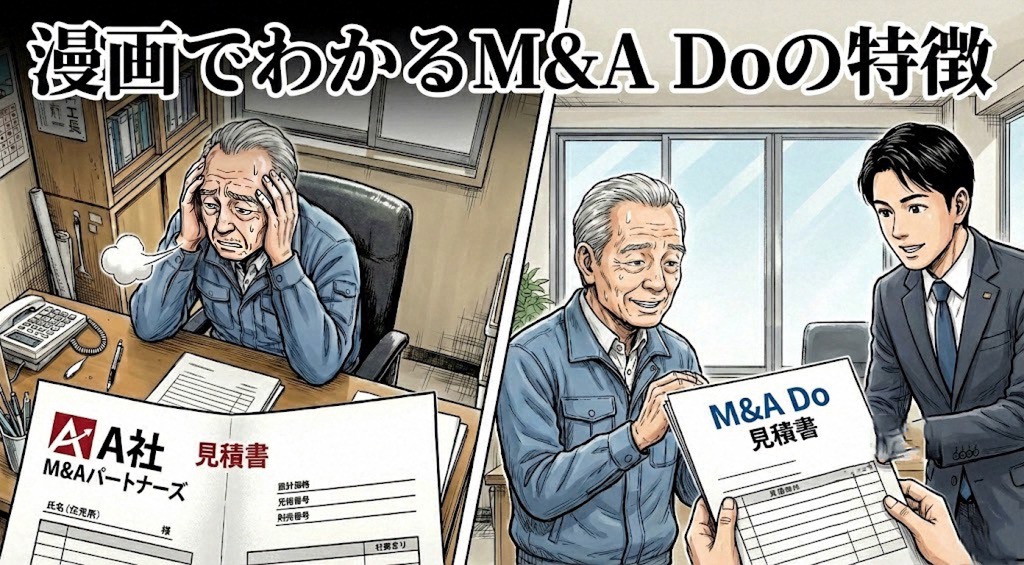本記事では、**国内M&Aの一形態である「事業譲渡」**について、その特徴や具体的事例、実務上のポイント、そして最新の動向と今後の展望を、専門家向けに詳細に解説します。事業譲渡は株式譲渡や会社分割と並ぶ主要なM&Aスキームですが、それぞれ異なるメリット・デメリットや法的・税務上の扱いがあります。本稿ではそれらの違いを整理し、近年の事例を企業名とともに紹介し、成功例と課題の残った例を比較分析します。また、事業譲渡を進める上での価値評価手法や契約・PMIのポイント、さらに現在のM&A市場における事業譲渡のトレンドや、コロナ禍・DX(デジタルトランスフォーメーション)の影響についても触れ、最後に事業譲渡を検討する企業へのアドバイスを提示します。
1. 事業譲渡の特徴
事業譲渡の定義と位置づけ
事業譲渡とは、会社の一部または全部の事業を第三者に譲渡(売却)するM&A手法です。具体的には、売り手(譲渡企業)と買い手(譲受企業)との間で売買契約等を結び、対象事業に属する**「資産・負債・契約」を個別に選定して移転する形態**を指します。事業全てを丸ごと移す場合は「全部譲渡」、一部の事業のみを切り出す場合は「一部譲渡」と呼ばれます。譲渡の対象には、工場設備や不動産といった有形資産だけでなく、債権・債務、人材、ブランド(のれん)、技術ノウハウなどの無形資産も含まれます。契約で定めれば、どの資産・負債・契約を移すかを自由に選別できる柔軟性があります。
事業譲渡は、株式譲渡や合併とは異なり会社法上の「組織再編」には該当しない取引行為(契約)です。したがって手続き面では組織再編に準じた厳格さはありませんが、会社法上の重要な意思決定として扱われ、後述するように原則として株主総会の特別決議が必要となるケースがあります。また、会社法上の競業避止義務規定により、事業を譲渡した会社は原則として譲渡後20年間、同一市町村および隣接市町村で同じ事業を営むことが禁止されます。このため、一度事業譲渡を行うと、売り手は当該事業分野から事実上撤退することになる点にも注意が必要です。
株式譲渡・会社分割との違い
株式譲渡は、会社の株主が保有する株式を買い手に売却することで経営権を移転する手法であり、対象会社の「法人格ごと」譲り渡す点で事業譲渡とは根本的に異なります。株式譲渡では会社そのものが買収されるため、対象会社のすべての資産・負債・契約が包括的に引き継がれます。一方、事業譲渡では前述の通り契約ごとに資産等を選別して移転するため、譲渡対象としない資産や負債は売り手側に残すことが可能です。この違いにより、株式譲渡では買い手が対象会社の簿外債務や偶発債務も含めすべて引き継ぐリスクがあるのに対し、事業譲渡では買い手は不要な負債を引き受けずに済むというメリットがあります。逆に言えば、事業譲渡では買い手が引き継ぎたい資産・事業のみ取得できる反面、既存の会社そのものは譲り受けないため法人格や許認可の継続性が失われる点が異なります。
会社分割(吸収分割・新設分割)も、会社の事業の全部または一部を他社に承継させる手法ですが、これは会社法上の組織再編行為に該当します。会社分割では「包括承継」といって、定められた事業に属する権利義務(契約関係や資産負債)が法律上包括的に移転します。そのため、個々の契約につき取引先や従業員の同意を得なくても一括して移せる点が特徴です。一方、事業譲渡では包括承継は認められず、基本的にすべての取引先との契約や従業員の雇用契約について個別に承諾を得て移転する必要があります。取引先が契約引継ぎに同意しなかったり、従業員が転籍に応じなかったりすると、譲受側が期待した事業の継続が損なわれるリスクがあります。この契約移行の手間が事業譲渡のデメリットの一つです。
また対価の支払い形態にも違いがあります。株式譲渡では対価は通常株主個人への金銭であり、会社分割では買い手企業の株式(分割対価として新株発行)で支払うことも可能ですが、事業譲渡では原則として金銭による支払いとなります。そのため、買い手は事業譲渡を行うには現金を用意する必要がありますが、会社分割であれば株式交付により現金不要で実行できる場合があります。さらに許認可の扱いも異なり、事業譲渡では原則事業に必要な許認可を譲受企業で新規に取り直す必要があります。会社分割の場合、一部の許認可は包括承継の一環で引き継げるものもありますが、引き継げない許認可も多いため事前確認が重要です。
以上をまとめると、事業譲渡は「必要な事業資産だけを現金売買で移転する」柔軟なスキームであり、株式譲渡や会社分割に比べて契約や許認可の再取得など実務負担が大きい一方、移転する範囲や負債をコントロールしやすい特徴があります。
法的・税務的な側面
法的手続き: 事業譲渡を行うには、会社法上いくつかの重要な手続き・要件があります。まず、譲渡企業(売り手)では原則として株主総会の特別決議による承認が必要です。会社法467条により、事業の全部、または事業の重要な一部を譲渡する場合は株主総会特別決議が要求されています(譲渡先が特別支配関係にある場合の略式手続きや、譲渡規模が小さい場合の簡易手続きでは省略可能なケースもあります)。特別決議を経ずに行われた事業譲渡は、その相手方が承知していたか否かに関わらず無効となり、誰でも無効主張できると判示した判例もあります。もっとも、実行後長期間経過してから無効を主張するのは信義則上制限される可能性があります。なお、買い手側(譲受企業)でも、大規模な事業取得で対価支払額が譲受会社純資産の5分の1超となる場合には株主決議を要すると定められています(会社法468条2項の簡易事業譲受けの要件)。さらに、事業譲渡では反対株主の株式買取請求権も認められます。組織再編と同様、事業譲渡に反対する譲渡会社の株主は、自分の株式を公正な価格で会社に買い取ってもらうことを請求できる制度があります(会社法469条)。これは少数株主の保護措置で、事業譲渡によって会社の経営に重大な変更が生じるため、離脱の機会を保証する趣旨です。
税務面: 事業譲渡では、売り手・買い手の双方に課税関係が生じます。売り手側の譲渡企業には、譲渡した事業の簿価と譲渡対価の差額(譲渡益)に対して法人税(実効税率約30%前後)が課されます。一方、株式譲渡の場合、譲渡益に対する課税主体は株主個人であり、税率は約20%(分離課税)と事業譲渡より低い水準です。このため同じ売却益でも、株式譲渡の方が売り手(株主)にとって税負担が軽いケースが多いです。特に中小企業オーナーが自社株を売却する場合、株主個人に20.315%(所得税・住民税)の譲渡益課税で済むため、事業譲渡より有利とされます。一方で、事業譲渡では売却益に法人税(約30%)がかかった上、売却益をオーナー個人に還元する際に配当課税や清算時課税が追加で発生する可能性があります。
買い手側については、事業譲渡では消費税の課税も問題となります。事業譲渡で資産を取得する行為は消費税の課税取引となるため、譲受企業は譲渡対価に含まれる消費税相当額の支払い義務が生じます(もっとも、買い手が課税事業者であれば仕入税額控除により実質的な負担は中立になります)。これに対し株式譲渡は消費税非課税取引であるため、事業譲渡のみ消費税コストが発生する点が留意されます。また、事業譲渡で土地建物を取得すれば不動産取得税や登録免許税も別途必要ですが、会社分割で承継する場合は一定要件下で非課税・減免措置が受けられる場合があります。したがって、税務上は株式譲渡が最もシンプルで負担が軽い一方、事業譲渡は法人税・消費税など即時の税負担が重くなる傾向があります。
もっとも、買い手側から見ると事業譲渡には将来的な節税メリットもあります。譲り受けた資産は原則として時価で会計計上されるため(ステップアップ)、のれんや減価償却資産として計上した分を償却費(減価償却・のれん償却)として損金算入でき、将来の課税所得圧縮につながります。特に譲受資産に含まれる無形資産(営業権など)は5年~20年で償却可能なので、買収後しばらくは減価償却費の増加による法人税の節税効果が期待できます。一方、株式譲渡では被買収会社の資産簿価は引き継がれるため(のれんは連結上計上されても個別には計上されない)、こうした資産の再評価による減価償却メリットは原則得られません。
以上のように、事業譲渡は売り手・買い手で税負担や会計処理に特徴的な違いがあります。譲渡企業側では譲渡益に法人税、譲受企業側では取得資産に消費税が発生する点や、売り手オーナーへの現金還流時の二重課税リスクなど、税務面のデメリットが存在します。その反面、買い手にとっては簿外負債引継ぎリスクを回避できたり、取得資産の償却による節税メリットが得られるなど税務・財務面のメリットもあります。
事業譲渡が選ばれるケース
上記の特徴を踏まえ、事業譲渡が選択されるのはどのような場面かを、中小企業と大企業それぞれの視点から整理します。
中小企業の場合: 中小企業のM&Aでは一般的に約9割の案件で株式譲渡が利用されているとのデータがあります。株式譲渡はオーナー社長個人にとって税率が低く手続きも簡便なため、中小企業では主流です。しかし、あえて事業譲渡が選ばれる中小企業案件も存在します。典型的なのは、譲渡企業に多額の負債や簿外債務、訴訟リスク等があり、買い手がそれら潜在リスクを引き継ぎたくない場合です。事業譲渡であれば問題のある負債や不要資産を除外して健全な事業部分だけを取得できるため、買い手に安心感を与えます。また、事業承継型M&Aでも事業譲渡は活用されます。例えば、後継者不在のオーナーが会社そのものは清算しつつ事業だけ第三者に引き継いでもらうケースです。この場合、オーナー個人にとっては株式譲渡の方が税負担は低いものの、会社に残る現預金等を清算配当で受け取ることまで考慮すれば、事業譲渡+会社清算でも総合的な手取りは大差ない場合があります(※状況により異なります)。特に不採算事業を切り離して本業に専念したい場合や、会社の法人格そのものには価値がなく負債清算予定の場合、事業譲渡で必要事業だけを売却する選択が検討されます。「会社は畳むが事業(店舗やブランド)は買い手に存続させる」というパターンは、中小企業の廃業回避策としてもしばしば見られます。さらに、買い手側に資金力があり現金買収を望む場合(例えばファンドによる買収でシンプルに現金決済したい場合)も、事業譲渡が選ばれることがあります。
大企業の場合: 大企業同士のM&Aでは、対象が事業部門単位であれば会社分割(カーブアウト)+株式譲渡のスキームが用いられることも多いですが、事業譲渡によるカーブアウトも行われます。特に、事業再編・選択と集中の文脈で、大企業が非中核事業を切り離す際に事業譲渡が活用されます。売り手である大企業から見ると、不要事業を現金化して経営資源を中核事業に振り向けるメリットがあります。買い手となる企業(場合によっては同業他社や新規参入を狙う企業)は、事業譲渡なら対象部門の負債や未承継契約を排除し、欲しい技術や設備、人材だけを取得できるため都合がよい場合があります。例えば、親会社が特定子会社の一部事業だけ他社に売却したいケースでは、当該事業を子会社から切り出して直接譲渡する方が迅速です(子会社株式の一部売却だと経営権問題が絡むため)。また、大企業の場合は許認可やブランドの継承に課題が少ないケースでは事業譲渡がしやすいです。逆に、事業譲渡だと許認可を取り直すコストが大きい業種(金融業など免許事業)では会社分割が選ばれる傾向があります。
ケース別に見る選択理由: まとめると、事業譲渡が選ばれるのは、(1) 買い手のリスク低減ニーズが高い場合(負債や不確定債務を切り離したい)、(2) 売り手に残したい事業や資産がある場合(必要な部門のみ売却)、(3) 取引の即時現金化を重視する場合、(4) 法人格の存続にこだわらない場合(事業だけ引き継げればよい)などです。例えば、不採算事業の整理には事業譲渡が適していますし、複数事業を営む会社が一事業のみ売却して他事業は引き続き自社で運営したい場合も事業譲渡となります。一方、株主が複数いて全員の合意が難しい場合や、売却後も法人格を維持して別事業を行いたい場合も、事業譲渡が用いられます(株式譲渡だと会社そのものを失うため)。実際には税負担や手続きの煩雑さとも天秤にかけて判断されますが、事業譲渡は「譲渡対象を選別できる」「現金取得できる」点で戦略的に有効な場面が多々あると言えます。
2. 国内における具体的な事例
ここでは、近年日本国内で行われた事業譲渡の具体的事例を紹介します。それぞれのケースについて経緯・目的・結果をできる限り詳しく述べ、成功裡に事業が引き継がれた例と、課題や波紋が残った例を比較分析します。
成功した事業譲渡の事例
事例①:異業種間シナジーによる旅館業の再生
ある老舗旅館(ここでは旅館Sとします)が後継者不足と業績低迷から事業継続を断念しようとしていたところ、写真スタジオ業T社がこの旅館事業を事業譲渡の形で引き受けました。T社はウェディングフォト事業を展開しており、旅館を買収後、通常の宿泊業に加えて旅館全体を使った結婚式事業やフォトスタジオ事業を展開しました。結果として旅館Sは新たなコンセプトで復活し、異業種間のシナジー効果によって事業が成功しています。
このケースでは、買い手のT社が旅館というリアルなロケーション資産を得て自社サービスを拡充でき、売り手側の旅館も従業員や施設が活かされるという双方にメリットのある結果となりました。事業譲渡スキームにより旅館の建物や設備、営業権が円滑に引き継がれたことで、新オーナーの下で事業価値が向上した好例と言えます。
事例②:老舗菓子メーカーの事業承継と存続
地方老舗の和洋菓子メーカーである白十字パーラー(長崎県佐世保市、創業50年以上)が、高齢の経営者に後継者がいないことから廃業の危機に直面していました。そこで地域スーパーマーケットチェーンのエレナ(長崎県佐世保市)が2024年末に新会社「株式会社ぽると総本舗」を設立し、白十字パーラーから菓子製造・販売事業を事業譲受しました。白十字パーラーの主力商品である佐世保銘菓「ぽると」などのブランドと製造ノウハウがエレナ側に受け継がれ、2025年以降、エレナは傘下企業を通じて地元で愛された菓子事業を継続しています。
この事例は中小企業の事業承継M&Aの成功例であり、事業譲渡によって廃業が回避され老舗ブランドが存続しました。買い手のエレナにとっても、自社スーパーで人気商品を継続販売でき集客につながる利点がありました。事業譲渡スキームにより従業員の雇用も守られ、地域経済への貢献が果たされた好例です。
事例③:大企業による非中核事業の譲渡と専門企業への引継ぎ
百貨店「大丸・松坂屋」などを擁する大手小売グループのJ.フロント リテイリング(以下JFR)は、近年本業以外の新規事業の見直しを行いました。その一環で、JFR傘下で認可外保育園を運営していた子会社「JFRこどもみらい株式会社」の保育事業を、教育サービス大手のやる気スイッチグループに事業譲渡することを決定しました。JFRこどもみらいは百貨店業とシナジーを狙って新規参入した事業でしたが、本業との親和性や収益性の観点から譲渡が判断されたものです。買い手のやる気スイッチグループは学習塾や保育事業を本業とする企業であり、今回の譲受によって自社の保育ビジネスを拡大できます。2025年4月1日付でこの保育園事業はJFRからやる気スイッチへ引き継がれる予定です。
このケースでは、大手流通グループが非中核の小規模事業を専門プレイヤーに託すことで、売り手は経営資源の集中と損失削減を図り、買い手は自社事業との相乗効果が見込める資産を獲得する、双方の戦略が合致した成功例といえます。譲渡後、保育事業は本来の専門領域である新オーナーの下で成長機会を得ることが期待されます。
以上のように、成功した事業譲渡の事例では**「買い手による事業の再活用・強化」**が実現している点が共通します。異業種の組み合わせであっても、買収側に明確な活用プランやシナジー戦略があれば事業譲渡は新たな価値創出につながります。また、事業譲渡契約の締結にあたって従業員や取引先との円滑な調整が行われていることも成功のカギです。上記事例ではいずれも、事業譲渡後に従業員の雇用が継続され、取引先との関係も大きな混乱なく引き継がれています。これは周到な事前交渉と合意形成により実現したもので、買収後のスムーズなPMI(統合)につながっています。
課題が残った事業譲渡の事例
事例④:赤字事業の譲渡による市場撤退とその後の展開(シャープの北米テレビ事業)
日本の電機大手シャープ株式会社は2015年、自社の経営再建策として北米地域のテレビ事業から撤退する決断を下しました。具体的には、シャープが北米・中南米で展開していたテレビの生産販売事業を、中国の家電大手ハイセンス(Hisense)グループに譲渡する契約を締結しました。この事業譲渡には、メキシコにあったテレビ生産子会社(Sharp Electronica Mexico社)の株式売却と、**「AQUOS」「Quattron」などシャープのテレビブランドの北米における使用許諾(ブランド供与)**が含まれていました。譲渡対価は非公表でしたが、この撤退に伴いシャープは約23億3,700万円の特別損失を計上しています。結果として、シャープは長年築いた北米テレビ市場から一時的に姿を消す形となりました。
買収側のハイセンスは譲り受けたブランドを用いて北米でテレビ販売を継続しましたが、消費者からはシャープブランドの品質低下への懸念も生じ、シャープ本体も2017年にハイセンスを特許侵害で提訴するなど、譲渡後に予期せぬ軋轢が生じる場面もありました。その後、シャープは業績回復を受けて2019年に北米テレビ市場への再参入を発表し、ハイセンスとの新たな協業関係を構築するに至っています。
この事例からは、事業譲渡による市場撤退は短期的損失を伴うものの、生き残りのための苦渋の選択であったこと、そして譲渡後のブランド管理や提携関係にも課題が残り得ることが読み取れます。シャープは結果的に再参入することでブランドを取り戻しましたが、一度譲渡した市場で再び信頼を築くには時間と追加投資が必要となりました。
事例⑤:契約交渉の不調による事業譲渡の頓挫
(※失敗事例として、仮想の一般論ベースで記述します。)ある中堅メーカーA社は、非中核部門を他社に売却すべく事業譲渡の交渉を進め、基本合意書(LOI)まで締結していました。しかし、その後A社経営陣が譲渡条件(価格や引継ぐ資産範囲)について基本合意後に一方的な変更要求を行ったため、買い手候補のB社が反発し交渉が決裂してしまいました。
このケースでは、売り手側の交渉姿勢のまずさが原因でM&A自体が不成立に終わっています。事業譲渡契約は株式譲渡に比べて詰める項目(譲渡資産の明細や個別契約の扱いなど)が多岐にわたり、互いの合意形成に時間を要します。その過程で一方が態度を翻すと信頼関係が損なわれ、破談に至るリスクが高くなります。実際、本件では売り手A社はその後他の買い手を見つけられず、譲渡を予定していた事業を縮小・整理せざるを得なくなりました。M&Aプロセス管理の失敗例として教訓的な事例です。
上記の課題事例からは、事業譲渡が必ずしも円満に成功するとは限らないことが分かります。事業譲渡はしばしば業績不振事業の切り離しや緊急避難的な撤退策として行われますが、その場合には譲渡条件が売り急ぎになるため売り手に不利な価格となったり、譲渡後の市場で競合他社にシェアを譲る結果になったりします。事業譲渡後、新オーナーで事業がうまくいかず最終的にその事業自体が消滅してしまうケースもありえます(買い手の経営能力や戦略次第では、引き継いだものの立て直せない場合もあります)。また、交渉段階の不手際やデューデリジェンス漏れによる失敗も起こり得ます。例えば、買い手が十分に調査せずに事業譲渡を受けた結果、想定外の債務や不利な契約を引き継いでしまう例も指摘されています。こうした事態は事前の専門家による精査不足が原因で、最悪の場合買収後に当該事業の巨額減損や破綻につながりかねません。
成功例と失敗例の比較から浮かび上がるのは、事業譲渡の成否は「譲渡の目的の明確さ」と「譲受後の計画・体制」にかかっているという点です。成功した事例では、売り手・買い手双方に明確な戦略目的があり、譲渡後のビジョン共有やステークホルダー調整が周到に行われています。対照的に失敗した例では、動機が場当たり的であったり交渉準備が不十分なまま進めてトラブルが発生しています。また価格交渉についても、成功例では適切な評価算定に基づきwin-winの合意が形成されていますが、失敗例では期待値の乖離や後出し交渉で信頼を損ねています。事業譲渡は契約書面だけでなく事前の合意形成プロセス全体が結果を左右するため、慎重かつ誠実な交渉姿勢と十分な情報開示・確認が重要であることが分かります。
3. 事業譲渡の実務上のポイント
事業譲渡を成功させるには、適切な事業価値の評価、抜け漏れのない契約交渉、そして譲渡後の円滑な事業統合(PMI)の各段階で専門的な対応が求められます。ここでは実務上の具体的ポイントとして、(1)事業価値の評価方法、(2)契約交渉上の留意点、(3)PMI(Post Merger Integration:買収後統合)の進め方について解説します。
事業価値の評価方法
事業譲渡における譲渡価値の評価は、基本的には企業価値評価の手法に準じて行われますが、譲渡対象が会社全体ではなく事業部門・資産単位である点に特徴があります。一般に譲渡対価の基準として用いられるのは、その事業の純資産の時価評価額+営業権(のれん)価値です。純資産時価とは、譲渡対象事業に属する資産負債を時価ベースで評価し直した金額で、これに事業の将来収益力を反映した無形の価値(のれん)を加算して事業価値を算出します。営業権(のれん)は、事業が将来生み出す超過収益力の現在価値であり、通常その事業の年平均利益の2~3年分程度で評価されることが多いです。安定性に応じて係数は調整され、景気変動の大きい業種では1~2年分、独自技術を持ち安定収益が見込める事業では5年以上をのれんとする例もあります。
たとえば対象事業の年間正常利益が1億円程度であれば、営業権価値は2~3億円(×2~3年)程度と見積もり、事業用資産の時価純資産が1億円あるなら合計3~4億円程度が譲渡価値の目安になる、という具合です。もちろん、実際の譲渡金額は売り手と買い手の交渉で決定されますが、そのベースにはこのような算定が用いられます。評価手法としては他にDCF法(将来キャッシュフローの現在価値)や類似事例との比較(マルチプル法)なども活用されます。事業単位であっても、将来の事業計画に基づきフリー・キャッシュフローを予測して現在価値合計を算出すればDCFによる評価額が得られますし、同業他社のM&A事例でのEBITDA倍率などを参考に算定することもあります。ただ、中小企業や部門単位の売買では詳細なDCFを組むのが難しい場合も多く、純資産+営業権のシンプルなアプローチが実務的に好まれる傾向があります。この際、棚卸資産や固定資産の簿価と時価の差額や、継続価値(Going Concern Value)をどう見るかが論点になります。また簿外負債の有無も重要で、環境対策費用や将来の解約損失引当など考慮すべき負債があれば純資産評価を調整する必要があります。
譲渡価格を決める交渉では、売り手は事業の将来性を強調してのれんを高く見積もろうとし、買い手はリスク要因を理由に値下げを主張するといった駆け引きが発生しがちです。適正な事業価値評価には、財務デューデリジェンスでの正確なデータ把握と、将来予測の客観性確保が欠かせません。必要に応じて公認会計士や評価機関の意見を仰ぎ、両者が納得できる評価根拠を用意することが大切です。
契約交渉のポイント
**事業譲渡契約(Business Transfer Agreement)**の交渉では、株式譲渡契約とは異なる特有のポイントが多々あります。主な留意事項を以下にまとめます。
-
譲渡対象の特定: 契約書上で**「譲渡する資産・負債・契約」の範囲を明確に列挙**する必要があります。譲渡対象に含めるべき資産(在庫、固定資産、知的財産、許認可、営業権、顧客リスト等)と、引き継がない資産(余剰資産や不要設備など)を洗い出し、一覧表(スケジュール)添付する形で合意します。負債についても、買い手が特定の負債を承継する場合は明記し、基本的には明示されない負債は買い手に承継されないのが原則です。曖昧なままだと後日トラブルになるため、範囲の特定は極めて重要です。
-
取引先との契約承継方法: 前述の通り包括承継ができないため、重要な取引先との個別契約については事前に承継の同意を得る必要があります。契約上譲渡に要承諾条項がある場合は書面で相手方の承諾を取得し、重要顧客との取引基本契約などは新会社との再契約を締結します。これらを**クロージング前の前提条件(Condition Precedent)**とすることも多く、「主要取引先〇社の契約が有効に承継されること」を取引実行の条件と定めるケースもあります。
-
従業員の処遇: 従業員は法律上自動的には移りませんので、譲渡企業で一旦退職し譲受企業に再雇用(新規入社)という手続きを取るのが一般的です。円滑な人員引継ぎのため、売り手側から従業員へ事情を説明し同意を得るプロセスが重要です。給与や勤続年数の取扱いについては、譲受企業が退職金通算や待遇維持を約束するケースもあり、これを労働条件通知書や承継合意書などの形で明文化します。従業員が承諾しない場合に備え、代替要員計画や特定従業員を譲渡対象から除外するオプションなどを検討しておくこともあります。
-
許認可・資格の承継: 許認可は原則取り直しとなるため、譲受企業側で事前に必要な許認可を取得できるよう当局と調整します(例えば食品製造業許可、建設業許可など)。許認可取得待ちの場合、経過措置として一時的に旧会社から業務委託を受ける形で運営するなどの対応も検討されます。医薬品製造販売業など譲渡に行政処分が伴う業種では、厚労省令に基づく承継手続が必要になるなど専門対応が求められます。
-
対価調整と決済: 譲渡対価は基本合意時には概算で決め、本契約で確定額を定めますが、**クロージング日までの運転資本や資産変動に応じて価格調整条項(Closing Adjustment)**を設けることがあります。棚卸資産の増減や売掛金・買掛金の回収状況により数百万~数千万円規模で調整する場合が典型です。決済はクロージング日に銀行振込で一括支払いが一般的ですが、分割払いやアーンアウト(将来業績連動払い)が合意される場合もあります。
-
表明保証と補償: 売り手は譲渡事業に関し、財務情報の正確性、潜在債務の不存在、法令遵守状況などについて表明保証(Representation & Warranties)を行います。万一これに反する事態(表明保証違反)が発覚した場合の補償クレームや、特定債務についての補償条項(Indemnity)も定めます。事業譲渡では売り手企業が存続するため、違反発生時にはその会社に補償請求することになります。例えば、「簿外債務が発覚した場合には売り手が全額賠償する」といった条項です。また、売り手にとっては競業避止義務の範囲を契約で調整することもポイントです(法定では20年の区域制限がありますが、実務上は買い手と協議して期間や地域を変更できます)。譲渡契約で「売り手および関係者は今後〇年間、本件と同種の事業を営まない」と明記しておくのが一般的です。
-
クロージング前後の対応: 契約締結(サイン)から譲渡実行日(クロージング)までに履行すべき事項を洗い出し、従業員への説明会開催、取引先への譲渡通知、在庫棚卸と引渡し、資産の目録作成と確認など、詳細なアクションプランを双方で策定します。ITシステムのデータ移行やメールアドレス変更案内、請求書宛名変更通知など、実務タスクも膨大です。これらを円滑に行うため、両社からなるプロジェクトチームを編成しチェックリストで管理することが望ましいです。
以上のように、事業譲渡の契約交渉は譲渡範囲の特定・同意取り付けと各種手続きの事前準備が肝になります。特に重要なのは**「抜け漏れ防止」**です。例えば、譲渡対象に含め忘れた資産が後から見つかると追加譲渡の交渉が必要になったり、承継漏れの契約が事業継続の妨げになったりします。過去の失敗事例では、債務調査が甘く想定していなかった負債を引き継いでしまったケースも報告されています。このような事態を避けるため、デューデリジェンス(DD)の段階から売り手事業の実態を徹底的に洗い出し、契約書に反映することが重要です。また、交渉においては基本合意後の大きな条件変更は避け、双方が信頼関係を損なわないよう透明性をもって議論する姿勢が求められます。事業譲渡は扱う論点が多岐にわたるため、法務・財務・税務それぞれの専門家チームでサポートし、綿密な計画と協議によって契約締結・クロージングへと進めていくことが成功のポイントです。
M&A後の統合プロセス(PMI)の進め方
事業譲渡契約が成立しクロージングを迎えた後は、Post Merger Integration(PMI)と呼ばれる買収後の事業統合プロセスが極めて重要です。M&Aのゴールは契約締結ではなく、その後に期待されたシナジーや効果を実現することにあります。PMIが失敗すると、当初見込んだ効果が得られないばかりか、場合によっては従業員の大量離職など深刻な問題に発展する可能性もあります。逆に、PMIが円滑に進み成功すれば、当初想定以上の成果を上げられることもあるため、「M&Aの成功はPMIにかかっている」とまで言われます。
事業譲渡の場合、組織全体の統合作業というよりは譲り受けた事業を買収企業の中でどう軟着陸させ軌道に乗せるかがPMIの焦点となります。以下にPMI実行上の要点を示します。
-
専任の統合責任者とチームの設置: PMIは組織の複数部門(人事・総務・営業・ITなど)にまたがる調整が必要となるため、譲受企業側で全社横断的な調整ができる責任者(統合マネージャー)を置くことが重要です。特に事業譲渡では譲渡企業から受け入れる従業員や事業資産に関して、労務・システム・営業など各方面で細かな対応が発生するため、統合責任者の指揮の下、関係部門を巻き込んだチーム体制を組みます。場合によってはPMI専任の担当部署や外部コンサルタントを起用して、通常業務と並行して進める統合作業を推進します。
-
人材・組織の統合: 譲渡事業から移籍してきた従業員が新しい組織になじむよう、受け入れ研修やオリエンテーションを実施します。企業文化の違いがある場合は、両社の風土のギャップを埋める交流の場を設けたり、相互に尊重し合う風土づくりに努めます。処遇の調整(給与体系や福利厚生の統一など)も早期に行い、不公平感が出ないよう配慮します。また、新旧従業員の混合チームを編成してプロジェクトを任せるなど、組織的な一体感醸成を図ります。
-
顧客・取引先対応: 譲渡によって看板(社名)が変わったり担当が替わったりすることを、顧客や取引先に的確に伝え、信頼関係を維持することが最優先です。挨拶回りや説明文書の送付を通じて、「事業は新体制で継続しサービス水準も維持向上する」ことを丁寧に説明します。取引先からすると不安要素もあるため、問い合わせ窓口を設け迅速に対応したり、重要顧客には経営陣自ら訪問するなどして顧客離れを防ぐ努力が必要です。
-
事業プロセス・制度の統合: 買収企業のルールやプロセスに合わせて、譲受事業の業務フローや社内制度を順次統合していきます。ただし、何もかも急激に自社色に染めようとすると混乱を招くため、重要度に応じて段階的に進めます。例えば、コンプライアンスや安全管理など譲受側グループで統一すべき事項は早期に共有・教育し、一方で営業方法やクリエイティブ面など事業譲渡元の強みが発揮できる部分はしばらく自主性を尊重するといった柔軟性が求められます。ITシステムや会計制度の統合作業も計画的に行います。必要に応じて旧システムから新システムへのデータ移行や、顧客情報の統合、在庫管理方法の変更など、専門チームが対応します。
-
早期のシナジー創出: PMIにおいては、できるだけ早期に**「成功体験」**を関係者が実感できることが望ましいです。当初期待したシナジー(例えば販売チャネル拡大やコスト削減効果)が具体的成果として現れるよう、短期KPIを設定して進捗を管理します。小さくても成果が出れば従業員の士気向上につながり、PMI推進に弾みがつきます。逆に統合初期にトラブル(顧客クレーム増大や生産遅延など)が起きると士気が下がり離職につながりかねないため、リスクモニタリングを強化し問題発生時は経営層が迅速に手当てします。
-
コミュニケーションとフォローアップ: PMI期間中は関係者への丁寧なコミュニケーションが不可欠です。統合計画や進捗、今後の方針について、経営トップから定期的に発信し、不安や疑問に答えます。従業員アンケートやヒアリングを行い、現場の声を把握して施策に反映させることも有効です。また、統合の進捗評価を適宜行い、計画から遅れている項目や追加で必要になった課題に対処します。統合作業は1年程度で完了する場合もあれば、大規模案件では数年単位になることもあります。重要なのは、統合プロセスを途中で投げ出さず最後まで継続する意思と体制です。
以上のようなPMI施策を講じることで、M&A後の混乱を最小限に抑え、期待以上の成果を引き出すことが可能となります。特に事業譲渡では、新たな経営の下で事業を再活性化させるチャンスである一方、うまくハンドリングしないと**「宝の持ち腐れ」**になりかねません。譲受側企業の経営陣は、譲り受けた事業の価値を最大化すべく戦略的な統合計画を立案し、人・物・金・情報すべての面で必要な投資とケアを行うことが肝要です。PMIを成功させれば、M&A前に描いていたシナジーが実現するだけでなく、想定以上の新規事業展開や収益改善も期待でき、まさにM&A成功の真価が発揮されるでしょう。
4. 最新の動向と今後の展望
最後に、近年の国内M&A市場における事業譲渡の動向と、コロナ禍やDXが与えた影響、そして事業譲渡を検討する企業に向けた今後の展望・アドバイスについて述べます。
事業譲渡を取り巻く最近のトレンド
日本のM&A件数は、ここ数年右肩上がりで増加傾向にあります。2020年は新型コロナウイルス感染拡大の影響で一時的に減少しましたが、その後2021年以降は急回復し、年間M&A件数は過去最高水準を更新しています。この中で、事業譲渡(事業売却)件数も増加傾向にあります。
特に注目されるトレンドの一つは、事業承継ニーズの高まりです。帝国データバンクの調査によれば、2022年時点で後継者未定の企業割合(後継者不在率)は57.2%と、2014年以降初めて60%を下回り改善しています。この改善の背景には、「未曽有のコロナ禍で自社の将来を見つめ直す中小企業が増え、全国に第三者へのM&Aや事業譲渡を含む事業承継の相談窓口が整備されたこと」が大きく寄与していると分析されています。つまり、地域金融機関やM&A仲介会社の普及により事業譲渡を選択肢とした事業承継が以前にも増して一般化してきたのです。実際、中小企業のM&Aでは前述のように株式譲渡が主流とはいえ、近年は事業譲渡による事業承継成功例も数多く報告されています。経営者の高齢化と事業承継問題は社会課題となっていますが、事業譲渡は有力な解決策の一つとして認識されつつあります。
もう一つのトレンドは、大企業の事業ポートフォリオ再編の活発化です。国内大手企業は収益力強化や資本効率向上のため、グループ内事業の「選択と集中」を加速しており、その結果として非中核事業の売却が相次いでいます。近年の例では、日立製作所や東芝、富士通、パナソニックなどが次々と事業売却(子会社株式の譲渡や事業譲渡)を実施してきました。事業譲渡という形態に限っても、素材・化学大手の住友化学が2025年にベルギー企業から樹脂事業を買収したり、エレクトロニクス大手のレゾナック(旧・昭和電工グループ)から大陽日酸が排ガス処理装置事業を譲受する契約を結んだなど、大型の事業単位売買も散見されます。また、小売・サービス業界でも、コンビニ大手が自社の非主力事業を譲渡したり、鉄道会社がホテル事業を売却したりといった動きが見られます。ファンドによるカーブアウト買収(事業切り出し買収)も活発で、日本産業パートナーズや海外PEファンドが大企業から事業を取得するケースも増えています。これらは一種の事業譲渡ブームとも言える状況で、企業価値向上のために事業の新陳代謝が進んでいるといえます。総じて、事業譲渡は「守りの承継」から「攻めの戦略」まで幅広い目的で活用され、市場に定着した感があります。
コロナ禍・DXがM&Aに与えた影響
コロナ禍の影響: 新型コロナウイルスによる経済環境の変化は、M&A・事業譲渡の世界にも複合的な影響を与えました。一方では2020年前後に業績悪化した企業が事業売却を検討するケースが増え、「コロナ破綻」を避けるために第三者に事業を託す動きがありました。他方で、2021年以降は景気持ち直しとともに旺盛なM&A需要が戻り、買い手側から見るとコロナ禍で割安になった良質な事業を買収する好機ともなりました。また、コロナ禍で人々の生活様式や需要構造が変化したことから、企業は事業ポートフォリオを見直す必要に迫られ、新規事業への参入や不採算事業からの撤退をM&Aで加速させました。帝国データバンクの分析にもあるように、コロナ禍で将来性を再検討した中小企業が多く、事業承継M&Aの件数が増える一因となりました。さらに、コロナ禍はリモートでのM&A推進を後押ししました。対面での交渉やデューデリジェンスが難しい中、オンライン会議やクラウド上のデータ共有(バーチャルデータルーム)などデジタル活用が進み、地理的制約が小さくなったことで地方企業と都市部投資家のマッチングが活性化する効果も生まれました。総じて、コロナ禍はM&Aの必要性を逆に高めたとも言われ、事業譲渡に関しても市場を活発化させる一因となっています。
DXの影響: デジタル・トランスフォーメーション(DX)は現在、多くの企業にとって喫緊の経営課題であり、M&Aを通じてDXを推進する動きが顕著です。具体的には、IT・デジタル分野の企業や事業を買収して自社のデジタル技術や人材を一気に強化しようとするものです。近年、日本企業が絡んだM&AではDXや脱炭素を目的とした案件が増加傾向にあり、2019年以降その傾向が顕著と報じられています。例えば製造業がAIスタートアップを買収したり、小売業がEC事業者を取り込んだりといった例が増えています。これは裏を返せば、デジタル分野の事業譲渡案件が増えていることも意味します。大企業が持つIT子会社の一部事業を専門企業に売却したり、逆にDX推進のため異業種のITサービスを買収したりと、業界を横断した事業の流動化が進んでいます。実際、コロナ禍を経てリモートワークや業務効率化へのニーズが高まり、それを満たすITソリューション企業の価値が上がりました。M&AマーケットでもDX関連はホットな分野で、2021年にはDX・ITを狙った買収が今後数年ピークを迎えるとの調査もあります。総じてDXは、M&Aの動機として新たな柱となっており、事業譲渡もその文脈で積極的に行われています。これからの事業譲渡では、AI・IoT・SaaSなどデジタル技術を持つ事業の売買や、従来型企業がデジタル事業をスピンオフして資本提携を結ぶケースなどがますます増えるでしょう。
事業譲渡を検討する企業へのアドバイス
最後に、これから事業譲渡によるM&Aを検討する企業(売り手・買い手双方)に向け、専門家の視点から主要なアドバイスをまとめます。
-
戦略目的を明確に: 事業譲渡を行う目的(事業承継なのか、不採算事業整理なのか、新規事業獲得なのか etc.)を明確化し、その目的に本当に合致したスキームかを検討しましょう。例えばオーナー引退が目的なら株式譲渡の方が良い場合もありますし、負債切離しが重要なら事業譲渡が有効です。目的・戦略に応じたスキーム選定が第一歩です。
-
専門家チームの活用: 事業譲渡は法務・税務・財務の論点が複雑に絡みます。信頼できるM&Aアドバイザー、弁護士、公認会計士・税理士などでチームを組み、初期段階から助言を受けてください。企業内部だけで判断せず、客観的なシミュレーションやバリュエーションを実施しましょう。特に中小企業ではM&A経験が少ないため、仲介会社や金融機関のM&A支援サービスを積極的に利用するのも有効です。
-
価値算定と価格交渉: 自社(または対象事業)の価値を冷静に見極めましょう。強みだけでなく弱みやリスクも洗い出し、適正な譲渡価格のレンジを想定しておきます。売り手の場合、希望価格が高すぎると相手にされず、逆に安すぎると株主の不利益になります。複数の評価手法でエビデンスを準備し、説得力をもって価格交渉に臨むべきです。また買い手の場合も、相手の提示額の根拠を精査し、必要なら追加のDue Diligenceを要求するくらいの慎重さが求められます。
-
デューデリジェンスの徹底: 買い手はもちろん、売り手も事前に自社事業のデューデリジェンス(セルフDD)を行うくらいの意識が必要です。簿外債務・法務リスク・契約状況・環境問題・労務問題など、考え得るあらゆるリスクを洗い出し対策を検討しておきます。これは交渉を円滑に進める材料にもなり、買い手からの信用向上にもつながります。逆にDDを怠ると、前述のような想定外の債務引継ぎや交渉決裂など失敗の原因になりかねません。
-
ステークホルダーへの配慮: M&Aは当事者だけでなく従業員、顧客、取引先、金融機関など多くの関係者に影響します。情報管理に留意しつつも、適切なタイミングで関係者への説明・相談を行うことが肝心です。特に従業員にとっては将来の働き方が左右される問題ですから、誠意をもって対応してください。早めにキーマンには打ち明けて協力を仰ぎ、噂が先行しないよう公式な発表の段取りも検討しましょう。
-
契約条件の詰めとスケジュール管理: 事業譲渡はクロージングまでにすべき準備が多いため、現実的なスケジュールを設定しタスクを洗い出します。許認可取得に要する期間や株主総会招集期間など法定要件も考慮して、無理のない計画を立てましょう。契約交渉では専門用語や条項が多岐にわたりますが、一つ一つ理解・確認することが大切です。曖昧な点を残さず、将来の紛争を防ぐ観点で契約書を作り込みます。場合によっては重要論点について合意議事録やサイドレターを交わしておくと安心です。
-
PMIの準備: 買い手企業は、クロージング後の具体的な統合作業計画(PMI計画)を事前に策定しておきましょう。誰をリーダーにして、どの順序で統合を進め、成功の目標をどこに置くかといった青写真がないと、せっかくの買収が無駄になりかねません。可能であればクロージング前から両社の担当者同士で協議を始め、移行期間中の暫定ルールや協力事項を取り決めておくとスムーズです。売り手企業も、譲渡後一定期間は**移行支援サービス(トランジションサービス)**を提供する姿勢を持つと、買い手からの評価が上がり交渉でも有利になるでしょう。
-
柔軟性と誠実さ: 交渉においては、自社の主張ばかりを通そうとせず相手の事情にも耳を傾け、ウィンウィンの落とし所を探る姿勢が重要です。特に中小企業M&Aでは経営者同士の人間的信頼が決め手となることも多いです。最終的に譲渡するとはいえ、自分が育てた事業を託す相手としてふさわしいかという観点で、お互い誠実に向き合うことが成功につながります。
以上の助言を踏まえ、事業譲渡を検討する企業は十分な準備と専門知識の活用を行った上でプロセスを進めてください。昨今はネットワークや情報も充実し、信頼できる支援者にアクセスしやすい環境です。実行前に様々なシミュレーションを行い、税務面・財務面・法務面のシナリオを比較検討することも重要です。事業譲渡は一度決行すれば元に戻すのが難しい重大な経営判断です。しかし、適切に遂行すれば企業に新たな成長や存続の道を開く有力な手段でもあります。今後も事業譲渡は、日本企業の新陳代謝を促し経済を活性化させる手法として存在感を増していくでしょう。その潮流の中で、自社の発展とステークホルダーの幸福を最大化できるよう、正しい知識と戦略の下で事業譲渡に取り組んでいただきたいと思います。

株式会社M&A Do 代表取締役
M&Aシニアエキスパート・相続診断士
東京都昭島市出身。慶應義塾大学理工学部を卒業後、大手M&A仲介会社にて勤務し、その後独立。これまで製造業・工事業を中心に友好的なM&Aを支援。また父親が精密板金加工業、祖父が蕎麦屋、叔父が歯科クリニックを経営し、現在は父親の精密板金加工業にも社外取締役として従事。