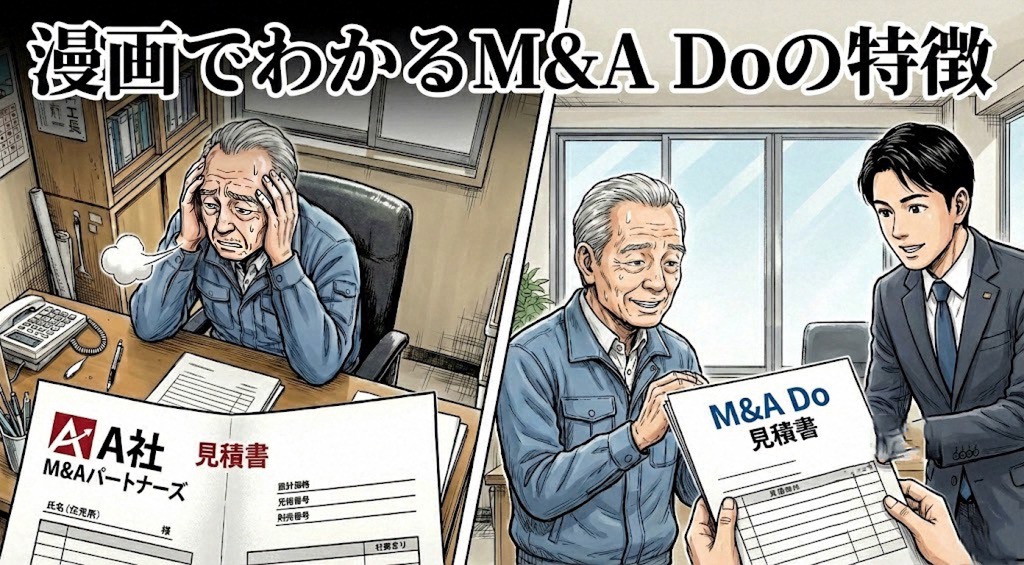【はじめに】
茨城県は首都圏に近く、豊かな自然環境と工業集積が融合した地域として、多彩な産業が根付いています。特に県北部には重工業や電機関連などの大手企業グループが、県南部にはIT、サービス、流通、医療機関などが数多く立地し、さらに農産物の生産量も全国上位に位置しています。このように多様な産業が盛んな土地柄ゆえ、県内外・国内外からの企業買収や事業譲渡が活発に行われてきました。近年では経営環境の変化や技術革新に合わせ、事業領域を拡大・集約させるためのM&A(合併・買収)がますます注目を集めており、茨城県内でもさまざまな事例が報じられています。
本記事では、茨城県を舞台に展開された数多くのM&A事例を紹介しつつ、その背景や意義、シナジー、地域経済への影響などを整理していきます。なお、記事の構成上、個別事例を大まかなカテゴリに分類しながら記述しますが、重複した分野や複合的な狙いをもった事例も多いため、各事例がどのような特徴をもっているかをご参照いただきながら読み進めてください。
【第1章:自動車・機械関連産業におけるM&A】
1-1. 日立製作所とホンダが主導した自動車部品メーカーの統合
2019年10月、日立製作所とホンダがそれぞれの傘下にある自動車部品メーカー4社を合併させる計画を発表しました。具体的には、ホンダ系列のケーヒン、ショーワ、日信工業の3社をTOB(株式公開買い付け)によってホンダが完全子会社化したうえで、日立製作所全額出資の日立オートモティブシステムズ(茨城県ひたちなか市)がこれら3社を吸収合併し、巨大な自動車部品メーカーグループを形成するというものです。合併後の新会社への出資比率は日立が66.6%、ホンダが33.4%となり、売上規模は約1兆8000億円に達する見込みとされました。これは国内の自動車部品メーカーとしてはトヨタ系のデンソー、アイシン精機に次ぐ第3位という大規模な体制です。
今回の統合は、自動車産業がCASE(コネクテッド、自動運転、シェアリング、電動化)に象徴される次世代技術へ大きくシフトしていく流れの中で、それぞれの強みを結集し国際競争力を高める狙いがありました。茨城県ひたちなか市に拠点を持つ日立オートモティブシステムズは、日立グループの中核企業として先端技術を担ってきましたが、統合によって製品ラインナップがさらに広がり、新たな研究開発投資も加速する見通しです。このように県北部のものづくり企業の再編が進むことで、地域全体の産業活性化にも寄与すると期待されています。
1-2. 双葉電子工業<6986>のTDKマイクロディバイス子会社化
2011年9月、双葉電子工業はTDK傘下のTDKマイクロディバイス(北茨城市)を子会社化することを公表しました。TDKマイクロディバイスは主に民生用小型有機ELディスプレーの開発・製造を手がける企業でしたが、有機EL分野は今後のディスプレイ市場での成長が見込まれ、双葉電子工業が持つ蛍光表示管(VFD)やIC開発の技術と融合させることで、自社の製品強化を図る狙いがありました。
有機EL技術はスマートフォンや次世代ディスプレイなどでの需要拡大が見込まれており、こうした先端部材分野でのM&Aは地域にとっても重要な意味を持ちます。北茨城市にはかつて炭鉱や金属工場が集積し、現在は電子部品関連の工場も一定規模残っています。双葉電子工業による買収により、地域における雇用維持や産業クラスターの形成も期待されました。
1-3. ムロコーポレーションのいがり産業買収
2019年、ムロコーポレーションは茨城県笠間市に拠点を置く精密樹脂成形部品メーカー・いがり産業(イガリホールディングス傘下)を子会社化しました。ムロコーポレーションは自動車用機能部品の金属プレス領域が強みですが、樹脂部品についても自動車や弱電分野での活用が拡大しており、精密樹脂成形のいがり産業を取り込むことで製品ラインナップを強化しました。
自動車産業では、軽量化を背景にプラスチックや複合材を使った部品需要が増大しています。今回のM&Aは、金属加工で培ったノウハウに樹脂成形の新技術を加えて、顧客企業への一括提案力を高める狙いがあるとみられています。
【第2章:建設・インフラ関連のM&A】
2-1. 鈴縫工業<1846>のMBOによる非公開化
2017年12月、茨城県日立市を本拠地とする老舗建設会社・鈴縫工業は、MBO(経営陣による買収)によって上場を廃止し、非公開化する方針を発表しました。県内の公共工事の受注が減少傾向にあるうえ、資材価格の高騰や労務費の上昇など採算面での課題が顕在化していました。こうした中、経営判断をスピード重視で行える非上場化のメリットを選択し、県内外の民間工事へシフトを図る戦略です。
非上場化によって企業の存在感が消えるわけではなく、むしろ地元企業として強みを生かしつつ、より柔軟な事業展開が可能になります。大手ゼネコンとの協業や自治体との連携も今後の焦点とされるなど、県内建設業界の動向を占う注目の事例となりました。
2-2. 戸田建設<1860>の茨城県地場建設会社・昭和建設の子会社化
2021年9月、戸田建設が水戸市に本拠を置く昭和建設を子会社化することを決定しました。昭和建設は1955年創業の地場大手で、茨城県内で公共・民間を問わず幅広い実績をもっています。戸田建設は全国的な総合建設会社としてのブランド力・技術力と、昭和建設の地元密着型営業・施工能力を掛け合わせることで、県内ビジネスの拡大を狙います。
茨城県は圏央道・常磐道などの交通インフラ整備によって、首都圏との接続が強化されており、新たな産業団地や宅地開発などが進むエリアでもあります。大手建設会社が地場企業を買収して拠点を強化する動きは、今後も続く可能性があります。
2-3. 日本乾溜工業<1771>の不溶性硫黄事業売却
2022年9月、日本乾溜工業は不溶性硫黄事業を切り離し、茨城県神栖市に本社を置く鶴見化学工業に譲渡すると公表しました。日本乾溜工業は道路や防災工事などの建設事業が主力ですが、今後は建設分野に経営資源を集中するため、不溶性硫黄事業を鶴見化学工業へ譲り渡す決定を下しました。茨城県の鹿島臨海工業地帯周辺には化学系企業が多く立地しており、専門性の高い化学工業分野における再編の一環ともいえます。
2-4. 八洲電機<3153>の空調事業売却
2011年3月、八洲電機は子会社ヤシマ・エコ・システム(東京都足立区)が茨城支店で行う空調事業を日立空調関東に売却すると発表しました。ヤシマ・エコ・システムの事業再編の一環であり、日立アプライアンス(当時、現・日立Global Life Solutions)の完全子会社である日立空調関東が譲り受ける形となりました。茨城県は日立製作所グループの関連企業や、空調分野でも大手関連工場が集まるなど独自の集積を持つエリアです。このような企業間の事業譲渡により、特定分野での統合や集中が見受けられます。
【第3章:運輸・インフラ関連サービスのM&A】
3-1. 京成電鉄<9009>、関東鉄道をTOBで子会社化
2019年7月、京成電鉄は茨城県内最大の鉄道・バス事業者である関東鉄道(土浦市)をTOBによって子会社化すると発表しました。関東鉄道は京成電鉄の持ち分法適用関連会社でしたが、買付により出資比率を約99%に高めることで、支配力を強化します。県南部や鹿行地域、さらに千葉県の一部にわたる広範なエリアを抱える関東鉄道と京成電鉄との連携が強化されることで、運行効率や設備投資の最適化が期待されました。
茨城県は公共交通機関の利用率が必ずしも高くない地域ですが、今後の少子高齢化対策や観光振興の観点から、鉄道やバスによる移動インフラの充実が求められています。京成電鉄グループ入りによる大規模投資やサービス改善を通じ、地域社会にどのような変化をもたらすか注目されています。
3-2. 第一交通産業<9035>、小島タクシーの子会社化
2013年2月、第一交通産業は茨城県土浦市に本拠を置く小島タクシーを完全子会社化し、「土浦第一交通」に社名変更しました。小島タクシーは30台の車両を運行していましたが、これで茨城県における第一交通産業グループの保有車両は合計110台に増加しました。第一交通産業は全国でタクシー保有台数を拡大する戦略を進めており、地域交通においても再編が進んでいることを示しています。
【第4章:食品・外食・流通業界のM&A】
4-1. クスリのアオキホールディングス<3549>、スーパーマルモの食品スーパー事業を取得
2021年4月、クスリのアオキHDは茨城県土浦市で食品スーパーを展開するスーパーマルモから7店舗を取得することを発表しました。ドラッグストアのヘルス&ビューティー商材と、地場食品スーパーの新鮮食材を掛け合わせることで、地域密着型の店舗展開を強化する狙いがあります。ドラッグストアの出店が著しい茨城県南地域において、消費者のワンストップショッピング需要を満たす布陣を敷くという戦略が見て取れます。
4-2. ホリイフードサービス<3077>、食品・酒類卸のホリイ物流を子会社化
2024年4月、茨城県を地盤とする居酒屋やイタリアンレストラン等を展開するホリイフードサービスが、主要仕入先の一つであるホリイ物流を子会社化すると決定しました。飲食チェーンを運営する企業が仕入れルートを垂直統合することで、コスト最適化や商品の安定調達を狙う動きが広まっています。茨城県は農産物や畜産物など一次産業も盛んであり、その流通や加工を担う中間事業者との関係を強化するケースは今後も増えていく可能性があります。
4-3. グルメ杵屋<9850>、ラーメン・中華料理店経営の雪村を子会社化
2020年4月、うどん・そばチェーンなどを手がけるグルメ杵屋は、主に茨城県南部でラーメン店「ゆきむら亭」などを展開する雪村の株式を取得し、同社とそのセントラルキッチン運営会社を完全子会社化しました。近年の外食企業は業態の多角化を図る中で、地場で根付く人気チェーンを取り込む動きが盛んです。茨城県南部では首都圏への交通アクセスが良好であるため、今後さらなる外食産業の再編が進むと考えられます。
【第5章:不動産・サービス業のM&A】
5-1. アコーディア・ゴルフ<2131>と平和<6412>によるゴルフ場再編
茨城県は首都圏近郊に立地するという地の利と豊富な土地を生かし、ゴルフ場が多数存在します。しかしゴルフ人口の減少やバブル期以降のゴルフ場経営の難化を背景に、ゴルフ場の売買や再編が頻繁に行われてきました。
- 平和(PGM)によるオールドオーチャードゴルフクラブ買収
2021年7月、平和の子会社パシフィックゴルフマネージメント(PGM)は大林組の子会社が所有するオールドオーチャードゴルフクラブ(茨城町)の事業を取得しました。買収によってゴルフ場ネットワークをさらに拡大し、収益の安定化を進めています。 - PGMによる内原カントリー倶楽部の買収
2015年にも同じくPGMが水戸市の内原カントリー俱楽部の事業を譲り受けて子会社化しています。 - アコーディア・ゴルフの各種ゴルフ場取得・譲渡
一方、アコーディア・ゴルフも茨城県内で積極的にゴルフ場の買収を行ってきました。しかし近年は収益構造の観点から特定コースを譲渡する例もあり、たとえば水府ゴルフクラブ(常陸太田市)などを売却する事例がありました。
これらの動きから、全国規模でゴルフ場を展開する大手企業による県内ゴルフ場の集約が進んでいるといえます。
5-2. かんぽの宿事業の譲渡
日本郵政グループは赤字幅の拡大が続く「かんぽの宿」事業について、2021年10月に32施設を一括して複数の事業者に譲渡すると公表しました。その中には茨城県ひたちなか市に所在する宿泊施設を地元不動産事業者ノザワワールドへ譲渡する事例も含まれており、観光資源の活用と雇用維持を目指しています。大手グループの資本再編において、地方の宿泊・観光施設が切り離され、地域企業が取得するケースは全国的にも見られます。
5-3. APAMAN<8889>による茨城県仲介・賃貸管理会社の買収
不動産仲介・管理のアパマンショップを展開するAPAMANは、茨城県守谷市で不動産仲介・賃貸管理を行うマイハウスを子会社化しました(2020年4月)。県南部を中心に店舗網を拡大する狙いがあり、首都圏のベッドタウンとして発展を続ける守谷やつくばエリアの人口増に対応する動きとも考えられます。
【第6章:医療・介護関連のM&A】
6-1. クオールホールディングス<3034>の調剤薬局展開
茨城県は県人口の減少が指摘されている一方で、医療サービスや介護サービスの需要は高まっています。こうした中、クオールHDは県内外の調剤薬局を積極的に取得しています。
- アルファームの買収
2013年には茨城県や栃木県、群馬県で調剤薬局を展開するアルファーム(水戸市)を完全子会社化。 - セントフォローカンパニー買収
2014年には茨城県中心に35店舗を構えるセントフォローカンパニーを子会社化し、関東地方での店舗数トップクラスを狙いました。 - メリーコーポレーション買収
2019年には日立市で調剤薬局2店舗を運営するメリーコーポレーションを買収し拠点を拡充。
クオールHDのような大手調剤チェーンが地場の薬局事業者を取り込むケースは全国的にも増えていますが、茨城県も例外ではありません。
6-2. セントケア・ホールディングの城南ビル買収
2024年4月、在宅介護サービスを広く展開するセントケア・ホールディングは日立市で介護事業を行う城南ビルを子会社化すると発表しました。訪問介護や高齢者住宅の運営など、介護関連領域は公共性が高く、また人手不足・高齢化など喫緊の課題が山積です。大手介護サービス企業による地場企業の買収は、サービス水準の安定や事業継続の観点でも期待されています。
【第7章:IT・ソフトウェア・研究開発関連のM&A】
7-1. ウインテスト<6721>、りょうしんメンテナンスサービス買収
2017年4月、ディスプレイ検査装置などを手がけるウインテストが、太陽光発電所の遠隔監視や点検を行うりょうしんメンテナンスサービスを買収。これに際し、茨城大学とも太陽光パネルの新モニタリング技術を共同で進めており、茨城県内での実証も期待されています。大学や研究機関との連携による新エネルギー・スマートシティ分野の取り組みを支援するM&Aとして注目されました。
7-2. チェンジ<3962>、ロゴスウェアの子会社化
2022年7月、チェンジはeラーニングや研修ライブ配信を行うロゴスウェア(茨城県つくば市)を株式取得し子会社化すると公表しました。つくば市は筑波大学や各種研究所が集まる日本有数の学術研究都市であり、先端技術やベンチャー企業が多数存在します。ITや教育テック(EdTech)の領域における大手企業からの買収案件が増えつつあり、地域のスタートアップエコシステムにも波及効果をもたらしています。
7-3. 情報企画<3712>、ソフトウエア開発のダンクを子会社化
2022年9月、金融機関向けシステムなどを手がける情報企画は、茨城県日立市でソフトウエア開発を行うダンクを子会社化しました。日立市周辺は日立グループの企業城下町として高度なエンジニアが多く集まり、ソフトウエア受託開発や人材派遣などが活発です。東京や首都圏に本社を持つIT企業が地場の開発拠点を取得することで、技術者確保とビジネス拡大を狙う動きが加速しています。
【第8章:エネルギー・環境関連のM&A】
8-1. 三谷商事<8066>の風力発電事業参入
2010年12月、総合商社の三谷商事は風力発電会社ウィンド・パワー(水戸市)の第三者割当増資を引き受けて子会社化しました。茨城県神栖市で外洋風力発電設備の設置を計画しており、再生可能エネルギー分野への期待が高まる中での投資です。神栖市周辺は沿岸部で風力発電に適した地形と風況を持ち、今後も洋上風力を含めたプロジェクトが注目されています。
8-2. プロスペクト<3528>による太陽光発電所売却
2020年3月、プロスペクトは茨城県牛久市など国内複数の太陽光発電所を一括売却すると発表しました。同社は稼働後の発電所を長期保有せず、利益が最大になるタイミングで売却する「開発→売却」型を基本戦略としています。FIT(固定価格買取制度)施策の変遷とともに、太陽光発電所の売買もM&Aの一種として取引が行われることが通例化してきました。
【第9章:金融・保険関連のM&A】
9-1. 筑波銀行<8338>の前身、関東つくば銀行と茨城銀行の合併
2009年4月、茨城県内の地銀2行(関東つくば銀行、水戸市の茨城銀行)が2010年3月1日付で合併し、筑波銀行が誕生することが公表されました。地元金融機関の大型再編として当時大きな話題となり、県域内での金融サービス強化が目指されました。
9-2. 全国保証<7164>、筑波信用保証を子会社化
2021年2月、全国保証は筑波銀行の子会社である筑波信用保証(茨城県つくば市)の全株式を取得すると発表しました。住宅ローンなどの信用保証事業において、全国保証が持つノウハウと筑波銀行の地元マーケットを融合させ、保証債務残高拡大や経営管理の効率化を狙います。金融関連でも県内の地方銀行グループ再編の動きが続いています。
【第10章:その他多彩なM&A事例】
10-1. メルカリ<4385>の鹿島アントラーズ買収
2019年7月、フリマアプリで有名なメルカリはJリーグ強豪クラブの鹿島アントラーズ(鹿嶋市)の株式61.6%を取得し、子会社化すると発表しました。日本製鉄が前身住友金属サッカー団を母体として支えてきたアントラーズは日本有数の人気クラブですが、メルカリとの資本提携により新たなビジネスモデルやデジタルコンテンツ開発が期待されます。
地域に根付くプロスポーツクラブをIT企業が買収する事例は日本では珍しく、県東地域の地域経済や観光振興との連携にも注目が集まりました。
10-2. 香陵住販<3495>のKASUMIC子会社化
2019年1月、茨城県南・千葉県北で売買仲介や賃貸管理を手がけるKASUMIC(つくば市)を香陵住販が取得し子会社化すると公表しました。県南エリアはつくばエクスプレス開業後に都市開発が加速しており、賃貸管理戸数の増強は香陵住販にとっても大きなメリットがあります。地元不動産企業同士のM&Aにより賃貸管理や仲介業務の統合・効率化が進む動きは全国各地で見られるところです。
10-3. バグースによる「サムタイム」「ビリヤード場」の買収
ダイニング・アミューズメント事業など幅広く手がけるバグース(本社:茨城県日立市)は、他企業のビリヤード場やアミューズメント施設を買収し事業拡大を図る動きが幾度か報じられました。首都圏に多店舗展開しているバグースは、公共交通機関や商業施設との相乗効果を狙い、インドアレジャー需要を取り込んでいます。アミューズメントやエンターテインメント業界でも、茨城県に拠点を置きながら都心へのアクセスを活かすケースが増えています。
10-4. ヤマノホールディングス<7571>、「スクールIE」加盟店を相次ぎ買収
ヤマノホールディングスは、創始者の山野愛子氏が「教育」と「美容」を経営理念の軸としたことから、教育事業領域の拡大に注力しています。茨城県や千葉県を中心に「スクールIE」フランチャイズを展開するマンツーマンアカデミーを2019年に子会社化したのち、2022年には東京エリアで16教室を運営する東京ガイダンスも買収。首都圏の学習塾市場は個別指導塾の成長余地が大きく、今後さらに再編が進む可能性があります。
【まとめ:茨城県M&Aの特徴と展望】
茨城県内では、大企業グループの再編や外資との提携、地場企業同士の合併など、多種多様なM&Aが進行しています。その背景には、以下のような要因が挙げられます。
- 立地条件の優位性
首都圏に隣接していることで人・物の流れが多く、新技術や新事業への投資対象として魅力が高いエリアです。交通インフラ(高速道路や鉄道、港湾など)も整備が進んでおり、物流や製造業が集積しやすい環境にあります。 - 多様な産業構造
自動車・電機・化学・食品・農産物加工・外食・観光・スポーツなど、非常に幅広い分野の企業が県内に存在しています。従来の重工業や製造業だけでなく、近年ではIT、介護、医療、再生可能エネルギーなど新たな領域が成長しており、それらを横断する形でM&Aが増えています。 - 中堅・中小企業の後継者問題や経営課題
地域密着型企業で後継者不在となったり、資本力強化が必要となった場合に、県外大手企業やファンドとのM&Aを選択するケースが増えています。スピード経営を求められる時代にあって、非上場化やMBOによって経営の柔軟性を確保する動きも見られます。 - 産学連携や研究開発拠点との協力
つくば市を中心とする学術研究都市、ひたちなか市や日立市を中心とする大手電機メーカーの拠点など、研究開発の集積を背景に、IT・ソフトウェア開発や新素材・新技術への投資が促されています。ベンチャー企業や外資系企業との協業や買収も、県内エコシステムを活性化させる要因となっています。 - 観光・レジャー・スポーツ分野の潜在力
海や山など自然環境に恵まれ、鹿島アントラーズのようなプロスポーツクラブも存在する茨城県は、観光・レジャー需要をさらに伸ばす可能性を秘めています。そのため、ゴルフ場や宿泊施設の再編、スポーツエンタメ系M&Aが今後も継続すると見られます。
一方で、全国的な人口減少や地方都市の高齢化は、茨城県も同様に直面する課題です。長期的な需要予測や人材不足への対応も不可欠であり、これらをカバーするためには、資本力や経営ノウハウを外部から取り込むM&Aがより重要になってくるでしょう。また、東京圏との競争に晒されることで、差別化や独自性を打ち出す戦略が求められ、M&Aを通じてスケールメリットや技術高度化を図る動きは続くと考えられます。
茨城県のM&Aは、単なる企業買収という側面だけでなく、地域経済の活性化や雇用創出、インフラの充実など多面的な価値を生み出しています。今後も企業同士のシナジーや技術革新が期待される中、県内外プレーヤーがどのように戦略的な資本提携を行うか、大きな注目を集めるでしょう。企業の再編や統合はときにリスクも伴いますが、優れたマネジメントや地域との協調があれば、長期的な持続成長への道筋を切り開く可能性を秘めています。
こうした数多くの事例から見ても、茨城県は首都圏隣接県としてのポテンシャルをさらに高めるべく、今後も多岐にわたる業種でM&Aが活発に行われるとみられます。大手企業の製造拠点や研究拠点を活かした先端技術分野の拡大のみならず、人口構造の変化に対応する医療・介護、生活インフラ関連、そしてデジタル技術を活用したサービス産業など、新たな局面での動きが注目されます。
茨城県のM&Aは、地域に根付いた企業文化と広域展開を目指す外部企業の双方にとって、大きなビジネスチャンスでもあります。買収される企業が持つ地域とのネットワークやノウハウに、大手・新興企業の資本力やブランド力が掛け合わされることで、県全体の産業底上げにつながる可能性が十分にあるのです。これからの動向を注視し、地域企業がどのように付加価値を高め、さらなる発展を遂げるのか、大いに期待が寄せられています。

株式会社M&A Do 代表取締役
M&Aシニアエキスパート・相続診断士
東京都昭島市出身。慶應義塾大学理工学部を卒業後、大手M&A仲介会社にて勤務し、その後独立。これまで製造業・工事業を中心に友好的なM&Aを支援。また父親が精密板金加工業、祖父が蕎麦屋、叔父が歯科クリニックを経営し、現在は父親の精密板金加工業にも社外取締役として従事。