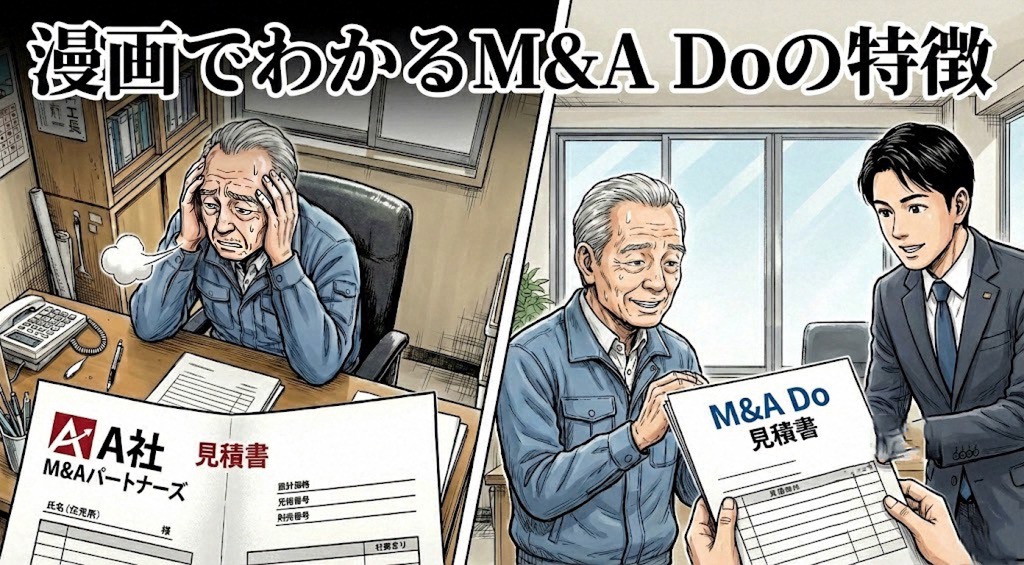1. 秋田県におけるM&Aの背景
秋田県は、全国的にも人口減少・少子高齢化が進む地域とされてきました。その影響は地元企業にも及び、市場規模の縮小や後継者不足、資本不足などが顕在化しています。一方で、秋田県は伝統ある製造業の技術力や、豊富な自然資源によるエネルギー産業(風力・バイオマス等)、さらには農産物や食品加工といった分野に強みを持つ地域でもあります。
こうした背景から、地元企業が大都市圏や海外企業との資本提携・事業統合を行うことで、販路拡大・技術力向上・人材育成などを図ろうとする動きが近年ますます活発化してきました。また、金融機関などの地域密着型企業同士の経営統合や、大手企業による県内拠点買収など、さまざまな手法でM&Aが利用されています。
2. 製造業関連のM&A事例
2-1. 日本鋳造による新東北メタルの一部株式譲渡
- 譲渡日:2009年7月1日
- 概要:鋳鋼品の製造・販売を手掛ける新東北メタル(秋田県北秋田市)の株式のうち51%を日立建機(東京都文京区)に譲渡し、日本鋳造による所有割合を100%から49%へ引き下げました。
- 背景と目的:新東北メタルの技術力向上や収益安定化を目指し、大手建機メーカーの傘下でシナジーを創出する狙いがありました。秋田県北秋田市にある生産拠点の強化と新規受注拡大が期待されました。
- ポイント:鋳鋼品は建設機械に欠かせないパーツであり、日立建機と組むことで、安定的かつ継続的な受注が見込めると同時に、研究開発面での支援や技術ノウハウの共有が進んだと考えられます。
2-2. 住友金属鉱山による住鉱テックの譲渡
- 譲渡発表:2022年7月29日
- 概要:非鉄事業に経営資源を集中するため、コネクター製造子会社である住鉱テック(横浜市)の全株式をミネベアミツミ傘下のミツミ電機に譲渡しました。住鉱テックは1990年に設立され、秋田県能代市に能代工場を、宮城県利府町に仙台工場を構えています。
- 背景と目的:住友金属鉱山は主力の非鉄金属事業に注力する方針を明確化しており、コネクター事業を手放すことで経営の選択と集中を推進しました。一方、ミネベアミツミはコネクター事業の拡大を目指しており、能代工場の生産能力や熟練の人材を取り込みたいという思惑がありました。
- ポイント:秋田県における電子部品製造事業が外資や大手企業の系列下で強化されることで、雇用や地元企業への受注など地域経済への影響が期待される一方で、グローバルな競争環境への対応も一層求められます。
2-3. プレシジョン・システム・サイエンス(PSS)によるエヌピーエスの連結子会社化
- 取得日:2012年7月31日
- 概要:PSSは遺伝子検査等の体外診断分野に強みを持つ企業で、秋田県大館市に本社を置くエヌピーエス(NPS)の株式を追加取得し、持分法適用関連会社から連結子会社にしました。
- 背景と目的:自動化装置の需要が世界的に拡大する中、製造コスト削減と生産管理体制強化を目的として、NPSを子会社化することで開発・製造のスピードアップを図る狙いがありました。
- ポイント:秋田県の大館市に製造拠点を持つNPSを傘下に収めることで、PSSの製造体制が盤石となり、研究開発から量産までの一貫した対応が可能になるメリットがあります。
2-4. メイコーによるベトナムEMS企業の子会社化と十和田グループとの関係
- 発表日:2019年9月3日
- 概要:メイコーは、ベトナムに拠点を持つ電子機器受託製造サービス(EMS)企業「Towada Electronics Vietnam(十和田ベトナム)」の持分60%を取得し子会社化しました。同社は秋田県小坂町に本社を置く十和田オーディオを中心とする十和田グループの一員です。
- 背景と目的:メイコーはベトナムでプリント基板の設計・生産を行っており、EMS事業をさらに拡大するため、十和田ベトナムを取り込む形となりました。
- ポイント:秋田県小坂町に拠点を持つ十和田グループの海外子会社を取り込むことで、地元企業のグローバル展開を後押ししつつ、メイコー側は日系EMSメーカーとして東南アジアでのプレゼンスを向上させる狙いがあるとみられます。
2-5. フジックスによるシオンの子会社化
- 取得日:2009年10月10日
- 概要:ミシン糸製造販売大手のフジックスは、卸売会社シオン(秋田県横手市)の全株式を取得し、あわせて9500万円の増資を引き受けることを決議しました。
- 背景と目的:フジックスは国内縫製市場が縮小する中、東北地区の販売シェア拡大を喫緊の課題としていました。シオンは東北地方でフジックス製品を主力とする販売会社であり、同社を子会社化することで地域での競争力を強化した格好です。
- ポイント:縫製関連市場はグローバル競争が激しく、国内市場の縮小が避けられない中でも、地方卸売企業の活用によるきめ細やかな顧客アプローチが期待されています。
3. エネルギー関連のM&A事例
3-1. 日本風力開発による八峰風力開発の子会社化
- 取得日:2014年2月28日
- 概要:日本風力開発は子会社を通じて八峰風力開発(東京都港区)の株式90%を取得し子会社化しました。八峰風力開発は秋田県八峰町で風力発電施設の開発・電力販売を手がけており、東北電力への系統連携の権利を保有していました。
- 背景と目的:秋田県は風力発電に適した地域が多く、再生可能エネルギー関連の開発が活発です。日本風力開発は地域資源を活かすため、系統連携権を有する企業の買収により事業拡大を図りました。
- ポイント:地元自治体や地域住民との協力体制の構築が重要となるエネルギー事業では、早期の開発進行が利益確保につながりやすく、風力発電の設備投資リスクを低減する効果が期待されます。
3-2. 日本風力開発による若美風力開発の株式譲渡
- 譲渡予定日:2014年12月12日
- 概要:日本風力開発は、子会社を通じて保有していた若美風力開発(東京都港区)の株式51%を、英国拠点の再生可能エネルギー開発企業RESグループの日本法人に譲渡しました。若美風力開発は秋田県男鹿市で風力発電プロジェクトを進めています。
- 背景と目的:大規模な風力発電プロジェクトを進めるには膨大な資金調達が必要です。海外大手のエネルギー企業を巻き込み、共同事業化することで資金力・ノウハウを取り込み、リスク分散や開発速度向上を図りました。
- ポイント:秋田県の風力発電事業を巡っては、海外企業も参入を模索しており、再生可能エネルギー分野の国際的な資金と技術の流入が県経済にプラスに働く一方、地元企業だけでは難しい大規模投資案件の進捗が加速するというメリットがあります。
3-3. レノバによるバイオマス発電所運営会社ユナイテッドリニューアブルエナジー(URE)の子会社化
- 取得発表:2017年7月6日
- 概要:レノバは秋田県の木質バイオマス発電所を運営するUREを、共同で設立する千秋ホールディングス(秋田市)を通じて子会社化しました。レノバ自身は千秋ホールディングスの株式51.0%を取得し、UREが持つ発電事業を傘下に収めています。
- 背景と目的:バイオマス発電事業は安定的な電力供給と森林資源の有効活用を両立できるとして注目されています。レノバは再生可能エネルギー事業を全国で展開しており、秋田県での事業基盤強化を目指したといえます。
- ポイント:秋田県の豊富な森林資源を活用し、地域に根差した再生エネルギー生産が期待されるほか、農林業の活性化にも寄与すると考えられます。
3-4. TOKAIホールディングスによるにかほ市ガス事業の取得
- 取得予定日:2020年4月1日
- 概要:TOKAIホールディングスは100%子会社の東海ガス(静岡県焼津市)を通じ、にかほ市(秋田県)の都市ガス事業を譲り受けることを決定しました。
- 背景と目的:にかほ市ガス水道局が運営していた同地域のガス供給件数は約5172件、年間売上高は4億円を超えています。TOKAIは静岡県外へのエネルギー事業拡大を図っており、秋田県への進出で販路を広げる考えです。
- ポイント:地方自治体がインフラ事業を民間に譲渡するケースが増加しており、民間企業側はスケールメリットやコスト削減を追求できます。一方、市民にとってはサービス維持・向上が期待されます。
4. 金融関連のM&A事例
4-1. 荘内銀行(山形県)と北都銀行(秋田県)の経営統合
- 統合日:2009年10月1日
- 概要:山形県鶴岡市に本店を置く荘内銀行と、秋田県秋田市に本店を置く北都銀行が株式移転方式でフィデアホールディングス(仙台市)を設立し、経営統合しました。
- 背景と目的:両行とも東北地方を主な営業基盤としており、独自のブランド力強化と相乗効果(規模の拡大やコスト削減)を狙っての統合です。
- ポイント:秋田県・山形県を中心とした地域金融機関が連携することで、貸出先の多様化や企業への支援強化が期待されました。地方銀行同士の再編の動きとしても注目されました。
4-2. フィデアホールディングスによるグランド山形リースの子会社化
- 取得日:2018年10月1日
- 概要:フィデアホールディングスは総合リース業のグランド山形リース(GYL、山形市)の全株式を取得し子会社化しました。
- 背景と目的:フィデアは荘内銀行と北都銀行が統合してできた持株会社であり、リース機能を強化することで、法人顧客や公共分野への金融サービスの幅を広げようとしています。秋田県でも北都銀行を通じて同様の取り組みを展開し、事業拡大を狙っています。
- ポイント:リース事業は設備投資をサポートする意味合いが強く、地域経済にとって欠かせないサービスです。フィデアグループ全体でリースサービスを拡充することで、秋田県内の企業支援に一層貢献する意図がうかがえます。
5. 流通・小売関連のM&A事例
5-1. アークスとジョイスの経営統合
- 統合日:2012年9月1日
- 概要:北海道を地盤とするアークス(札幌市)と、岩手県を中心に秋田県・青森県へ展開するジョイス(盛岡市)が株式交換方式により統合。ジョイスはアークスの完全子会社となり上場廃止となりました。
- 背景と目的:人口減少、少子高齢化などの環境下で生き残りを図るべく、北東北の食品スーパーマーケットを傘下に収める戦略をアークスが進めていました。ジョイス側も大手グループとの連携で経営基盤を強化する狙いがありました。
- ポイント:秋田県内でもジョイスの店舗が展開されており、アークスグループ入りによる共同仕入れやコスト削減が期待される一方、地元競合他社との競争が激化する可能性もあります。
5-2. ヤマザワによるよねや商事の子会社化
- 取得予定日:2014年2月28日
- 概要:山形県に本社を置くヤマザワは、秋田県内でスーパーを展開するよねや商事(秋田県横手市)の株式90%を追加取得し、完全子会社化しました。
- 背景と目的:東北地方における食品スーパー業界は競争が激しく、規模拡大と経営資源の共有で収益力を向上させる目的があります。よねや商事は秋田県南部を中心に地域密着で営業しており、ヤマザワの広域展開戦略とマッチしました。
- ポイント:秋田県内の消費者にとっては品揃えや価格競争力の向上が期待されますが、地元中小スーパーにとっては大手の参入が脅威となりうる側面もあります。
5-3. アコーディア・ゴルフによる男鹿ゴルフクラブの株式譲渡
- 譲渡日:2012年3月23日
- 概要:アコーディア・ゴルフは子会社であるアコーディアAH11が保有する男鹿ゴルフクラブ(東京都渋谷区)の全株式を、秋田県秋田市の男鹿興業社に譲渡しました。
- 背景と目的:ゴルフ場事業の収益性や将来計画から、地元企業へ経営を任せる方が地域に根差した運営ができると判断したとされています。
- ポイント:地域住民との関わりが強いゴルフ場は、地元企業が運営主体となることで地域コミュニティに寄与しやすくなります。大手資本が撤退する動きは全国的にも見られ、地方企業による事業継続が重要となります。
5-4. カウボーイによる本間物産の譲渡(伏見屋グループとの関係)
- 譲渡日:2008年2月29日
- 概要:カウボーイは子会社の食品スーパー本間物産(山形県遊佐町)の全株式(53.85%所有)を伏見屋(秋田県仙北市)に譲渡しました。本間物産は東北地方と新潟県で店舗を展開していました。
- 背景と目的:カウボーイは小売事業の再生過程にあり、経営資源を集中させるために収益性の見直しを進めた結果、伏見屋への売却を決定しました。
- ポイント:伏見屋は秋田県を拠点とする酒類販売などを手掛ける企業で、その後グループ企業を通じてスーパー事業を拡大し、近年ではクスリのアオキホールディングスとの取引にも発展しました。
5-5. ダイユーエイトによる日敷(にっしき)の子会社化
- 取得予定日:2015年1月13日(実際の取得価額は6億5000万円)
- 概要:福島県を中心にホームセンターを運営するダイユーエイトは、秋田県湯沢市を地盤とするホームセンター会社、日敷の株式を追加取得し、所有割合を51%に引き上げました。
- 背景と目的:秋田県への営業基盤強化とホームセンター事業の拡大を狙い、既存株式に加えて追加取得を行いました。
- ポイント:ホームセンター業界は大型化が進み、品揃えやDIY需要への対応力が重視されています。地域性の強い秋田県でのシェア向上を図るには地元企業との連携が効果的です。
5-6. クスリのアオキホールディングスによる伏見屋グループのスーパー事業取得
- 取得予定日:2025年2月28日
- 概要:ドラッグストア大手のクスリのアオキホールディングスは、秋田県仙北市に本社を置く伏見屋グループが東北・関東で展開するスーパーマーケット事業46店舗を一挙に取得すると発表しました。
- 背景と目的:ドラッグストアと食品スーパーの融合で集客力を高め、競合他社との差別化を図る目的があります。伏見屋グループの「フレッシュフードモリヤ」「マルホンカウボーイ」「サン・マルシェ」などを取り込むことで、一気にスーパー事業を拡大し、秋田県への本格進出を果たします。
- ポイント:ドラッグストア業界の競争が激化する中、食品分野の売上を拡大することで客単価を引き上げる戦略が一般化しており、大型M&Aとして注目されています。
5-7. ツルハホールディングスによるおおがたむら調剤薬局の子会社化
- 取得予定日:2019年7月4日
- 概要:ツルハHDは秋田県大潟村にある調剤薬局1店舗の運営会社「おおがたむら調剤薬局」の全株式を取得しました。
- 背景と目的:調剤専門薬局をグループに取り込むことで、ドラッグストアとの相乗効果を高め、地域住民へ総合的な医療サービスを提供する狙いがありました。
- ポイント:秋田県は地域医療の担い手不足が懸念される地域も多く、調剤薬局とドラッグストアの一体運営により、利便性向上と地域医療の補完が期待できます。
6. 食品・農業関連のM&A事例
6-1. プリマハムによるユキザワの子会社化
- 取得予定日:2018年6月29日
- 概要:プリマハムは子会社の太平洋ブリーディング(福島県富岡町)を通じて、SPF豚(特定病原体不在)を生産するユキザワ(秋田県大館市)の全株式を取得しました。
- 背景と目的:国産豚肉の生産・販売拡大と効率化を最優先課題とするプリマハムにとって、ユキザワの生産拠点は出荷頭数の大幅増に寄与します。SPF豚は品質面で評価が高く、安定的な供給体制確立が求められていました。
- ポイント:秋田県大館市での養豚事業拡大により、地域の農業振興と雇用創出が期待されるほか、プリマハムはグループ内での生産・加工・販売を一貫管理することでブランド力を高める戦略を推進できます。
6-2. JFLAホールディングス(盛田)による阿櫻酒造など10社の譲渡
- 譲渡予定日:2023年1月1日
- 概要:JFLAHD傘下の盛田が保有する酒造会社10社の全株式を、酒類関連のコンサルを行う伝統蔵(東京都中央区)に譲渡しました。その中に秋田県横手市の阿櫻酒造が含まれています。
- 背景と目的:コロナ禍で酒類消費が落ち込む中、経営改善計画の一環として酒造会社を外部に売却し、事業再編を図りました。
- ポイント:阿櫻酒造は秋田を代表する酒造銘柄の一つで、今後は伝統蔵の支援のもとブランド価値向上や海外展開などが期待されます。ただし、地元に根付いた銘柄が外部資本へ移ることで、今後の経営方針がどう変化するか注目されています。
7. サービス業・IT関連のM&A事例
7-1. ナックによる秀和住研の子会社化
- 取得日:2024年5月24日
- 概要:ナックは注文住宅建築を手掛ける秀和住研(青森県八戸市)の全株式を取得し、子会社化しました。秀和住研は秋田県内にも住宅展示場を4カ所展開しており、ナックグループの住宅フランチャイズ事業「ACE HOME」を展開しています。
- 背景と目的:フランチャイズ加盟店の中でも実績のある企業を直接子会社化することで、収益基盤を強化しつつ地域でのサービス向上を図る意図があります。
- ポイント:青森・秋田エリアでの住まいづくりニーズに対応しながら、フランチャイズ本部としての商品企画・マーケティングを強化する相乗効果が見込まれます。
7-2. ピーエイによるトラバースの子会社化
- 取得日:2015年10月1日
- 概要:ピーエイは無料求人情報誌「ジョブポスト」を主力とする求人広告代理店で、岩手県、秋田県、青森県で展開するトラバースの株式を取得しました。
- 背景と目的:北東北エリアでの販路拡大と、求人広告サービスのシェア拡大が主要な狙いです。地方の労働市場は求人・求職のマッチングが課題となることも多く、新しいサービスの展開が期待されます。
- ポイント:秋田県においても地元企業の求人需要は高いものの、人口減少が進む中で労働力確保が課題です。ピーエイのネットワークを活用して効率的なマッチングが進むことが期待されます。
7-3. セントケア・ホールディングによる虹の街(および虹の街企画)の子会社化
- 取得予定日:2015年7月1日
- 概要:セントケアHDは在宅介護サービスを行う虹の街(秋田県北秋田市)の全株式を取得し、同社子会社の虹の街企画も吸収合併する形で事業を統合しました。
- 背景と目的:東北エリアでの在宅介護事業を強化し、秋田県へ新規参入することで事業拡大を目指しています。
- ポイント:秋田県は高齢化率が高く、在宅介護サービスの需要も大きいと予想されます。セントケアHDとしては地域における事業基盤を得ることで、さらなる成長機会を狙っています。
7-4. チェンジホールディングスによる東光コンピュータ・サービスの完全子会社化
- 発表日:2024年8月14日
- 概要:チェンジホールディングスは、秋田県大館市に本社を置き自社開発ソフトを全国展開する東光コンピュータ・サービスの株式を追加取得し、持ち株比率を14.5%から100%に引き上げ、完全子会社化することを決定しました。
- 背景と目的:資本業務提携の一環として既に14.5%を保有していましたが、さらなる相乗効果を実現するには完全子会社化が最適と判断したものです。
- ポイント:東光コンピュータ・サービスは森林組合向けシステムや健診システムなどニッチな分野で実績があり、チェンジグループによるデジタル技術との融合が進めば、秋田県発のITサービスが全国に普及する可能性があります。
8. 医療関連のM&A事例
8-1. ウイン・パートナーズによる大沢商事の子会社化
- 取得予定日:2017年10月1日
- 概要:医療機器販売を手がけるウイン・パートナーズ子会社のテスコ(仙台市)は、秋田県を中心に医療機器を販売する大沢商事(秋田市)の全株式を取得しました。
- 背景と目的:ウイン・パートナーズは東北地方でのシェア拡大を狙っており、大沢商事の地盤である秋田県との地理的補完関係を活かすことで、医療機関向けサービスを強化する方針です。
- ポイント:秋田県は高齢化が進んでいるため、医療需要の増大が見込まれます。医療機器やサービスを円滑に供給できる体制整備は、地域医療の質向上に寄与します。
8-2. ウイン・パートナーズによるエムシーアイの子会社化
- 取得予定日:2018年12月1日
- 概要:ウイン・パートナーズ子会社のテスコは、山形県天童市に本社を置くエムシーアイの全株式を取得し完全子会社化しました。エムシーアイは医療機器販売・賃貸・保守サービスを展開しています。
- 背景と目的:秋田県を含む東北エリアにおける医療機器需要をカバーするため、山形県のエムシーアイを傘下に収めたものです。大沢商事の買収と合わせ、東北全域でのサービス網拡大を図っています。
- ポイント:ウイン・パートナーズは、医療機器の販売からアフターサービスまで一括でサポートする体制を構築し、東北地方でのトップシェアを目指しています。
9. M&Aが秋田県経済・産業にもたらす影響
秋田県では、従来から製造業を中心に堅実な地場企業が多く存在してきました。しかし、人口減少や市場縮小の影響で企業単独での事業拡大が難しくなるケースも増えています。こうした中で、M&Aは以下のようなメリットや課題をもたらします。
- 経営資源の補強と事業再編
- 大手企業の資本や技術を取り込むことで、地域企業が生き残りと成長のチャンスを得られます。
- 選択と集中により、非中核事業を手放して本業に専念する動きも見られます。
- 雇用と技術移転
- 県外・海外企業による買収でも、既存雇用が維持されるケースが多く、雇用の安定につながることがあります。
- 新オーナー企業からのノウハウや研究開発力の移転は、県内の技術水準向上に寄与します。
- 地域経済の活性化と課題
- 流通・小売業や介護・医療など身近なサービス分野でのM&Aは、県民の利便性向上につながりやすい一方、地域独自の中小企業が大手に飲み込まれるリスクも存在します。
- 外部資本の増加は新しいビジネスチャンスをもたらす反面、経営判断が県外や海外の意向に左右されやすくなる懸念もあります。
- 公共性の高いインフラ・自治体事業の譲渡
- ガス・水道などの公共事業の民営化により、サービスの効率化や財政負担の軽減が期待されますが、住民サービスの維持・向上が確保されるかどうかが常に課題となります。
10. 今後の展望と課題
秋田県が抱える構造的な問題(人口減少、高齢化、担い手不足など)は、今後も続くと予想されます。一方、再生可能エネルギーや農林水産業、IT、医療などは成長が見込まれる分野であり、大手・外資企業との連携やM&Aを通じて新たなビジネスチャンスを生み出す動きは継続的に行われるでしょう。
- 事業承継問題とM&Aの重要性
県内企業の経営者高齢化や後継者不足により、事業承継の手段としてM&Aがますます必要とされます。地元金融機関や自治体、専門家が連携して支援体制を整えることで、地域産業の空洞化を防ぐことが急務です。 - グローバル展開のチャンス
製造業においては、海外の需要を取り込むことで市場規模を拡大する例が出てきています。秋田県発の技術や製品を、M&Aを活用してグローバルマーケットに売り込む動きも期待されます。 - 地域独自の価値を守る取り組み
酒造業や食品スーパーなど、地域色の強い企業が外部資本傘下に入る場合、地元ブランドや伝統の維持・発展が課題となります。M&A後も地域コミュニティと良好な関係を築き、企業の長所を活かす取り組みが求められます。 - 行政・金融機関の積極的なサポート
秋田県内のM&Aを円滑に進めるため、経済団体や地方銀行が仲介・情報提供を行い、マッチングを促進する役割が重要となるでしょう。
まとめ
秋田県のM&A事例を振り返ると、製造業・エネルギー・小売・金融・医療・介護など、多岐にわたる分野で事業統合や買収・譲渡が行われていることがわかります。これらの動きの根底には、地域の人口減少と市場縮小という大きな課題が存在しますが、同時に再生可能エネルギーや農業、IT、サービス分野などで新たな成長の可能性を模索する企業の姿勢も明確です。
大手企業や外資系企業との連携・統合は、しばしば「地元色の喪失」や「利益の域外流出」への懸念が伴います。しかし、M&Aは地元企業の生き残りと成長にとって有力な選択肢でもあり、地域の人材・技術を守り、雇用を維持するためには不可欠な手段となりつつあります。今後も行政や金融機関、支援団体が積極的に関与し、うまく誘導することで、秋田県全体の産業競争力の強化につなげていくことが重要でしょう。
M&Aは企業だけでなく、そこに働く人々や地域社会にも大きな影響をもたらします。経営統合によるサービス向上や商品供給力のアップ、インフラ整備の効率化など、プラス面を最大化しつつ、地域特性を損なわないよう配慮することが求められています。秋田県における数多くの事例は、こうしたさまざまなバランスを模索しながら、県内外との連携を深めてきた歴史ともいえます。
今後も、経済や社会の構造変化が加速する中、秋田県の企業がどのように変化に対応し、新たな成長軌道を描いていくのか、その成否のカギを握るのがM&Aを含む柔軟な経営戦略であることは間違いありません。秋田の地から新たなビジネスモデルや企業連携の先駆例が生まれていくことに、今後一層の期待が寄せられています。

株式会社M&A Do 代表取締役
M&Aシニアエキスパート・相続診断士
東京都昭島市出身。慶應義塾大学理工学部を卒業後、大手M&A仲介会社にて勤務し、その後独立。これまで製造業・工事業を中心に友好的なM&Aを支援。また父親が精密板金加工業、祖父が蕎麦屋、叔父が歯科クリニックを経営し、現在は父親の精密板金加工業にも社外取締役として従事。