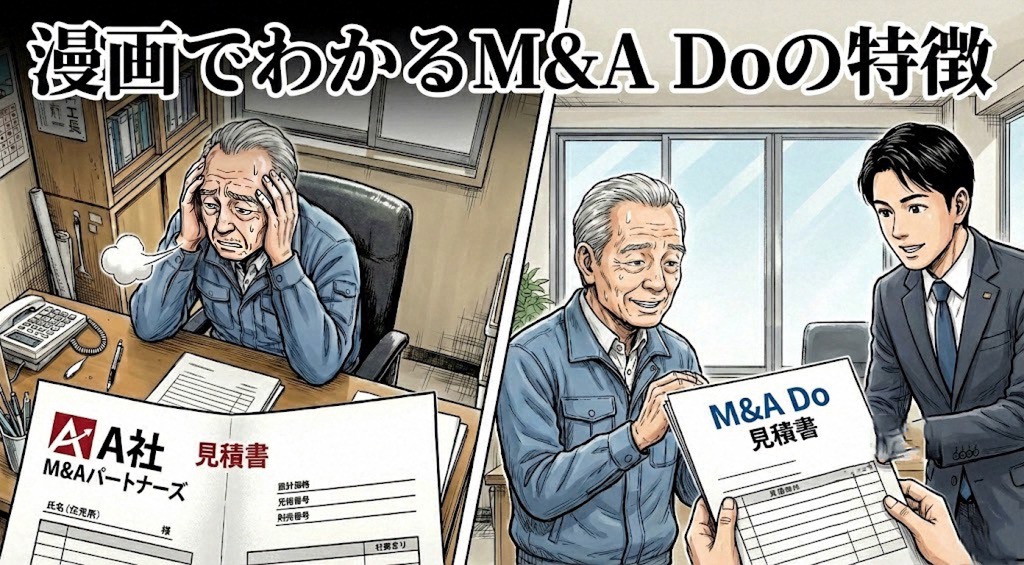経営業務管理責任者がいない時の対策まとめ
― 令和2年10月の建設業法改正対応版 ―
近年の建設業界では、職人や管理職をはじめとする人材不足が深刻化するなか、事業運営上欠かせない「経営業務の管理責任体制」をいかに確立するかが、大きな課題となっています。かつては「経営業務管理責任者」(以下「経管(けいかん)」と呼称されることもありました)という資格要件が厳格に定められていましたが、令和2年10月の建設業法改正により、この資格要件は形式的には廃止されました。
ただし、現在は新たに「経営業務を適切に行うための体制を整えていること」を示さなければ建設業許可が取れない、あるいは更新できない仕組みになっており、実質的には「会社経営に必要な知識・経験を有する役員を配置すること」が求められています。
では、もしそのような経験を持つ役員(旧・経管相当要件を満たす人材)がいなくなった場合、どうすればいいのでしょうか。本記事では、「経営業務管理責任者がいない時の対策」について、令和2年10月改正後の制度や実務事情を踏まえてわかりやすく解説します。最終的にはM&A(会社売却)という選択肢を含め、様々な対応策を網羅していますので、自社に合った方法を検討する際の参考にしてください。
1. 「経営業務管理責任者」制度は本当に廃止?
改正のポイントをおさらい
1-1. 令和2年10月の改正建設業法で何が変わった?
従来の建設業法では、建設業許可を取得・維持するために「経営業務管理責任者」(経管)を役員等として常勤配置することが義務付けられていました。具体的には「5年以上の経営経験」や「7年以上の経営補佐経験」といった実務年数要件を満たすことが必要で、社長や古参役員がこの役割を担うケースが大半でした。
しかし、令和2年10月の改正で「経管」の制度は形式上は廃止され、以下のように変更されました。
- 新要件:「経営業務を行う体制を有していること」
会社として経営業務を適切に遂行できる体制があるかを審査されます。
例えば「常勤の取締役(または支配人)に一定の経営経験がある者が含まれているか」「複数人の体制で経営業務をカバーできるか」などがポイントになります。 - 具体的な証明方法
「経営業務の管理責任を担う役員が、過去に何年か建設業の経営に携わっていた」という書類を提出する、
もしくは「建設業の経営経験は短いが、他の管理者と協力して適切に経営を行う体制がある」ことを示す、
などのパターンがあります。
つまり「経管」という肩書そのものがなくなっただけで、実質的には「建設業経営の知識・経験がある役員」が常勤していることを示す必要がある点は変わっていません。
1-2. 経営業務管理責任体制を満たせないとどうなるのか
経営管理の体制要件が満たせない(=それに該当する役員がいない)場合、新規で建設業許可を取得できないだけでなく、許可の更新も認められない可能性があります。さらに、建設業法では主要な役員が変更になった場合、30日以内に都道府県知事や国土交通大臣への届出が必要です。これを怠ると、許可取消や許可失効といったリスクもあるため、想定外のトラブルを避けるためにも早めの対応が必要です。
1-3. 名義貸しは絶対にNG
経管制度が廃止された後でも、名義貸しに対する取り締まりは厳格化し続けています。非常勤の人を形だけ役員にして書類上だけ常勤と偽るなどの行為は違法です。行政側の審査も厳しくなっているため、名義貸しが発覚すると厳しい処分が下される可能性があります。
2. 経営業務管理責任者(相当の人材)がいないときの対策
それでは、実際に「旧経管要件を満たす役員」がいなくなったり、もともと存在しなかったりする場合に、どのような選択肢があるのでしょうか。今回は大きく3つの方向性に分けて解説します。自社の状況や許可更新時期、事業規模などを踏まえ、検討してみてください。
2-1. 社内で要件を満たせる役員候補者を育成・配置する
2-1-1. 要件を満たす常勤役員の要素とは
令和2年改正後の建設業許可要件では、「経営業務を行う体制」として以下のような人物を役員に据えるケースが想定されています。
- 建設業の経営経験が5年以上ある(または旧制度で経管要件を満たしていた)
- 経営経験が短くても、他の管理者と連携して適切に経営できる体制を整えている
- 常勤役員として従事している(非常勤では認められない可能性が高い)
2-1-2. 社内登用・昇格のメリット
1. 会社の実情を理解している
既存社員を役員に昇格させる場合、社内の雰囲気や取引先、業務フローなどを把握しているため、経営判断がスムーズに行われやすいです。
2. 社員のモチベーション向上
後継者問題が解消され、キャリアパスが明確になることで、ほかの従業員の士気にも好影響を与えます。
3. 育成コストの内訳が明確
新しく外部から人を採るより、社内の給与体系や教育費を把握しやすく、計画的に進めやすいメリットがあります。
2-1-3. 注意点
- 育成期間が必要
どのように経営に関与していたか証明するための書類準備なども含め、すぐに体制が整わない場合があります。 - 経営全般の知識習得
現場や技術だけでなく、労務・財務・法務など幅広い業務を理解することが求められます。 - 常勤役員としての条件
労働条件や報酬体系をきちんと設定し、名義貸しと疑われない実態が必要です。
2-2. 外部から要件を満たす人材を採用・招へいする
2-2-1. 外部採用の利点
即戦力の確保が最大のメリットです。他社で建設業許可の役員経験を持つ人材を常勤役員として迎えれば、書類上の要件をすぐに満たせる可能性が高く、同時に経営ノウハウも期待できます。外部からの視点によって、社内の仕組みや営業戦略を再点検するきっかけにもなるでしょう。
2-2-2. 採用時の注意点
- 名義貸しと疑われない形で常勤
非常勤や嘱託契約などで実態のない状態だと、書類審査で問題視される可能性大。 - 相応の役員報酬・条件
経営経験者は希少価値が高く、報酬も高めになる傾向があります。採用予算とのバランスを考慮しましょう。 - 社内文化との相性
外部から来た人材と既存スタッフの間に軋轢が生じないよう、導入前に十分な調整・説明が欠かせません。
2-2-3. 人材確保の手段
- 人材紹介会社・転職エージェントを利用する
- 業界団体や組合でのOB・シニア人材の紹介
- シニア層向けのマッチングサイトなどの活用
2-3. 事業の抜本的な再編:範囲縮小やM&Aの検討
2-3-1. 許可不要の軽微工事だけに特化する
建設業許可は「1件あたりの工事代金が500万円以上(建築一式は1,500万円以上)」で必要とされます。これ未満の工事にしか手を出さない――つまり、許可不要の領域に経営をシフトするという選択もあります。
例えば小規模リフォームやメンテナンスを主力とすれば、許可そのものを保有しなくても一定の事業は成立します。
メリット: 許可の維持コストや更新手続き、管理責任者要件の悩みから解放される
デメリット: 大型案件や公共工事を一切受注できないため、売上や信用面の影響が大きい
2-3-2. M&A(会社売却・統合)で根本解決
社内に後継者がいない場合や経営者が高齢化している場合、M&A(事業譲渡や株式譲渡)によって他社に統合するのも大きな選択肢になります。
すでに買い手側が建設業許可要件をクリアしている場合は、そちらの体制のまま事業を継続できるため、速やかに「経営業務を行う体制」を満たすことが可能です。
メリット:
- 許可要件の維持が可能
買い手グループで経営経験豊富な役員が揃っており、自社の役員不足を一気に解消できる。 - 株式売却益による創業者のキャッシュ化
引退や老後の資金確保がスムーズになる。経営から早期退任しやすい。 - 従業員の雇用維持
買い手企業が事業拡大の意向を持っている場合、雇用や既存取引先も引き継がれる可能性が高い。
デメリット:
- 経営権が買い手に移るため、オーナーとしての自由度は失われる。
- 企業文化の違いによる従業員の戸惑い、トラブルが起こる可能性。
- M&A仲介手数料やデューデリジェンス(調査)のコスト・時間がかかる。
3. 経営管理要件が途絶した場合の手続きとリスク
3-1. 「30日以内の届出」が必要
建設業許可事業者が主要役員を退任・死亡などで変更したときは、30日以内に都道府県知事または国土交通大臣への届出が必要とされています。
もし変更後に要件を満たす役員が誰もいない場合、迅速に対応策を講じないと許可取消につながる恐れがあります。
3-2. 更新時に要件不備が判明すると…
建設業許可は一般的に5年ごとの更新ですが、その際に「経営業務を行う体制」を改めて審査されます。そこで要件を満たしていないと許可の更新が認められず、営業自体が違法状態となってしまうリスクがあります。
3-3. 名義貸しや書類偽装は厳禁
「とりあえず名前だけ借りる」「経営経験を虚偽申告する」などの行為は明確に違法であり、近年の取り締まり強化もあって発覚リスクが高まっています。
許可取消だけでなく、罰金刑や業務停止命令を受ける可能性もあるため、絶対に避けなければなりません。
4. 事例紹介:経管不在をどう乗り越えたか
4-1. 事例1:外部役員を招いて許可更新に成功
状況:
社長兼「経管」を担っていた創業者が高齢により退任を決定。社内に10年以上勤務するベテラン社員はいるが、経営経験の証明が難しく、許可更新まで1年しかない。
対応策:
建設業に特化した人材紹介会社を使い、他県で建設会社役員を務めたシニア人材をスカウト。フルタイム常勤役員として雇用し、必要書類を準備した。
結果:
許可更新が滞りなく完了。新役員の経験から社内改革も進み、業績アップに繋がった。
4-2. 事例2:社内昇格で要件を満たしたケース
状況:
社長(経管)が急逝し、副社長は経験年数が2年と不足。だが、技術部長が以前別の建設会社で7年ほど管理業務に関与していた。
対応策:
技術部長を取締役に昇格し、過去の経営近いポジションであったことを証明する在籍証明や契約書などを集め、行政書士に相談して書類を整備。
結果:
変更届および更新手続きが認められ、許可継続に成功。技術部長が経営にも携わるようになり、一体感ある組織体制が構築された。
4-3. 事例3:M&Aで許可要件と事業承継を両立
状況:
地域密着型の中小建設会社。社長が70代で後継者がおらず、社員は現場監督や職人がメイン。許可更新まで2年あるが、社長は早めに退きたい意向。
対応策:
M&A仲介会社に打診し、公共工事分野を強化したい中堅建設会社(買い手)に株式譲渡。社長は買収後半年間顧問として残り、引き継ぎを行う。
結果:
社長は売却益で引退後の生活を確保。買い手は即戦力として従業員を迎え入れ、元々持っていた建設業許可とあわせてスムーズに事業拡大。従業員の雇用と取引先も維持され、ウィンウィンの関係となった。
5. 実際に動くときの手順・ポイント
5-1. まずは現状の棚卸し:要件をどこまで満たせるのか
1. 常勤役員リストの再確認
現在の役員がいつからどんな業務に携わり、どんな証明書類を用意できるか整理してください。
2. 許可更新や受注案件のスケジュール
次回更新までの猶予や今後の受注見込みなどを考え、いつまでに体制を整える必要があるか明確にします。
5-2. 行政書士や専門家への相談
建設業許可の審査は書類のボリュームが多く、細かな要件も定期的に改正されるため、行政書士などの専門家に相談するとスムーズです。特に経営経験を証明するための在籍証明や工事経歴の整合性など、見落としがちなので注意しましょう。
5-3. 社内か外部か、それともM&Aかを検討
- 社内登用や昇格:
育成に時間はかかりますが、企業文化を理解した人材を上手く活用できる利点があります。 - 外部採用:
即戦力を確保できますが、コストが高くなり、カルチャーの調整も必要です。 - 許可不要へのシフト:
規模を縮小して軽微な工事に特化する手段。売上ダウンや取引先の減少も想定されます。 - M&A(会社売却など):
根本解決を図る大きな選択肢。後継者難や財務改善など同時に解決できますが、交渉や手数料が発生し、経営権を手放すデメリットも。
5-4. コンプライアンスと余裕あるスケジュール
不正行為は絶対に避けることと、早めに動くことが何よりも大切です。更新期限や役員変更の届出期限が迫ってからバタバタしても間に合わないケースが多いため、最低でも半年〜1年前を目安に準備を進めましょう。
6. まとめ:経営業務管理責任体制の不在は“事業の岐路”
旧制度上の「経営業務管理責任者」がいなくなった(または該当者が不足している)状況は、会社にとって大きな経営リスクになりますが、同時に事業戦略全体を見直すきっかけでもあります。
社内で後継者を育てるのか、外部から即戦力を招へいするのか、それともM&Aで抜本的に解決するのか――。いずれの道を選択するにせよ、早期に情報を収集し、計画的に手続きを進めることが重要です。特に、許可更新のタイミングは見逃せません。
また、安易に「名義貸し」などで切り抜けようとするのは、違法リスクと重い罰則が待ち受けているため絶対にやめましょう。建設業界のコンプライアンス意識が高まる中、そうした不正行為は企業の信頼と存続を根底から揺るがす結果を招きかねません。
経営業務管理責任体制の不在を早めに察知できれば、事前に専門家(行政書士・弁護士・税理士・M&A仲介会社など)と連携し、時間をかけて最適な解を探ることができます。特にM&Aを検討する場合は、数カ月から1年近くの準備期間が必要になるケースもありますので、余裕をもって動き出すことが成功の鍵です。
7. おわりに
本記事では、令和2年10月改正後の建設業許可制度を踏まえた「経営業務管理責任者(または相当要件を満たす役員)が不在になったときの対策」を概観しました。最新の建設業法や実務動向に即した正しい手続きを行っていただければと思います。
繰り返しになりますが、名義貸しや書類偽装といった短絡的な方法は厳禁です。結果的に取り返しのつかないダメージを受ける危険があります。
最後にポイントを振り返ると、
- 社内で後継者を育成・登用するか
- 外部から経験者を確保して即戦力にするか
- 事業規模を縮小し、許可不要の領域だけに集中するか
- M&Aによる会社売却や合併で根本的に解決するか
これらを的確に見極めるには、自社の財務状況、社内の人材、そして今後の事業計画を総合的に考慮する必要があります。もし判断に迷う場合は、ぜひ早めに専門家へ相談してください。先手を打つことが、許可の継続と事業の存続・発展を両立させる大きな秘訣となるはずです。
以上、「経営業務管理責任者(相当の人材)がいない状況」を乗り越えるための主な対策を、改正建設業法のポイントとあわせてご紹介しました。この記事が、貴社の将来を切り開く一助となれば幸いです。

株式会社M&A Do 代表取締役
M&Aシニアエキスパート・相続診断士
東京都昭島市出身。慶應義塾大学理工学部を卒業後、大手M&A仲介会社にて勤務し、その後独立。これまで製造業・工事業を中心に友好的なM&Aを支援。また父親が精密板金加工業、祖父が蕎麦屋、叔父が歯科クリニックを経営し、現在は父親の精密板金加工業にも社外取締役として従事。