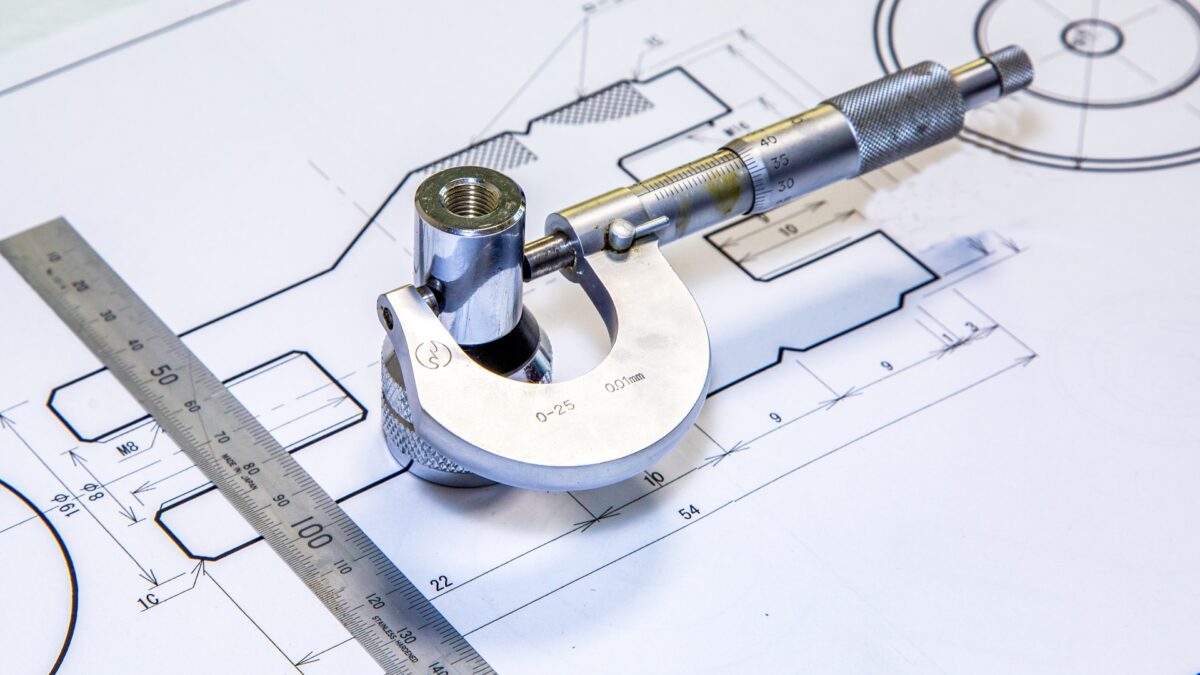- 1. はじめに
- 2. 機械設計業界の概要とM&Aの背景
- 3. 機械設計技術者派遣市場の拡大とM&Aの意義
- 4. 近年の主要事例一覧と概要
- 5. 各事例の詳細と戦略的背景
- 6. 機械設計業界でM&Aが活発化する要因
- 7. M&Aによるシナジー効果と課題
- 8. 今後の展望と注意点
- 9. まとめ
1. はじめに
近年、機械設計業界を取り巻く環境は大きく変化しつつあります。国内外での競争が激化する中、新技術の導入やグローバル展開を図る企業が増え、その一方で人材不足が深刻化しています。とりわけ日本では、少子高齢化による労働力人口の減少が顕在化しており、技術力の維持と確保が企業成長の要となってきました。
こうした状況下で注目される手段の一つが、M&A(合併・買収)です。M&Aは、自社に足りないリソースを迅速に補完したり、既存事業の拡大や新規領域への参入をスピーディに実現したりするために、大変有効な経営戦略といえます。なかでも機械設計業界では、エンジニア派遣事業とのシナジーを狙ったM&Aが、ここ10年ほどの間に数多く見受けられています。
本記事では、機械設計業界におけるM&Aの背景と具体的な事例、さらにそれに伴うシナジー効果や課題、今後の展望などについて詳しく解説していきます。特に、機械設計技術者派遣企業を傘下に収めることで新たな市場を開拓したり、自社の技術力強化や顧客基盤の拡大を狙ったりする動きが顕著です。ここでは、2010年代以降に行われた複数のM&A事例を参照しながら、その背景や狙い、また各企業がどのような成果を狙っているのかを整理し、解説してまいります。
2. 機械設計業界の概要とM&Aの背景
2-1. 機械設計業界とは
「機械設計業界」と一口にいっても、実際には多岐にわたる分野が含まれます。自動車、航空機、家電、産業用ロボット、医療機器、建設機械など、多種多様な製品の設計・開発を担う企業が存在し、それぞれの専門技術を背景に高付加価値を生み出しているのが特徴です。
日本は世界的にも製造業が強い国として知られており、現場のものづくり力を支えるエンジニアの質の高さや、長年培われたノウハウの豊富さが強みとされてきました。しかし、グローバル競争が一段と激化し、高度な設計技術を必要とする新領域が次々と登場している昨今では、企業一社のみで対応することが難しくなっています。
2-2. M&Aが行われる背景
(1) 技術の高度化と新規領域への参入
AI、IoT、ロボティクスなど、新技術が次々に生まれる中で、企業が新分野へ迅速に進出するためには、外部リソースの取り込みが不可欠となる場合が多いです。自社で時間とコストをかけて開発するよりも、すでに実績を持つ企業を傘下に収めるほうが、事業スピードを上げやすくなります。
(2) 人材不足と派遣エンジニアの需要
日本では少子高齢化や理工系人材の確保難によって、エンジニア不足が大きな社会問題となっています。特に機械設計の分野は専門性が高く、経験豊富な人材を集めるのが難しいとされています。企業は人材派遣会社やエンジニア派遣企業を買収することで、人材確保を図り、即戦力を活用しやすくするメリットがあります。
(3) グループ全体の事業多角化・収益基盤安定化
M&Aを通じて、建設業界向けの派遣から機械設計、ソフトウエア領域まで幅広く手がけるグループへと変貌し、景気変動のリスクを分散させる動きも多く見られます。特定の分野に偏るのではなく、複数の業界を相互に補完することで、グループ全体の売上と利益の安定化を図るのです。
(4) 顧客基盤の拡大とブランド力強化
買収対象企業が持つ顧客層や業界での知名度を取り込み、大手メーカーや新規顧客との取引を拡大することで、自社のブランド力や信頼性を向上させられます。特に大企業向けに技術サービスを提供してきた企業を買収するケースでは、M&A直後から取引先が拡大しやすい利点があります。
(5) 経営者の世代交代や事業承継ニーズ
中小企業のオーナー経営者が後継者問題を抱える中、M&Aは事業を円滑に引き継ぐための有力な選択肢となっています。機械設計や技術者派遣の分野では長年の実績とノウハウを有する企業が多い一方で、後継者不在という状況があり、買収先を探しているケースが増えているのです。
3. 機械設計技術者派遣市場の拡大とM&Aの意義
機械設計技術者派遣市場は、製造業における柔軟な労働力活用が浸透するにつれ、年々需要が高まっています。以下では、派遣エンジニアの市場拡大要因と、その中でのM&Aの意義について整理します。
3-1. 派遣エンジニア需要拡大の要因
- 技術革新のスピード
AIやIoT、ロボティクスなどが急速に普及し、企業が一時的・短期的に専門知識を持つエンジニアを求めるケースが増加しました。新分野は試行錯誤の連続であり、企業が常時自社に専門家を抱えるよりも、外部の力を必要なときに活用する方がリスクを抑えることができます。 - 労働力人口の減少
少子高齢化によって、若手エンジニアの確保が難しい状況にあります。製造業に限らず、エンジニアリング業界全体での人手不足傾向は深刻です。経験豊富なベテランや特定分野に強みを持つエンジニアを確保するために派遣会社の活用が進んでいます。 - 企業の経営戦略の変化
製造業や開発部門では、固定費削減や柔軟な体制づくりが求められています。プロジェクト単位でエンジニアをアサインできる派遣ビジネスは、そのニーズに合致しやすく、成果物ベースで活用できる利点があります。
3-2. M&Aの意義
こうした機械設計技術者派遣市場の拡大を背景に、M&Aは次のような意義を持ちます。
- 市場シェア拡大
同業他社や近接する領域の企業を買収することで、顧客基盤やエンジニアの数を一挙に増やすことができます。新規獲得に比べて早期に大きなシェアを確保できる点が魅力です。 - ノウハウの獲得
派遣エンジニアの教育プログラムや管理システム、プロジェクトマネジメント手法などは、企業によって蓄積されたノウハウが異なります。M&Aにより自社に欠けていたノウハウを取り込むことで、サービス品質の向上が期待できます。 - サービスラインナップの拡張
機械設計分野だけでなく、ソフトウエア開発やITエンジニアリング、建設技術者派遣など多角的に展開することで、顧客へ包括的なソリューションを提供しやすくなります。垂直統合的なモデルを構築する企業も増えています。 - 人材流出リスクの低減
M&Aの一つの重要な狙いは、買収企業が抱える有能な人材の確保です。通常、M&Aによって経営基盤が安定すれば、雇用の安定や研修制度の整備が進み、人材流出を防ぎやすくなると考えられます。 - スケールメリットによる競争力強化
派遣ビジネスは一定のスケールがあるほど効率がよいとされています。大手メーカーとの交渉力向上や、教育プログラム・情報システムの共通化など、大規模化によるメリットは無視できません。
4. 近年の主要事例一覧と概要
ここからは、実際のM&A事例を見ながら、機械設計業界における動向を深掘りしていきます。以下に挙げるのは、2010年代以降に行われた代表的な事例です。
- 夢真ホールディングス<2362>による三立機械設計の子会社化(2018年10月4日)
- 鴻池運輸<9025>によるエヌビーエス(NBS)の子会社化(2018年5月31日)
- ヘリオステクノホールディング<6927>による関西技研の子会社化(2013年5月10日)
- ミューチュアル<2773>による鈴木製作所の事業取得(2013年10月4日)
- ワールドホールディングス<2429>による日本技術センターの子会社化(2023年4月20日)
- コプロ・ホールディングス<7059>によるアトモスの子会社化(2021年4月27日)
- コプロ・ホールディングス<7059>によるバリューアークコンサルティングの子会社化(2021年9月14日)
- UTホールディングス<2146>によるシステム・リボルーションの子会社化(2015年3月20日)
これらの事例に共通するキーワードとして、「エンジニア派遣事業の強化」「顧客基盤の拡充」「技術力の補完」「新規分野への参入」などが挙げられます。いずれの事例も、人材や技術を効率よく獲得して企業競争力を高めることが主な目的となっているのが特徴です。
5. 各事例の詳細と戦略的背景
5-1. 夢真ホールディングス<2362>による三立機械設計の子会社化
事例概要
- 取得日: 2018年10月4日
- 取得価額: 非公表
- 三立機械設計の概要:
- 売上高: 3億6700万円
- 営業利益: 3800万円
- 純資産: 9080万円
- エンジニア数: 約40名
- 建機と液晶分野に強みを持ち、日立グループなど有力顧客を抱える
夢真ホールディングスはもともと建設技術者派遣を主力としてきましたが、近年はエンジニア派遣事業にも力を入れています。今回の三立機械設計の買収により、機械設計領域のエンジニアを獲得し、自社グループのサービスラインナップを拡充する狙いがあったと考えられます。
特に建機や液晶分野に強みを持つ三立機械設計は、大手クライアントとの取引実績を有しており、安定した収益を期待できるうえ、既存の顧客基盤を拡大する絶好の機会でもあったでしょう。夢真ホールディングスにとっては、本業である建設技術者派遣とのクロスセルや、派遣先の多様化によるリスク分散効果も大きなメリットだったと推察されます。
5-2. 鴻池運輸<9025>によるエヌビーエス(NBS)の子会社化
事例概要
- 取得日: 2018年5月31日
- 取得価額: 非公表
- エヌビーエス(NBS)の概要:
- 電気工事業を国内外で展開
- 発電所やエネルギー関連プラントのエンジニアリング事業で約30年の実績
鴻池運輸は物流・運輸事業を中心に手がける企業として知られていますが、プラント機器や設備の機械設計・据え付け工事も行っています。エヌビーエスを子会社化したことで、電気・計装設計や運転管理までを含む一貫したサービス提供が可能になりました。
この買収の意義は、鴻池運輸グループが従来持っていた機械設計や据付工事のノウハウに、NBSの電気工事領域の技術力が加わることで、ワンストップサービスを拡充できる点にあります。プラント保守や定期メンテナンスなどの需要増を背景に、総合的なエンジニアリング企業へと成長する基盤が整うことになりました。
5-3. ヘリオステクノホールディング<6927>による関西技研の子会社化
事例概要
- 取得日:
- 一部株式取得: 2013年5月10日
- 残り株式の取得(株式交換): 2013年5月31日
- 取得価額: 1億300万円
- 関西技研の概要:
- 売上高: 2億2800万円
- 営業利益: 590万円
- 純資産: 1億9100万円
- 技術者派遣・機械設計が主力事業
ヘリオステクノホールディングは、人材派遣を手がける子会社を有していましたが、長期化する経済低迷の影響で顧客ニーズが多様化し、人材ビジネスの規模拡大が急務となっていました。そこで、関西技研を傘下に取り込み、機械設計の領域での顧客満足度向上と雇用創造を同時に進める戦略を打ち出しました。
関西技研は兵庫県姫路市を拠点に機械設計技術者の派遣を展開しており、地域密着型で強みを発揮してきた企業です。ヘリオステクノホールディングにとっては、地理的な拡大と技術者派遣ノウハウの獲得という両面でのメリットが期待できました。また、既存の人材派遣サービスとのシナジーを高めることで、経営の安定化を図ったものと考えられます。
5-4. ミューチュアル<2773>による鈴木製作所の事業取得
事例概要
- 取得予定日: 2013年12月
- 取得価額: 3億5100万円
- 鈴木製作所の概要:
- 破産申立て(2013年8月)前まで、各種自動充てん機の製造・販売・メンテナンス事業を展開
- 医薬品や化粧品向けの自動充てん機分野で一定の技術力を持つ
ミューチュアルは医薬品・化粧品製造装置の分野で事業を展開しており、鈴木製作所から自動充てん機などの事業を取得することで、同社の技術と顧客を継承しました。鈴木製作所は破産申立てを行っていましたが、高収益業務の一部にはまだ事業再構築の可能性があると判断されたのです。
このM&Aは一般的な「子会社化」という形ではなく、「事業譲受」に近い形態といえます。ミューチュアルにとっては、破産企業の事業を買い取るリスクはあるものの、技術の継承や既存顧客との取引維持が可能になるという大きなメリットがありました。競合他社が入り込む前に重要な資産を手に入れることで、自社の競争優位性をさらに高める狙いがあったと考えられます。
5-5. ワールドホールディングス<2429>による日本技術センターの子会社化
事例概要
- 取得予定日: 2023年5月22日
- 取得価額: 非公表
- 日本技術センターの概要:
- 売上高: 67億7000万円
- 営業利益: 1億6300万円
- 純資産: 13億円
- 1967年設立、兵庫県姫路市を拠点
- 機械設計技術者を多数抱え、大手メーカー向け製造・技術者派遣が主力
ワールドホールディングスは製造派遣・請負事業を基幹としており、日本技術センターの子会社化によって、西日本エリアでの事業強化と顧客拡大を図ろうとしています。日本技術センターは長年にわたり大手メーカーへの派遣を中心に事業を展開しており、蓄積されたノウハウと人材育成の仕組みが大きな魅力でした。
この買収によって、ワールドホールディングスは単に派遣エンジニアの数を増やすだけでなく、エンジニアのスキルセットの幅を広げることも期待されています。特に西日本地域を中心に強固な顧客基盤を持つため、新規案件の拡大や地域密着型のサービス提供に一層力を入れられると考えられます。
5-6. コプロ・ホールディングス<7059>によるアトモスの子会社化
事例概要
- 取得日: 2021年4月30日
- 取得価額: 非公表
- アトモスの概要:
- 売上高: 8億2700万円
- 営業利益: 200万円
- 純資産: 1億8600万円
- 2006年設立、名古屋市拠点
- 大手製造業の開発・設計部門に約100人の派遣社員
コプロ・ホールディングスは建設・プラント業界向けの人材派遣・紹介事業を主力としていますが、エンジニア派遣領域の拡大を目指し、機械設計技術者派遣に強みを持つアトモスを子会社化しました。アトモスは中部地区の大手製造業に根強い取引基盤があり、機械設計技術者約100人を派遣していることが最大の強みです。
この買収により、コプロは製造業界への参入を一層強化し、建設分野に次ぐ新たな収益源を獲得できます。また、エンジニア派遣のノウハウを相互に活用することで、より広範囲かつ専門性の高い人材ビジネスを展開できるようになると期待されています。
5-7. コプロ・ホールディングス<7059>によるバリューアークコンサルティングの子会社化
事例概要
- 取得予定日: 2021年9月30日
- 取得価額: 非公表
- バリューアークコンサルティングの概要:
- 売上高: 7億5400万円
- 営業利益: 5700万円
- 純資産: 1億8600万円
- 2004年設立、東京都品川区
- フリーランスITエンジニア向け案件情報サイト「ハッピーエンジニア」を運営
- 上場企業を含む約60社の顧客企業で約90人のフリーランスITエンジニアが稼働
コプロ・ホールディングスは機械設計や建設・プラント業界の人材派遣で実績を重ねていましたが、バリューアークコンサルティングを子会社化することでIT分野へと事業領域を広げました。フリーランスITエンジニアを対象にしたプラットフォームを保有することで、多様な働き方に対応できる仕組みを手に入れたといえます。
この買収は、エンジニア派遣ビジネスをより総合的に強化する施策として位置づけられます。ITエンジニアは特に人材不足が著しい市場であるため、同社としては将来的な成長が見込める分野を取り込む狙いが大きかったと考えられます。
5-8. UTホールディングス<2146>によるシステム・リボルーションの子会社化
事例概要
- 取得日: 2015年3月27日
- 取得価額: 10億5000万円(アドバイザリー費用などを含む)
- システム・リボルーションの概要:
- 売上高: 12億2000万円
- 営業利益: 7160万円
- 純資産: 3億900万円
- 1986年設立、東京・名古屋を拠点にソフト開発・エンジニア派遣事業を展開
UTホールディングスは中核の製造派遣事業に加え、機械設計やソフトウエア開発、建設などのエンジニア派遣にも注力しています。システム・リボルーションを子会社化したことで、ソフト開発分野の顧客基盤と技術者を手に入れ、IT領域での事業拡大を図りました。
製造業とIT技術の融合が進む中で、スマートファクトリーや自動化システムへのニーズが急速に高まっています。UTホールディングスとしては、ハードウェアとソフトウェアの両面でエンジニア派遣を行える体制を整え、競合他社との差別化につなげる狙いがあります。
6. 機械設計業界でM&Aが活発化する要因
上記のような複数の事例から、機械設計業界(および関連するエンジニア派遣業界)でM&Aが活発化している要因を整理してみます。
- 人材不足の深刻化
高度化する設計技術やソフト開発を担う人材が慢性的に不足しているため、優秀なエンジニアを抱える企業の獲得は企業戦略上の最重要課題となっています。 - 技術の複雑化と高度化
設計・開発・製造の各工程が高度化・複雑化する中、1社ではカバーしきれない技術領域が増えています。M&Aによる専門企業の取り込みは、開発スピードと品質を担保するうえで有効な手段です。 - 需要拡大とリスク分散
さまざまな業界のニーズに応えるには、幅広いエンジニアを確保する必要があります。建設から機械設計、ITまで一括で提供できる体制を整えることで、不況時にもリスクを分散しやすくなります。 - 大手メーカーとの関係強化
大手メーカーは依然として国内外で大きなシェアを持ち、安定した案件を提供してくれます。大手企業と直接の取引実績を持つ派遣企業を買収することで、即座にその関係を手に入れられるというメリットが生まれます。 - 事業承継問題
中小規模の機械設計企業では、オーナー経営者の高齢化と後継者不足が深刻になっています。経営者がM&Aで大手グループに参画することは、従業員の雇用維持や企業の存続のためにも有力な手段となっているのです。
7. M&Aによるシナジー効果と課題
7-1. シナジー効果
- 技術力・人材の補完
買収した企業が持つ専門技術やエンジニアは、親会社の新たな武器となり、短期間で技術領域を拡大できます。 - 顧客基盤の拡張
お互いが持つ顧客リストを共有し、クロスセルを行うことで新たな受注を獲得しやすくなります。大手メーカーなど有力顧客との取引実績を相互に活用できる利点は非常に大きいです。 - スケールメリットとコスト削減
教育プログラム、管理システム、営業活動などを統合・共有することで、コスト効率を高められます。また、大規模な組織体制により社会的信用も高まり、大口案件への入札や新規参入がしやすくなります。 - 事業多角化によるリスク分散
建設・プラント分野と機械設計分野、さらにはIT分野など複数の事業を持つことで、一方の景気低迷を他方で補い合うことができます。親会社グループ全体の安定収益化に貢献します。
7-2. 課題
一方、M&Aには以下のような課題も存在します。
- 文化・組織統合の難しさ
異なる企業文化を持つ組織同士が統合するとき、社内ルール、評価制度、給与体系などを一体化するのは容易ではありません。従業員のモチベーション低下や離職リスクを伴う場合があります。 - 買収コストの正当化
M&Aには多額の資金が必要となります。買収価格が妥当であったか、十分なリターンを得られるかを慎重に見極める必要があります。 - 人材確保と流出防止
M&Aの狙いの一つが人材確保であるにもかかわらず、統合後に社風の違いや待遇への不満などでエンジニアが離職すると、期待したシナジーを得られなくなります。 - 事業戦略との整合性
単に勢いで買収を進めるのではなく、自社の中長期的な戦略に合致しているか、買収後の計画を明確に示す必要があります。統合後の具体的なビジョンが無いまま買収を行うと、組織混乱を招く恐れがあります。
8. 今後の展望と注意点
8-1. エンジニアリング領域のさらなる拡大
今後もAI、IoT、ロボティクス、自動運転、5G/6G通信など新技術が進化し続けることが予想されます。これらの新領域に対して、製造業だけでなくサービスや流通、建設業界なども技術的な支援を必要としています。機械設計やIT分野のエンジニア派遣需要は引き続き拡大が見込まれ、M&Aも活発に行われるでしょう。
8-2. 地方企業のM&A需要
大都市圏のみならず、地方の機械設計企業やエンジニア派遣会社に対するM&A需要も高まると考えられます。地方で優良顧客を持ち、技術力もあるが後継者不足に悩む企業は多く、大手グループの傘下に入ることで経営基盤を安定化させるケースが今後も増えるでしょう。
8-3. IT領域との融合
機械設計分野とIT領域の境界は徐々に曖昧になっています。製造現場の自動化やスマートファクトリー化が進む中、機械設計とソフトウェア設計を一体的に進める必要がある場面が増え、システムインテグレーターやITエンジニア派遣企業との連携が不可欠になります。今後はIT企業が機械設計の会社を買収したり、その逆が起こったりするケースもさらに増加すると予想されます。
8-4. グローバル化対応
海外企業との競争や海外拠点の設立も視野に入れる企業が増えています。日本国内だけでなく、アジア圏をはじめとする海外の有力企業との提携や買収が行われる可能性もあるでしょう。海外製造拠点に対する技術者派遣ニーズは根強く、グローバル化を見据えたM&Aが一段と重要視されると考えられます。
8-5. 経営者の覚悟と統合戦略の明確化
M&A後の統合成功率を高めるには、経営者の強いリーダーシップと明確な統合戦略が欠かせません。企業文化の違いや人事制度・評価体系のズレを解消するためには、時間とコストを惜しまない姿勢が求められます。大きなビジョンを共有し、両社の従業員が納得感を持って取り組めるような環境づくりが重要です。
9. まとめ
本記事では、機械設計業界におけるM&Aの動向や背景、具体的な事例、そしてシナジー効果と課題、今後の展望について詳しく解説してきました。以下に主なポイントを振り返ります。
- 背景と目的
- 機械設計技術者やITエンジニアなどの人材不足が深刻化する中で、企業はM&Aによって即戦力や専門技術を取り込む狙いがあります。
- 新技術が次々と登場する環境下で、新領域に迅速に参入し、競争優位を築くためにもM&Aは重要な経営手段となっています。
- M&A事例の特徴
- 夢真ホールディングスによる三立機械設計の買収に見るように、建設技術者派遣を主力とする企業が機械設計分野に進出するケースは増えています。
- コプロ・ホールディングスは機械設計分野だけでなく、フリーランスITエンジニアを対象とする事業にも広げるなど、サービスの多角化が進んでいます。
- 大手企業だけでなく、中小規模の技術者派遣会社や設計会社を取り込むことで、地域的な拡大や専門技術の補完を行う事例が数多く見受けられます。
- シナジー効果
- 技術力やノウハウ、人材の獲得により、企業競争力を高めることができます。
- 顧客基盤を相互利用し、クロスセルを推進することで売上拡大を狙えます。
- 大規模化によるスケールメリットとリスク分散により、経営の安定化が図れます。
- 課題と留意点
- 組織文化や人事制度の違いによる摩擦、エンジニアの流出リスクなどの統合上の課題があります。
- 買収価格の正当性や中長期的な投資リターンを見極めるために、戦略的なM&A計画が必要です。
- 統合後のビジョンを従業員や顧客に丁寧に説明し、相互理解を深めることでM&Aの成功確率を高められます。
- 今後の展望
- 少子高齢化による人材不足と技術高度化の流れは続くため、機械設計領域やIT領域でのM&Aは一層活発化すると考えられます。
- 地方企業や後継者不足の中小企業を中心に、さらなるM&Aの波が広がるでしょう。
- ITやデジタル技術と機械設計の融合が進み、新たな付加価値を生み出す企業が先行者メリットを得る可能性が高いです。
- 経営者には、ただ企業規模を拡大するだけでなく、買収先とのシナジーを的確に生み出す綿密なプランと統合プロセスが求められます。
以上のように、機械設計業界のM&Aは、多様化・高まる顧客ニーズに対応するための「即戦力獲得」「新技術・新市場への参入」「人材確保」「リスク分散」を目的として、今後も継続的に行われると見られます。企業間競争が激化する中で、各社がM&Aをどのように活用し、どんな価値を顧客や社会にもたらすのかが注目されます。
一方、M&Aは決して万能薬ではなく、事業戦略との整合性や統合後の課題解決に取り組む責任が伴います。買収によって得られるメリットと潜在的なデメリットのバランスを慎重に評価し、統合プロセスを計画的に進めることが不可欠です。
機械設計技術者派遣の市場は、製造業の活性化や新技術分野の拡大に支えられ、引き続き明るい展望が持てる領域です。しかし、そのなかでもより優れた技術力・人材を抱える企業が競争で優位に立ちやすいのは事実です。こうした背景から、M&Aは企業がダイナミックに成長し、業界全体を活性化させる大きなきっかけとなるでしょう。
本記事を通じて、読者の皆様に機械設計業界でのM&Aの全体像、主要事例やその背景、今後の方向性などをご理解いただけましたら幸いです。M&Aを検討する企業のみならず、エンジニア派遣を利用する顧客企業や、そこで働くエンジニアの皆様にとっても、M&Aの知識は自分たちのキャリアや事業選択を考えるうえで重要な要素となるかもしれません。
今後も業界の動向を注視しながら、自社や自身のスキル、キャリアを最適に活かすための選択肢としてM&Aを捉え、活用していくことが期待されます。日本のものづくりを支える機械設計業界が、M&Aを通じてどのように発展を遂げるのか、引き続きその動きに注目していきたいと思います。

株式会社M&A Do 代表取締役
M&Aシニアエキスパート・相続診断士
東京都昭島市出身。慶應義塾大学理工学部を卒業後、大手M&A仲介会社にて勤務し、その後独立。これまで製造業・工事業を中心に友好的なM&Aを支援。また父親が精密板金加工業、祖父が蕎麦屋、叔父が歯科クリニックを経営し、現在は父親の精密板金加工業にも社外取締役として従事。