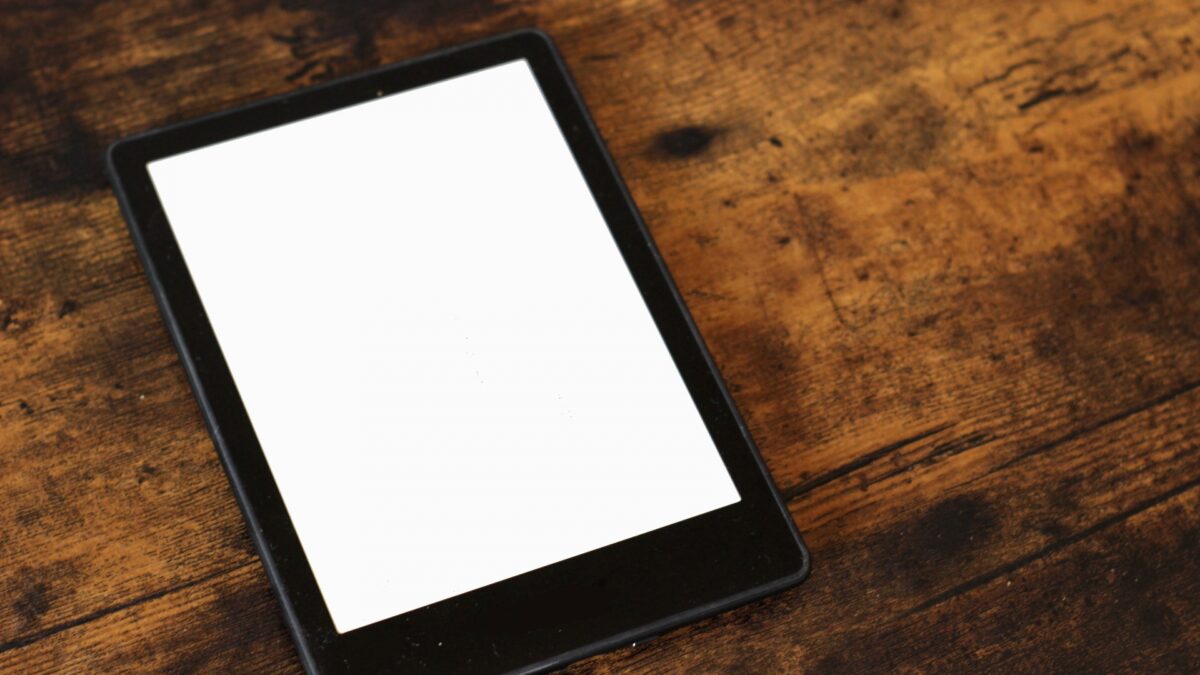- 1. 電子書籍業界の概況と成長要因
- 2. M&Aの主な目的と背景
- 3. 国内電子書籍関連M&A 主要事例の詳細解説
- 3-1. 大日本印刷による文教堂グループHDの譲渡事例
- 3-2. 船井総合研究所によるビジネス社売却事例
- 3-3. 楽天のOverDrive譲渡事例/Kobo買収事例
- 3-4. 近鉄百貨店のビッグウィル譲渡事例
- 3-5. 角川グループHDによるドワンゴ関連会社スカイスクレイパー子会社化
- 3-6. ヤフーによるイーブックイニシアティブジャパンTOB事例
- 3-7. リアルワールドによる電子書籍紹介サイト「漫画大陸」取得事例
- 3-8. 共立印刷による暁印刷子会社化
- 3-9. メディアドゥHDの一連の買収(徳島データサービス、フライヤー、出版デジタル機構など)
- 3-10. ポールトゥウィンHDによるDMM.com舞台事業譲受(周辺領域拡大)
- 3-11. ビューティガレージによる女性モード社子会社化
- 3-12. ネクスグループの実業之日本デジタル子会社化
- 3-13. ビーグリーによるノベルバ・NSSK-CC買収
- 3-14. ショーケース・ティービーによるgalaxy子会社化
- 3-15. インプレスHDのデジタルディレクターズ子会社化
- 3-16. イーブックイニシアティブジャパンのFind Japan売却・買収(中国ウェイボー関連)
- 3-17. イーブックイニシアティブジャパンのマグネット買収・ブークス子会社化
- 3-18. インテア・ホールディングスの雑誌オンライン・電子コミック事業買収
- 3-19. アプリックスIPHDの出版事業子会社3社譲渡
- 3-20. オリコン子会社のモバイル事業譲渡
- 3-21. アクセルマークのエフルート吸収合併
- 3-22. エムアップのEMTG子会社化(ファンクラブ運営と電子書籍のシナジー)
- 3-23. フォーサイドによる「Popteen」事業取得
- 3-24. INESTのZITTO子会社化(デジタルコンテンツ配信)
- 3-25. KYORITSUによる東京アド子会社化(電子書籍制作拡充)
- 3-26. INCLUSIVEとメディアドゥの提携、「マンガ図書館Z」譲受
- 3-27. INCLUSIVEのナンバーナイン子会社化(電子コミック事業拡充)
- 3-28. ACCESSの電子出版ソリューション事業をブックウォーカーへ譲渡
- 3-29. SmartEbook.comのデジタリオ子会社化
- 3-30. and factoryによる電子書籍ストア「ソク読み」事業取得
- 3-31. AmaziaによるWithLinks買収(Webtoon分野拡大)
- 4. 米国や海外における動向と事例
- 5. M&Aによるシナジーの具体的なメリット
- 6. 今後の課題と展望
- 7. まとめ
1. 電子書籍業界の概況と成長要因
1-1. 市場規模拡大の背景
日本の電子書籍市場はスマートフォンやタブレットの普及に伴い急速に成長してきました。1990年代後半から2000年代前半にかけては、いわゆる「ガラケー」向けのケータイ小説やコミック配信が注目されていた時期がありましたが、その当時はコンテンツの画質や決済手段、読みやすさの面でさまざまな制限があり、本格的な普及には至りませんでした。
その後、iPhoneやAndroidスマートフォンが普及し、タブレット端末の性能が飛躍的に向上するとともに、通信環境が充実してきたことで、いつでもどこでも快適に電子書籍を楽しめる条件が整いました。さらに出版各社も、紙媒体だけではなくデジタル配信への対応を急速に進めるようになり、国内電子書籍市場は2010年代以降、右肩上がりの成長を遂げてきました。
また、出版社やコンテンツホルダーだけでなく、IT企業や通信企業など異業種からの参入も相次いだため、市場には多様なビジネスモデルが生まれました。読み放題サービス、定額制、バナー広告付き無料コミックなど、多様なサービスが展開され、電子書籍の閲読スタイルが一層広がったのです。
1-2. 消費者行動の変化
電子書籍はスマートフォンを中心に、通勤通学時などの「スキマ時間」に手軽に楽しめる利点があり、特にライトユーザーや若年層を取り込みやすくなりました。紙の書籍を置くスペースが不要である点や、刊行のタイムラグが少ないこと、新刊の発売日に即座に手元で読めることなど、多くのメリットがユーザーに受け入れられました。
一方で、紙の書籍を好む層も依然として根強い需要を持っています。そのため、書店や取次会社は電子書籍と紙書籍をうまく併存させる形で販売を進めようと模索しています。その中で企業間の連携や協業、もしくはM&Aによる経営統合が進んでいるのです。
1-3. 出版社・取次・書店・IT企業の参入
出版社が直接電子書籍を手がけるケースだけでなく、取次や書店が独自の電子書籍プラットフォームを展開するケースも増えました。たとえば大日本印刷系の「honto」、丸善ジュンク堂や文教堂との連携などが有名です。これに加えて、IT企業による独自アプリやストアの展開も拍車をかけています。楽天の「Kobo」、Kindleを擁するAmazonの存在、ヤフーの「Yahoo!ブックストア」などが代表的です。
このような業態の垣根を越えた参入によって、業界全体が活性化し、さらに競争が激化してきました。その結果として、企業間の資本提携やM&Aが積極的に行われるようになってきたのです。
2. M&Aの主な目的と背景
2-1. 電子書籍におけるシナジー追求
電子書籍は、紙の書籍と比べると「流通コスト」「在庫リスク」「返品リスク」が圧倒的に少なく、データ配信を通じて自社のプラットフォームを強化し、さらに顧客基盤を拡大できる魅力があります。M&Aで他社を買収し、既存の電子書籍プラットフォームやコンテンツを取り込むことで、ユーザー数を一気に増やせるほか、相互送客などのシナジーを見込めます。
とりわけ出版取次会社や書店は、電子書籍への対応を強化する一方、紙の販売とネット通販を連動させることで、幅広い顧客ニーズに対応できるようになります。出版社にとっては、M&Aによる共同開発や共同販促で売上機会の拡大や新サービスの創出が期待できます。
2-2. 印刷事業とデジタル事業の融合
紙の書籍を中心に事業を展開してきた印刷会社も、近年は電子媒体やデジタルコンテンツへの対応が欠かせなくなっています。売上が紙媒体に大きく依存している場合、将来的な市場縮小リスクを回避するために、電子書籍やデジタルコンテンツの制作・流通を行う企業を買収するケースが増えています。
今回紹介する事例でも、共立印刷による暁印刷の買収や、メディアドゥグループの積極的な買収は、印刷と電子書籍の組み合わせで事業ドメインを広げようとする戦略が垣間見えます。
2-3. 経営資源の集中と事業再編
一方で、IT・デジタル事業に注力するために、既存の出版事業を譲渡したり、逆に出版事業を売却して外食事業に集中する例も見られます。たとえばヴィア・ホールディングスが暁印刷を手放し外食に集中したケースや、船井総合研究所が出版子会社ビジネス社を売却した例があります。またアプリックスIPホールディングスが出版事業子会社3社を譲渡し、IoT事業へ集中した例も同様です。
こうした事業再編の背景には「選択と集中」という経営判断があり、電子書籍事業を強化する企業がある一方で、デジタル部門を売却して自社のコア事業に資源を回す企業も少なくありません。
2-4. グローバル展開と海外企業買収
日本の電子書籍企業が海外企業を買収することで、国際展開を加速させる動きも見られます。代表的な例として楽天によるKobo買収や、メディアドゥによる米ファイアーブランド・グループ2社買収などが挙げられます。逆に海外投資ファンドに日本の電子書籍関連企業が買収されたり、合弁企業として海外市場に進出するケースもあります。
電子書籍はデジタル配信で国境を越えやすく、権利関係がクリアになれば多言語対応によって一気に巨大市場を狙うことができます。そのため、M&Aによる海外進出は魅力的な選択肢となっているのです。
3. 国内電子書籍関連M&A 主要事例の詳細解説
ここからは具体的なM&A事例を順に取り上げ、その背景やシナジー、買収側・売却側の目的などを詳しく見ていきます。多種多様な業態が混ざり合っているのが電子書籍業界の特徴であり、そこにM&Aがどのように作用しているのかを紐解くことがポイントです。
3-1. 大日本印刷による文教堂グループHDの譲渡事例
日付: 2016年9月12日
概要: 大日本印刷が連結子会社の文教堂グループHD株式の一部を、日本出版販売へ譲渡。持ち株比率を51.86%から23.74%に引き下げ、文教堂グループHDは大日本印刷の持分法適用会社となりました。
大日本印刷グループは紙媒体の印刷を中心に、ネット通販や電子書籍販売サービスを連携させた「honto事業」を展開しています。今回の譲渡は、出版流通市場における協業関係強化と市場活性化が狙いとされています。譲渡後も文教堂とは引き続き協業し、新サービスの開発などに取り組む計画でした。
本事例は、印刷会社と書店チェーン、取次業社の三者がどのように役割分担し、連携を深めるかがポイントです。電子書籍への対応が進む中、紙の書店を維持することに加え、ネット通販やデジタル配信も並行して強化していく姿勢をうかがえます。
3-2. 船井総合研究所によるビジネス社売却事例
日付: 2011年6月6日
概要: 船井総合研究所が出版子会社のビジネス社を経営陣に譲渡。メディアの多様化や電子書籍の普及によって競争が激化するとの予測から、出版事業を切り離し経営資源をコンサルティング本業へ集中。
ビジネス社は単行本を中心とする出版社でしたが、赤字を計上しており、船井総研は今後の電子化で競合がさらに厳しくなると判断しました。譲渡価額はわずか24,000円ながら、特別損失として計上し財務体質の健全化を狙ったものと思われます。ここでも「選択と集中」の経営戦略が見てとれます。
3-3. 楽天のOverDrive譲渡事例/Kobo買収事例
- Kobo買収(2011年11月9日発表)
楽天はカナダの電子書籍事業者Koboを約236億円で買収し、世界100カ国以上で電子書籍コンテンツを配信する体制を手にしました。専用端末「Kobo eReader」やアプリの多言語展開で、グローバル展開を急拡大させようとする狙いがありました。 - OverDrive譲渡(2019年12月25日発表)
一方で、楽天は2015年に米国の図書館向け電子書籍配信企業OverDriveを買収していましたが、2019年に投資会社に売却しました。主な理由としては、楽天グループとしての経営資源配分や事業ポートフォリオ最適化があったとみられます。電子書籍事業自体はKoboを通じて継続する一方、図書館配信事業は投資ファンドに譲渡し、得られた資金を他の成長事業へ振り向けるという判断を行ったのです。
このように楽天の一連の動きは、電子書籍市場での世界シェア拡大を目指しながらも、事業再編を柔軟に行う姿勢が特徴と言えます。
3-4. 近鉄百貨店のビッグウィル譲渡事例
日付: 2012年3月28日
概要: 近鉄百貨店が連結子会社ビッグウィル(書籍・CD小売、レンタル)株式の一部をジュンク堂書店へ譲渡し、所有割合を100%から14%へ大幅に低下。ビッグウィルは丸善CHIホールディングスグループの傘下に入りました。
近鉄百貨店は自社の運営する書籍売り場の充実を図るためには、電子書籍やネット通販への対応力が必要だと認識していました。一方で、丸善ジュンク堂を擁する丸善CHIグループは商品調達力や電子書籍事業のノウハウを有しており、連携することでビッグウィルの企業価値向上を狙えます。このように、百貨店グループが書籍事業を専門書店チェーンに任せ、共同で電子化やネット強化を進めるモデルは、今後も増えると考えられます。
3-5. 角川グループHDによるドワンゴ関連会社スカイスクレイパー子会社化
日付: 2013年2月28日
概要: 角川グループHDがドワンゴ子会社の広告代理業スカイスクレイパーの株式60%を取得し子会社化。
角川は当時、独自の電子書籍プラットフォーム「BOOK☆WALKER」を強化中であり、ドワンゴのネット事業ノウハウとの融合で紙とネットを結び付けた広告事業の新モデルを狙っていました。さらに角川は出版事業や映画、アニメなど多角的にコンテンツビジネスを手がけており、ドワンゴとの協業によってネット上のプロモーション力を高める戦略がうかがえます。
3-6. ヤフーによるイーブックイニシアティブジャパンTOB事例
日付: 2016年6月9日
概要: ヤフーがイーブックイニシアティブジャパンに対しTOBを実施し、買付予定数49.0%を取得して子会社化。同社の上場は維持。
ヤフーは自社の「Yahoo!ブックストア」を強化するため、コミック配信などを手がけるイーブックイニシアティブジャパンのコンテンツやシステム開発力を求めました。イーブック側もヤフーグループ入りで集客・販売チャネルが大幅に拡大するメリットがあります。買付価格にプレミアムを付与しながらも、上場を維持して両社のブランド価値を高め、シナジーを狙うやり方はソフトバンクグループらしいM&A手法と言えます。
3-7. リアルワールドによる電子書籍紹介サイト「漫画大陸」取得事例
日付: 2020年11月2日
概要: リアルワールドがプルチーノから月間約600万ページビューを持つ漫画・電子書籍紹介サイト「漫画大陸」を2億2000万円で取得。
この事例は電子書籍の“紹介サイト”という間接的な収益源を取り込む狙いが特徴的です。「漫画大陸」は読者を公式の電子書籍サイトに送客することで収益を得ています。リアルワールドは自社のWebメディア事業とのシナジーを見込み、急拡大するオンラインコンテンツ市場での集客を強化しようとしています。
3-8. 共立印刷による暁印刷子会社化
日付: 2013年3月6日
概要: 共立印刷がヴィア・ホールディングス傘下の暁印刷を8億5000万円で買収。暁印刷は文庫本や辞典類の印刷を得意とし、電子書籍媒体のデジタルコンテンツ開発も手がける。
印刷企業同士の統合に見えますが、実は電子書籍対応力が大きなカギでした。共立印刷は生産設備と暁印刷のデジタル開発力を組み合わせることで、紙から電子への一貫体制を構築できるメリットがあります。一方、ヴィアHDは外食サービス事業への集中を目指し、印刷事業を手放すという事業再編の典型例です。
3-9. メディアドゥHDの一連の買収(徳島データサービス、フライヤー、出版デジタル機構など)
メディアドゥ(メディアドゥホールディングス)は電子書籍の取次やシステム開発を主力とする企業で、2010年代後半から積極的にM&Aを行ってきました。その一例を挙げます。
- 徳島データサービスの子会社化(2018年12月)
書誌データ入力の増加を見込み、同社を取り込むことでデジタルコンテンツ創出を効率化。 - フライヤーの子会社化(2016年10月)
書籍の要約サービスを提供するスタートアップ企業。これを自社の電子書籍販売プラットフォームと連携し、読者の選書支援と新規顧客獲得を狙う。 - 出版デジタル機構の子会社化(2017年2月)
産業革新機構や主要出版社が出資し設立した大手取次。これを取り込むことで電子出版の流通網を大幅に拡充。 - 米ファイアーブランド・グループ2社買収(2020年10月合意、2021年1月取得)
北米市場におけるデジタル書誌管理や電子書籍配信の事業ノウハウを獲得。
これらのM&Aにより、メディアドゥは国内外で電子書籍取次のトップクラス企業へと成長を遂げています。
3-10. ポールトゥウィンHDによるDMM.com舞台事業譲受(周辺領域拡大)
日付: 2024年8月27日発表
概要: ポールトゥウィンHD子会社のHIKEが、DMM.comの舞台事業を会社分割で取得。「DMM STAGE」は2.5次元舞台(漫画やアニメの舞台化)を手がける。
電子書籍とは直接関係が薄いように見えますが、「漫画原作→舞台化」という2.5次元ビジネスが拡大する中、漫画・アニメなどのコンテンツ制作を幅広く手掛ける企業が舞台制作にも進出する動きが活発です。ポールトゥウィンHDはゲームやメディア領域に強く、舞台を含めたクロスメディア展開の可能性を見据えていると考えられます。
3-11. ビューティガレージによる女性モード社子会社化
日付: 2024年5月7日
概要: ビューティガレージが、美容業界専門メディアの女性モード社を子会社化。女性モード社は月刊誌「HAIRMODE」などを刊行し、電子書籍やデジタルメディアにも進出。
美容業界の物販や店舗設計を行うビューティガレージが業界専門メディアを傘下に置くことで、集客やブランド力を高める戦略です。ここでも紙媒体と電子媒体を絡めた情報発信の拡充が狙いとなっています。
3-12. ネクスグループの実業之日本デジタル子会社化
日付: 2022年2月2日
概要: ネクスグループが株式交換で電子書籍事業の実業之日本デジタルを傘下に取り込み、新規収益源の確保を図る。
ネクスグループは赤字事業の撤退を進めており、電子書籍事業を今後の主力の一つに据える狙いです。出版不況の中でも、電子書籍は一定の伸びが見込めると判断し、経営リソースをシフトさせた例です。
3-13. ビーグリーによるノベルバ・NSSK-CC買収
ビーグリーはコミック配信サービス「まんが王国」を展開する企業で、近年はM&Aによりコンテンツを増強。
- ノベルバ買収(2018年11月14日)
小説投稿サイト「ノベルバ」の運営会社を子会社化。自社コミック配信との連携で新たなIP開発を狙う。 - NSSK-CC買収(2020年9月18日)
女性向け漫画を中心に「ぶんか社」「海王社」など5社を傘下に持つNSSK-CCを約53億円で取得。紙と電子の両面でのコンテンツ強化を図る。
これら買収により、自社オリジナル作品の幅が広がり、電子書籍事業の競争力を高める動きを見せています。
3-14. ショーケース・ティービーによるgalaxy子会社化
日付: 2017年6月15日
概要: ショーケース・ティービーがオンデマンド出版事業のgalaxyを1億4000万円で買収。galaxyはAmazon PODを活用したサービスや電子書籍化などを手がける。
ショーケース・ティービーはデータマーケティングや広告関連サービスを展開しており、紙・電子書籍の制作ソリューションと組み合わせて新たな顧客開拓を狙っています。印刷から電子化までのワンストップサービスは、出版社や個人出版を目指すユーザーにとって魅力的です。
3-15. インプレスHDのデジタルディレクターズ子会社化
日付: 2008年12月18日
概要: インプレスHDは電子書籍制作のデジタルディレクターズを子会社化(株式所有割合が58.4%に上昇)。デジタルディレクターズはコミックなどの電子化を企画・制作。
インプレスHDはIT・デジタル関連の出版を多く手がけており、電子書籍関連事業の強化が急務でした。デジタルディレクターズの制作力を取り込むことで自社の電子コンテンツ拡充と品質向上を実現しようとしたものです。
3-16. イーブックイニシアティブジャパンのFind Japan売却・買収(中国ウェイボー関連)
- ウェイボーの日本総括代理事業の買収(2015年1月22日)
イーブックイニシアティブジャパンは、中国最大級SNS「微博(ウェイボー)」代理事業を手がけるFind Japanの株式56.5%を取得し子会社化。中国市場で電子書籍事業展開を目指す。 - Find Japanを売却(2017年3月10日)
しかし中国での規制強化の影響により、当初想定ほどの成果が出ず、2017年にはFind Japanを代表取締役に3000万円で譲渡。中国市場への展開を再検討することとなった。
このように海外展開の一環でM&Aを行ったものの、規制や環境変化で撤退を余儀なくされるリスクを示す例として注目されます。
3-17. イーブックイニシアティブジャパンのマグネット買収・ブークス子会社化
- マグネット買収(2015年4月27日)
クックパッド傘下のマンガ配信企業マグネット株式50.98%を取得。自社電子書籍ノウハウと合体させ、漫画家向けの制作・配信システムを強化。 - ブークス子会社化(2015年3月12日)
オンライン書店運営会社ブークスを完全子会社化。紙の書籍販売とも連携し、電子と紙を統合したプラットフォーム形成を進めた。
イーブックは電子コミックのユーザーをさらに拡大するため、紙のオンライン書店も取り込む戦略をとっています。紙と電子をシームレスに扱うことで利用者の利便性を高め、コミック需要を取り込む動きがここに表れています。
3-18. インテア・ホールディングスの雑誌オンライン・電子コミック事業買収
- 雑誌オンライン(2012年11月30日)
スマートデバイス向けアプリ累計370万ダウンロードを超える雑誌オンライン事業を買収。 - 宝島ワンダーネットの電子コミック事業(2013年4月25日)
共同運営してきた電子コミック事業を完全自社化し、本格的に電子書籍ビジネスを強化。
インテアHDはITサービス関連事業を幅広く手がけており、電子書籍も重要な収益源の一つとして位置づけ、M&Aを活用して規模拡大を図っています。
3-19. アプリックスIPHDの出版事業子会社3社譲渡
日付: 2017年2月23日
概要: 出版子会社(アプリックスIPパブリッシング、フレックスコミックス、ほるぷ出版)のうち、2社をBookLiveへ、1社をフェニックス・ホールディングスへ譲渡。IoT事業への集中を目指す。
アプリックスは元々IT・電子部品領域で強みを持っており、出版事業は非中核化していたと考えられます。電子コミックを手がけるフレックスコミックスをBookLiveに売却することで、BookLive側はコミックラインナップを強化できるメリットがあるとも言えます。
3-20. オリコン子会社のモバイル事業譲渡
日付: 2024年9月25日
概要: oricon MEが運営するモバイル事業(「オリコンミュージックストア」「よむるん」)をエムティーアイ傘下企業メディアーノに譲渡。経営資源を顧客満足度調査やニュース配信に集中。
「よむるん」は電子書籍サイトであり、音楽配信と合わせて運営されていましたが、オリコンはデジタル音楽配信や書籍事業よりも、CS調査やニュース配信を中核とする方針へかじを切った形です。エムティーアイ側は電子書籍や音楽配信でのシナジーを見込んでいるものと推察されます。
3-21. アクセルマークのエフルート吸収合併
日付: 2011年6月16日
概要: アクセルマークが携帯電話検索ポータルを運営するエフルートを吸収合併。ソーシャルアプリや電子書籍を含めた新市場への進出強化。
携帯ポータルを取り込むことで集客を拡大し、ソーシャルゲームや電子コンテンツ配信を一体的に運営する戦略です。ガラケーからスマートフォンへの移行期において、ポータルサイトのユーザー基盤は大きなアセットとなりました。
3-22. エムアップのEMTG子会社化(ファンクラブ運営と電子書籍のシナジー)
日付: 2018年5月15日
概要: エムアップがファンクラブや電子チケット事業を行うEMTGを子会社化。エムアップはファンクラブ運営やデジタルコンテンツ配信を展開しており、電子書籍との親和性も高い。
アーティストファンクラブと音楽配信、電子書籍などエンタメ系コンテンツを総合的に扱うことで、クロスセルや顧客接点の拡大を目指しています。ファンビジネスは継続課金や関連グッズ販売なども見込めるため、電子コミックや書籍販売との相乗効果が期待できます。
3-23. フォーサイドによる「Popteen」事業取得
日付: 2021年6月25日
概要: フォーサイド子会社のモビぶっくが角川春樹事務所から女子中高生向けファッション誌「Popteen」事業を取得。電子書籍配信やSNSを通じた集客を強化。
フォーサイドは既に小中学生向けファッション誌「Cuugal」を展開しており、読者層を広げるため「Popteen」と連動させる考えです。紙媒体と電子版を組み合わせたクロスメディア展開やモデルマネジメントでも収益を狙います。
3-24. INESTのZITTO子会社化(デジタルコンテンツ配信)
日付: 2023年9月14日
概要: INESTが光通信系のZITTO(デジタルコンテンツ配信)に約10億円を出資し、68.6%の株式を取得して子会社化。アフィリエイトマーケティングなどでシナジーを期待。
INESTは通信サービスやカスタマーサポート等を行うグループで、ZITTOが持つ電子書籍・映画・音楽配信のノウハウを組み合わせ、安定した収益源を形成しようとしています。
3-25. KYORITSUによる東京アド子会社化(電子書籍制作拡充)
日付: 2024年10月1日
概要: KYORITSUが広告代理店の東京アドを子会社化。印刷やデジタル制作物のDX推進、電子書籍データ制作の強化を狙う。
広告代理店を傘下にすることでメディアバイイング力やデジタルマーケティングのノウハウを取り込み、出版物のデジタル化・販売促進につなげる考えです。
3-26. INCLUSIVEとメディアドゥの提携、「マンガ図書館Z」譲受
日付: 2023年3月27日
概要: INCLUSIVEグループのナンバーナインがメディアドゥ傘下のJコミックテラスを子会社化し、「マンガ図書館Z」を取得。無料公開+広告モデルで旧作漫画の収益化を図る。
ナンバーナインは漫画家支援や電子書籍配信事業を展開しており、広告収入を作者に還元する仕組みの「マンガ図書館Z」を取り込むことで、クリエイターエコノミー拡大に取り組んでいます。
3-27. INCLUSIVEのナンバーナイン子会社化(電子コミック事業拡充)
日付: 2021年12月9日
概要: INCLUSIVEがナンバーナイン株式の76%を取得。漫画家の電子書籍配信サポートや確定申告代行など、幅広いサービスを展開するナンバーナインを傘下に置き、クリエイターエコノミー領域を強化。
紙・電子の壁を超え、漫画家・イラストレーターを手厚く支援するビジネスモデルが注目されています。INCLUSIVEはメディア運営ノウハウを活かし、漫画家とのエージェント機能をさらに拡充する意図と見られます。
3-28. ACCESSの電子出版ソリューション事業をブックウォーカーへ譲渡
日付: 2023年11月29日
概要: ACCESSはIoT事業に集中するため、電子書籍関連ソリューションをKADOKAWAグループのブックウォーカーに売却。
ブックウォーカーはKADOKAWAの電子書籍部門を担っており、同事業を取得することで開発リソースや技術を拡充し、電子書籍ストアの機能強化につなげる狙いです。ACCESSは本来の主力事業である通信ソフトウェアやIoT分野に特化するため、非中核事業を手放しました。
3-29. SmartEbook.comのデジタリオ子会社化
日付: 2014年11月28日
概要: IT技術者派遣やWifi整備を手がけるデジタリオを2億5500万円で買収。電子書籍クラウドサービスの利便性向上と事業多角化を狙う。
SmartEbook.comは電子書籍配信サービスを運営していましたが、それに付随する通信環境や技術サポートを強化し、ユーザー体験を向上させる意味合いがあります。また複数事業を展開してリスク分散を図る狙いもありました。
3-30. and factoryによる電子書籍ストア「ソク読み」事業取得
日付: 2024年8月14日
概要: スマホアプリ事業を展開するand factoryが、共同印刷傘下のデジタルカタパルトが運営する電子書籍ストア「ソク読み」を取得。60万点の作品を配信する事業基盤を取り込み、海外展開も視野。
and factoryはスマートフォン向けマンガアプリを展開しており、「ソク読み」の顧客基盤を合体することで電子コミック事業のシェア拡大を目指しています。共同印刷は印刷事業がメインであり、電子書籍ストア運営は子会社に任せる形でしたが、戦略的に譲渡することで資本回収を図ったと見られます。
3-31. AmaziaによるWithLinks買収(Webtoon分野拡大)
日付: 2024年3月26日
概要: AmaziaがWebtoon制作のWithLinksを3000万円で買収し、90.9%の株式を取得。Webtoonは縦スクロール形式のスマホ最適化コミックであり、Amaziaの成長エンジンとして重要。
Amaziaは国内電子コミックアプリ「マンガBANG!」などを運営しており、Webtoonの拡大は不可欠な戦略です。WithLinksの制作ノウハウを取り込むことでオリジナル作品を強化し、差別化を図ろうとしています。
4. 米国や海外における動向と事例
4-1. ZoomによるFive9買収
2021年7月の事例ですが、Zoomがクラウドコンタクトセンターを提供するFive9を約149億ドルで買収発表した件は、米国IT業界の大規模M&Aとして話題になりました。直接電子書籍とは関係しないものの、DXが一気に進む中で、クラウドサービス同士の統合が進んでいる流れを示す例と言えます。カスタマーサポートの充実やオンライン会議システムとの連携など、顧客との接触を高度化する技術が注目されています。
4-2. VisaによるCurrencycloud買収
同じく2021年7月、Visaが為替・決済APIを提供するCurrencycloudを約9億6300万ドルで買収すると発表しました。電子書籍販売やデジタルコンテンツのグローバル決済を円滑にするプラットフォームとして、類似の決済サービスが注目されており、出版業界やコンテンツビジネスもグローバル展開時にこうしたFinTechサービスを活用する可能性があります。
4-3. BYJUによるEpic買収
インド最大手のオンライン学習サービスBYJUが、米国の子供向け電子書籍図書館Epicを約5億ドルで買収。学習向け電子書籍プラットフォームはコロナ禍のリモート授業需要で一気に伸びた分野の一つです。教育分野の電子書籍は定期購読モデルや学習管理システムとの連携が重要であり、企業価値が高く評価されるケースが増えています。
4-4. 電子書籍業界における北米や欧州企業の動向
米国ではAmazonのKindleが圧倒的シェアを持っていますが、Barnes & Nobleの「Nook」やRakuten Koboなどの競合も存在します。欧州市場もTolino(ドイツ)やその他端末・プラットフォームが並び立ち、各社がM&Aを通じてシェア拡大や新技術の獲得を目指す動きがあります。
5. M&Aによるシナジーの具体的なメリット
5-1. コンテンツ拡充とプラットフォームの強化
買収先のコンテンツ(コミック・書籍・雑誌など)や著作権、あるいはユーザー基盤を取得できるため、短期間で自社サービスのラインナップを大幅に増やせます。既存ユーザーへのクロスセルが容易になるほか、新規ユーザー獲得にも効果的です。
5-2. 技術・人材獲得
電子書籍関連の開発力や運営ノウハウを持つ企業を買収することで、自社のサービス開発に役立つ技術や人材を一括して取り込むことができます。大手印刷会社がデジタルコンテンツ制作会社を買収するケースなどは、紙から電子へ知見を広げる絶好の機会となります。
5-3. 海外市場への進出と国際展開
海外企業を買収・提携することで、その国の規制や流通チャネル、マーケティングノウハウをすばやく活用できるようになります。電子書籍事業はデジタル配信ゆえに国境を越えやすいですが、現地での決済や著作権管理などハードルがあるため、M&Aを通じたショートカットが有効です。
5-4. 経営効率化と事業領域拡大
書籍取次や電子取次を束ねることで在庫・物流コストを削減したり、出版社や印刷会社同士が協力して生産効率を上げる例も見られます。デジタル化により紙の返品リスクが減る一方、紙と電子のハイブリッド販売を仕組み化することでユーザーの利便性を高める動きが進んでいます。
6. 今後の課題と展望
6-1. デジタル著作権やプラットフォーム競争
電子書籍は著作権管理が難しい側面があり、海賊版サイトや違法アップロードとの戦いが続いています。大手プラットフォーム同士の競争も激化し、Amazon・楽天・ヤフーなどの巨大IT企業がマーケットシェアを握る傾向があります。中堅・中小の電子書籍プラットフォームは差別化が不可欠であり、M&Aで規模を確保する動きは今後も続くでしょう。
6-2. 電子書籍と紙書籍の相互補完
紙書籍市場が縮小する中で、電子書籍がさらに存在感を増す一方、紙には根強いファンがいます。特に写真集や大型書籍、学術書など紙の存在意義が高いジャンルは残り続けるでしょう。新刊発売時に「紙+電子セット販売」や、購入者に電子版を割引提供するサービスが広まる可能性があります。そのためには取次や書店と電子プラットフォームが協業しやすい体制づくりが欠かせません。
6-3. Webtoonや音声コンテンツなど新分野の可能性
スマートフォンで読みやすい縦スクロール漫画(Webtoon)はアジアや北米を中心に爆発的に伸びています。日本国内でも出版社やプラットフォームがこぞってWebtoon制作に乗り出し、関連スタジオを買収する動きが見られます。また、オーディオブックや音声配信(ポッドキャスト)との融合など、新しいコンテンツ形態が次々と登場しています。これらの新領域を取り込むM&Aも増えていくでしょう。
6-4. さらなる業界再編とM&Aの加速
出版不況や少子化の影響を受け、書籍市場全体の縮小が懸念されています。一方で、デジタル分野は成長が続いており、同時に競争も激化しています。その結果、大手出版社やIT企業の寡占化が進む可能性があり、中小企業は連携か、より大きなグループに参加するかの選択を迫られるでしょう。M&Aは今後ますます業界再編のカギとなりそうです。
7. まとめ
本記事では、国内外で行われてきた電子書籍業界のM&A事例を幅広く取り上げ、その背景や企業間シナジー、経営戦略を詳しく解説してまいりました。主なポイントを振り返ります。
- 市場背景
スマートフォン・タブレットの普及とともに、日本の電子書籍市場は拡大し続けています。紙書籍の売上減少を補う形で、出版社・印刷会社・IT企業など多業種のプレイヤーが参入・再編を進めています。 - M&Aの動機
- 電子書籍事業を強化したい企業が、関連企業を買収してコンテンツ・ユーザー基盤を獲得するケース
- 非中核事業となった出版部門や電子書籍部門を売却し、本業に集中するケース
- 海外の電子書籍・デジタルソリューション企業を買収し、国際展開や技術獲得を目指すケース
- 事例の多様性
印刷会社による電子書籍企業買収、書店や取次会社の株式譲渡、大手IT企業が専門企業を取り込むケース、出版社同士の統合など、さまざまな形態があります。さらに、コンテンツ制作スタジオ(Webtoon、舞台化)、紹介サイトの買収など、電子書籍の周辺領域にもM&Aは広がっています。 - 今後の展望
電子書籍は紙書籍と並行しながらも、技術の進歩や国際的な競争環境の変化によってさらなる拡大が期待されています。一方で、著作権管理やプラットフォーム競争の激化など課題も多いため、業界再編は引き続き活発化する見込みです。M&Aを通じて生き残りや競争優位を確立する動きは今後さらに加速していくでしょう。
電子書籍業界のM&Aは、企業の成長戦略や事業再編を象徴する重要なテーマとなっています。デジタルコンテンツは国境を越えて配信できる魅力があり、それに伴うライセンス交渉やマーケティング、技術的課題の解決が必要となるため、単独での拡大には限界があります。そこでM&Aや戦略提携によって一気に経営資源を取り込み、変化の激しい市場の中で先行者優位を確保することが重要になっているのです。
また、昨今では紙書籍・電子書籍の垣根を超え、「リアルとデジタルをどう融合させるか」が大きなテーマです。紙書店はリアルの接客や立ち読み体験を提供しつつ、電子書籍に繋ぐプラットフォームを整備することで新たな顧客満足を生み出す可能性があります。さらに漫画原作の舞台化やアニメ化、ゲームとのコラボなど、多彩なメディアミックスの広がりが市場を賑わせており、これら周辺ビジネスへの参入・拡大を目的としたM&Aも増えています。
デジタル技術の進化は早く、読み放題サービスや定額サブスクリプション、スマホ縦読みのWebtoon、さらにはAI生成コンテンツなど、これからも新たな波が来ることは確実です。企業がそうした新トレンドに対応し、市場をリードするには、積極的なM&A戦略とアライアンスが不可欠と言えるでしょう。とりわけ海外市場への展開には、グローバル企業を買収したり、逆に海外ファンドと提携して資金調達するなど多角的な手段が考えられます。
今後も電子書籍市場は多方面から注目され、新しいプレーヤーが参入することで競争が激しくなるでしょう。その中で勝ち残るためには、どれだけ多様なコンテンツを確保し、質の高いユーザー体験を提供できるかがカギとなります。M&Aは、そのための最も効率的かつスピーディーな手法の一つです。企業トップはビジョンを明確にしながら、買収や統合後のシナジーを的確に実現できるかどうかが成否を分けるでしょう。
電子書籍ビジネスは単なる書籍デジタル化にとどまらず、広義のデジタルコンテンツ(漫画・雑誌・小説・音声書籍・動画連動など)へと拡張しやすいため、企業のイノベーションを後押しする大きな可能性を秘めています。技術革新とユーザー嗜好の変化が激しい時代にあっては、M&Aを含む「動的な経営」が不可欠になってきたと言えるでしょう。これからも数々のニュースが報じられると考えられる電子書籍業界のM&A動向から、目が離せません。

株式会社M&A Do 代表取締役
M&Aシニアエキスパート・相続診断士
東京都昭島市出身。慶應義塾大学理工学部を卒業後、大手M&A仲介会社にて勤務し、その後独立。これまで製造業・工事業を中心に友好的なM&Aを支援。また父親が精密板金加工業、祖父が蕎麦屋、叔父が歯科クリニックを経営し、現在は父親の精密板金加工業にも社外取締役として従事。