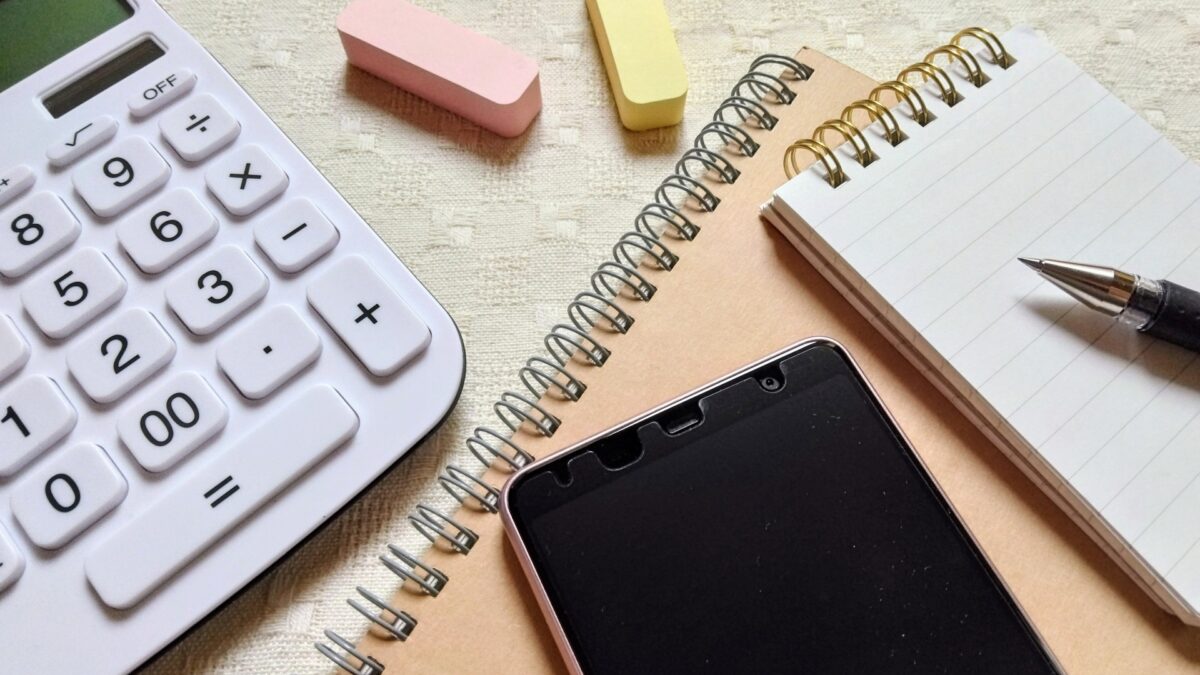- 第1章:比較サイト・メディア業界の概要とM&Aの位置づけ
- 第2章:比較サイト・メディア業界のM&Aにおける主な目的
- 第3章:比較サイト・メディア業界におけるM&A事例の考察
- 第4章:事業売却・事業譲渡としての比較サイト運営
- 第5章:比較サイト・メディア業界の特徴的なシナジーとリスク
- 第6章:M&A後の統合施策とポイント
- 第7章:比較サイト・メディア業界M&Aの近年の潮流
- 第8章:主なプレイヤーの動向
- 第9章:今後の展望と戦略
- 第10章:まとめ
- 終わりに
第1章:比較サイト・メディア業界の概要とM&Aの位置づけ
1-1. 比較サイト・メディア業界とは
比較サイト・メディア業界とは、消費者がインターネット上で商品やサービスを「比較検討」できるように情報を整理し、掲載、提供するウェブサイト・アプリケーションを運営する事業者群を指します。具体例としては、以下のようなものが挙げられます。
- 旅行予約の比較(航空券や宿泊施設の料金比較サイトなど)
- クレジットカードや保険など金融商品の比較
- 引っ越し、リフォーム、外壁塗装など生活サービス比較
- 各種体験やエンタメ系の比較
- 不動産比較、住宅ローン比較 など
これらのサイト・メディアは、消費者が複数の選択肢を一括で検討する際に役立ち、その利便性から高いトラフィック(アクセス数)を集めることがあります。そして、比較検討という行為は購買行動に直結しやすく、掲載企業や広告主から見れば、自社の商品・サービスの露出を高め、見込み客を獲得するうえで有力な集客チャネルとなります。
さらに、比較サイト・メディアでは、ユーザーからの問い合わせや資料請求、会員登録などの「リード獲得」を成果報酬型で受けるビジネスモデルが一般的です。そのため、広告収入が主体のサイト運営の中でも、比較的収益の予測が立てやすいという特徴があります。ただし、近年は同業他社の増加や、多様な広告媒体の台頭などにより、競合が激化してきているのも事実です。
1-2. M&Aが盛んに行われる背景
比較サイト・メディア業界では、新規参入が比較的容易である一方、ユーザー集客力(SEO対策やSNS広告運用など)を高めるためにはまとまった資金力が求められます。また、同業界はネットマーケティングやシステム開発に加え、ユーザー獲得・顧客管理・コンテンツ運用など多岐にわたる専門スキルが必要とされるため、業務効率化や事業拡張のスピードを加速するうえで、M&Aという手法が選択されることが少なくありません。
また、自社領域だけでなく、周辺領域(リフォーム・美容・医療など)へ迅速に展開したいというときにも、比較サイトやメディアをすでに運営している企業を買収し、一気に顧客基盤や運営ノウハウを獲得することは有効な戦略となります。さらに、広告やシステム開発、予約システムなどと相互補完できる企業同士が組むことでシナジーを狙うケースも多く見られます。
第2章:比較サイト・メディア業界のM&Aにおける主な目的
2-1. 顧客基盤や会員基盤の拡大
比較サイトのビジネスモデルは、ユーザーが何らかの商品やサービスを比較検討して最終的に問い合わせや購入、資料請求などのアクションを起こすと、サイト運営会社に成果報酬が入る仕組みが一般的です。したがって、ユーザー数や会員数が多いほど収益機会が拡大するため、「既に一定数のユーザー基盤を持つサイト」や「強力なブランド力を備えたメディア」を取り込めるM&Aは大変魅力的です。
実際の事例として、旅行商品の比較サイトを運営していた企業が、同じ旅行分野のオンライン販売会社を買収して事業領域を拡大し、一気に予約システムを強化するといった動きがあります。これにより、ユーザーは比較だけでなく、そのまま予約まで完結できるサービスへと進化し、利便性が向上します。
2-2. 新規領域への参入・コンテンツ強化
比較サイトは、例えば「クレジットカード比較」から「保険比較」に横展開するなど、他の金融商品やサービスカテゴリーに参入していくのが一般的です。しかし、全て自前で立ち上げるとなると専門知識やノウハウをゼロから蓄積しなければならず、時間とコストがかかります。そこで、すでに市場での実績やノウハウ、顧客基盤を持つ企業をM&Aすることで、一気に新規領域の獲得やコンテンツ強化を図る動きが盛んになっています。
2-3. システム開発力・技術力の取得
比較サイト・メディア運営には、検索エンジンのアルゴリズム対応、UI/UXの改善、広告配信など多面的な技術が必要です。高度なシステムを短期間で確立しようとすると、エンジニアを自社で大量採用し育成するよりも、優れた技術者集団を抱える企業を買収してしまう方が効率的だと判断される場合があります。そのため、技術力や特定のプラットフォームを持つ企業へのM&Aも増えてきました。
2-4. 競合との統合や事業整理
比較サイト・メディア業界は、その性質上、ある程度のスケールメリットが収益に大きく影響する一方で、激しい競争にさらされています。近年は広告費の高騰、集客チャネルの複雑化などにより、利益率が圧迫されがちです。そのため、競合同士で統合しスケールを確保したり、不採算事業を売却することで本業に集中する例も増えています。
第3章:比較サイト・メディア業界におけるM&A事例の考察
ここからは、具体的なM&A事例をもとに業界動向や企業の狙いを考察していきます。提供された事例や、それに類似する動きを背景として解説いたします。
3-1. 旅行関連比較サイトの事例
比較.com<2477>、住友商事<8053>の海外旅行オンライン販売子会社を取得(2008年)
比較サイト企業として上場していた比較.comは、総合商社の住友商事が100%出資していたグローバルトラベルオンラインを買収し、子会社化しました。グローバルトラベルオンラインは、当時日本国内で初めてダイナミックパッケージ(交通手段と宿泊施設を自由に組み合わせる形態)をオンラインで販売するビジネスを展開していたのが特徴です。
このM&Aの目的としては、比較.comが運営する「総合比較サイト」との連動によって、いわゆる「比較→予約→決済」のワンストップ化を実現し、旅行領域の価値を高める狙いがありました。取得価額は約2億6600万円で、当時としては比較的リーズナブルな投資額ですが、予約システムと在庫連動をリアルタイムで実装していた技術的優位性を取り込むことで、比較サイトの利便性を大きくアップさせる意味合いがあったと推測されます。
比較.com<2477>、国内宿泊予約サービス事業をマイナビに売却(2013年)
一方で、同じ比較.comが予約ドットコムの国内宿泊予約サービス事業をマイナビに譲渡した事例です。こちらは、事業の選択と集中の側面が強いM&Aと言えます。比較.com側は事業戦略の見直しに伴い、「インターネット広告事業やアプリケーションサービス事業」に重点を置く方針へ転換したため、不採算または経営資源を集中すべきでない事業と判断された国内宿泊予約サービスを切り離しました。結果として、売却価額は3500万円という比較的コンパクトな取引でした。
これらの事例から、比較サイト事業者は一貫して旅行分野を重視してきたものの、オンライン旅行販売の高度化や周辺領域の取り込みのために事業を拡充するケース、逆に不要と判断した領域を早期に切り離すケースの両面が存在することがわかります。いわゆる「投資→成長→収益化→再投資or売却」という一連の流れを機動的に行うのが、比較サイト・メディア業界の特徴の一つと言えるでしょう。
3-2. 予約サービスや周辺事業の取得・譲渡の事例
比較.com<2477>、プレコのホテル予約サイト事業を取得(2009年)
こちらも比較.comがらみの事例です。完全子会社となったグローバルトラベルオンラインを通じ、国内ホテル予約事業を手がけるプレコからホテル予約サイト事業を取得しました。プレコは老舗とも言えるオンライン予約システムを1996年から開発・導入しており、ビジネスホテル予約のコールセンター事業も展開していた点が大きな魅力でした。オンライン+オフライン両方のチャンネルを強化するという意味で、比較.comにとってシナジーが高い案件だったと推測されます。
なお、比較.comのように、M&Aを通じて旅行や宿泊予約サービスの集客や予約機能を強化する流れは、同業他社にも共通して見られます。旅行サイトはユーザーが比較検討した上で予約に至ることが多いため、比較サイトと予約サイトの連動は売り上げに直結しやすいからです。
3-3. メディア分野の周辺領域・広告プラットフォームとの連携
電通<4324>、広告配信プラットフォームのVOYAGE GROUPを子会社化(2018年)
電通は大手広告代理店として知られていますが、インターネット広告事業を加速させるため、VOYAGE GROUPを子会社化しました。VOYAGEは広告配信プラットフォームやポイントサイトなど、デジタルメディアでの集客を得意としていました。比較サイト業界やリスティング広告、アフィリエイト広告などと連動しやすい領域を多く抱えている企業を取り込むことによって、電通にとってデジタルマーケティング強化という目的があったと推測されます。
比較サイト・メディア運営においては、広告収益や集客効果をどのように高めるかが大きな鍵です。そのため、広告配信プラットフォームとの連携や、ポイントを使ったユーザー誘導を得意とする企業とのシナジーが期待できるM&Aが、今後も増えていく可能性があります。
3-4. 選択と集中やMBOによる経営方針の転換
比較.com<2477>、遺伝子検査キット販売の子会社をMBOにより譲渡(2010年)
比較.comは、遺伝子検査キットを扱うヒメナ・アンド・カンパニーをMBO(マネジメント・バイアウト)の形で経営陣に譲渡しました。比較サイト・メディア事業者がなぜ遺伝子検査キット?と不思議に思われるかもしれませんが、当時はヘルスケア関連の個人向け検査サービスが注目され始めていた時期でもあり、新規事業として展開を模索していたと考えられます。しかし、結局は事業シナジーが思ったほど得られなかったか、あるいは経営リソースの分散を避けるために売却に至ったと推測できます。
ベンチャーリパブリック<2177>、MBOにより非公開化(2012年)
ベンチャーリパブリックは価格比較・商品検索サイトを運営していましたが、急激な競合環境の変化や大手検索エンジン企業の参入などを背景に、抜本的な経営戦略を打つためにMBOを実施し、上場を廃止しました。上場企業であると短期的な利益確保や四半期ごとの開示負担が避けられず、経営判断が制約されることもあります。比較サイトのように変化が早い分野では、非公開化して機動的な戦略を進める選択をするケースもあるのです。
3-5. 他業種連携による比較サイト・メディアの可能性
じげん<3679>やマーケットエンタープライズ<3135>など多様な比較サイト取得事例
近年は、じげんやマーケットエンタープライズといったIT企業が、リフォーム比較サイトや修理比較サイト、買取比較サイトなど、さまざまな比較サイトを相次いで買収・取得しています。これは、「既存事業の集客ノウハウを新領域に横展開する」「アフター市場やリユース市場を取り込み、ライフスタイル全般を網羅する」といった狙いがあります。
たとえば、じげんはリフォーム比較サイト「リショップナビ」や、外壁塗装比較メディア、さらには航空券比較サイトなどを次々に取得しており、複数の比較プラットフォームを一括で運営することで、ユーザーにとっては「じげんの比較サイト群=多様なジャンルを網羅する総合的プラットフォーム」として認知を広げる施策を展開しています。
同様に、マーケットエンタープライズも「高く売れるドットコム」を中心としたリユース事業を強化するために、買取比較サイト「おいくら」や修理業者比較の「最安修理ドットコム」など、周辺の比較サイトを取得しています。こうすることで、ユーザーが「買う・売る・修理する」といった一連の行動を同社グループ内で完結できるようになり、顧客ロイヤルティ向上やクロスセル(関連サービスの利用促進)を狙えます。
このように、比較サイト運営同士でのM&Aのみならず、別種のウェブサービスを展開する企業による比較サイト買収も頻繁に見られるようになりました。背景としては、単一カテゴリーのみでは市場規模や成長余地に限界があるため、複数のカテゴリを束ねる「プラットフォーマー」として飛躍しようという企業が増えたことが大きいと考えられます。
第4章:事業売却・事業譲渡としての比較サイト運営
4-1. 比較サイトを手放す理由
比較サイト・メディアは、運営次第で大きく成長する可能性を秘めていますが、流行の変化や競合の増加によって収益が伸び悩む場合もあります。また、広告費やSEO施策などの投資コストがかさみ、黒字化が難しくなるケースもあります。運営元が自身のコア事業に集中するため、集客力の強い比較サイトを他社に売却することでキャッシュを得る事例も珍しくありません。
さらに、保険業界をはじめとする規制の影響も大きい分野では、比較サイトやマッチングサイトが「募集行為」にあたり、法律上の資格や新たな手続きを整えなければならない場合があります。その体制づくりを断念して事業を譲渡する例も見受けられます。
4-2. 譲渡先が得られるメリット
買い手側の企業には「自社のポートフォリオに不足しているカテゴリを手軽に増やせる」「ノウハウやユーザーデータを即時に取り込める」といったメリットがあります。比較サイトはユーザーが購買を前提としてサイトを訪れることが多く、リード獲得や収益化を図りやすいジャンルです。また、SEO観点でも比較サイトは検索需要が高いキーワードを多く狙える傾向があるため、買収後の流入拡大を見込むことができます。
第5章:比較サイト・メディア業界の特徴的なシナジーとリスク
5-1. シナジーの種類
- 集客シナジー
複数の比較サイトを運営することで、ユーザー相互送客や、サイト間の広告・クーポン連携などが可能になります。たとえば、引っ越し業者比較サイトと不動産検索サイトが連動すれば、物件を探す段階から引っ越し手配までをスムーズに繋げられます。 - 営業シナジー
同一の広告主や加盟店に対して、複数の比較サイトでまとめて提案できるようになることで、営業効率が高まるとともに、クロスセルやアップセルによる収益増が狙えます。 - 技術シナジー
予約システムや在庫管理システムを複数のサイトで共通利用することでコスト削減ができたり、顧客データを一括管理することによって分析精度を上げたりできます。特にクラウド技術やAI技術と連動したレコメンドエンジンは、サイト単体では投資が難しい部分をグループ全体で活用する余地があります。
5-2. 比較サイト特有のリスク
- 広告費の高騰
検索連動型広告やディスプレイ広告の単価が年々上昇しており、集客コストの増大が利益を圧迫する可能性があります。特にリスティング広告への依存が大きい比較サイトはこの影響を受けやすいです。 - コンプライアンスや法規制
保険比較サイトでは保険業法、金融商品比較サイトでは金融商品取引法など、業種によって厳しい規制が存在します。旅館業法や旅行業法、景品表示法など、関連する法律が多岐にわたり、常に法改正への対応が求められます。 - 競合激化
大手検索エンジンや大手ECサイトが自社サービスで比較機能を導入すると、ユーザーがわざわざ比較サイトを訪れなくなる恐れがあります。GoogleやYahoo!、楽天やAmazonなど巨大プラットフォームの動向は無視できません。
第6章:M&A後の統合施策とポイント
M&Aで企業や事業を取得した後、統合を円滑に進められるかどうかが成果を左右します。以下は主な統合のポイントです。
6-1. ブランド統合・サイト統合
「比較サイトA」と「比較サイトB」の両方を独立して運営するか、もしくは一つに統合するかの判断は非常に重要です。それぞれに認知度がある場合は残すべきかもしれませんが、運営コストやSEO効果を考えると統合が有効なケースもあります。機能やコンテンツの重複を整理し、ユーザービリティ(使いやすさ)を高めることが、集客力向上につながります。
6-2. システム連携とデータベース統合
比較サイトにおけるシステム連携は、商品情報やクチコミ情報、顧客データなど多岐にわたります。M&A直後は、買収先企業のシステムと自社システムを並行稼働させるケースが多いですが、重複する作業やシステム維持コストが増大しやすいため、早い段階で統合に向けたロードマップを策定し、業務効率化を図る必要があります。
6-3. 組織文化の違いへの対応
比較サイト運営企業の中には、少数精鋭のベンチャー気質を持つところが多い一方、大手企業はルールやプロセスが整備されていることが多いです。M&Aによって両者が一緒に働くと、意思決定のスピード感やワークフローなどでギャップが生じがちです。したがって、経営トップの明確な方針や文化の擦り合わせが重要になります。特にIT・ウェブ業界はスピード感が重要なため、M&A後の組織体制整備は入念な計画をもって行う必要があります。
第7章:比較サイト・メディア業界M&Aの近年の潮流
7-1. 新型コロナウイルス感染拡大の影響
新型コロナウイルス感染症の流行は、比較サイト業界にも大きな影響を与えました。旅行や外食・アクティビティなど、リアルの消費行動が制限されたカテゴリーの比較サイトは一時的にアクセスが激減し、広告売上が低迷しました。一方で、在宅勤務やオンライン化が進むことで、通信関連サービスやクラウドサービスの比較サイトには追い風となるケースもありました。
こうした波があったため、M&Aの方針を転換し、事業の一部を切り離す企業や、成長カテゴリーを強化するために新規取得を行う企業が見られました。たとえば、外食系の予約サイトを持つ企業が飲食店向けのシステムを扱う企業を買収するなど、関連サービスを押さえる動きも加速しています。
7-2. 大手プラットフォーム企業との競合と協業
Googleが「Google Flights」や「Google Hotels」といった旅行情報検索を開始したように、大手プラットフォーム企業が比較サービス領域に参入する動きは増えています。これは比較サイト運営企業にとっては脅威でもあり、連携相手でもあります。大手プラットフォームは圧倒的なユーザー数とトラフィックを持つため、うまくAPI連携などを行うことでさらなる集客が期待できるケースもあるため、今後は提携か対抗かという複雑な選択を迫られるでしょう。
7-3. 海外展開とインバウンド需要
日本国内の比較サイト市場は成熟しつつあるため、海外の比較サイト事業者との連携や買収による海外展開も視野に入っています。特にインバウンド需要や越境ECなどが盛り上がる中で、旅行比較サイトやショッピング比較サイトが海外展開するケースが増えています。現地企業とのM&Aによって、その国や地域のユーザー基盤を獲得し、文化的・言語的な壁を乗り越える狙いがあります。
第8章:主なプレイヤーの動向
8-1. じげん<3679>の積極的M&A戦略
「求人×比較サイト」から事業をスタートしたじげんは、近年はリフォーム、不動産、引っ越し、外壁塗装、留学、フランチャイズなど、多岐にわたる比較サイトを買収しており、総合比較メディアカンパニーへと進化を遂げています。同社はユーザーのライフイベントやビジネスニーズに応じて、複数の比較プラットフォームを提供できる体制を作り、事業ポートフォリオを拡充しているのが特徴です。さらに、人材採用やリユース、海外進出にも意欲を見せており、成長余地の大きい領域を取り込む姿勢が明確です。
8-2. マーケットエンタープライズ<3135>のリユースプラットフォーム構築
ネット型リユース事業「高く売れるドットコム」を展開するマーケットエンタープライズは、中古品の買取価格比較サイト「おいくら」、修理業者比較サイト「最安修理ドットコム」などを相次いで取得し、“買う・売る・修理する”の循環を同社グループ内で完結できる体制を構築しつつあります。リユース市場は環境意識の高まりや節約志向、サステナブル消費の定着などにより拡大傾向にあります。比較サイトを組み込むことで、一気にユーザーとの接点を増やし、収益性を高める狙いがあると考えられます。
8-3. アドベンチャー<6030>の旅行分野強化
「skyticket」という旅行商品比較・予約サイトを強みに持つアドベンチャーは、ツアー企画会社や商品券販売会社、ファッションレンタルサービス、さらにエンタメチケット販売関連事業なども取得しており、幅広い分野へ広げています。旅行メディアの軸はそのままに、周辺サービスを取り込むことで、「単なる航空券比較サイト」を超えた総合プラットフォーム化を目指していると見られます。
第9章:今後の展望と戦略
9-1. 総合プラットフォーム化と垂直統合の加速
比較サイト・メディア業界の次なるステージとして、複数のサービスをワンストップで提供する「スーパーアプリ化」「統合プラットフォーム化」が挙げられます。例えば、旅行、グルメ、イベントチケット、ショッピングなどを一つにまとめることで、ユーザーの利便性を格段に高める動きです。M&Aによって多様な比較サイトや周辺サービス企業を取り込むことで、生活全般に対応できる巨大プラットフォームが誕生する可能性があります。
9-2. 差別化戦略としての専門特化
一方で、大手のプラットフォーマーがあらゆる領域を横断する場合、小規模・中規模の比較サイトは埋没してしまう可能性があります。そのため、特定のニッチ分野に特化し、徹底的に差別化を図る戦略も考えられます。たとえば「高級ホテルだけを比較する」「ハイブランドのリユース品に特化する」「海外在住者向けの日系サービス比較に絞る」などです。このような専門特化型サイトは、大手にはない独自性を武器として、一定のユーザー層から根強い支持を得ることが期待できます。また、特化サイトを展開する企業は大手プラットフォーマーや総合比較サイト運営企業にとって魅力的な買収ターゲットにもなり得ます。
9-3. データ活用とAIの導入
比較サイトではユーザーが検索やフィルタリングを行った履歴、口コミの傾向などの膨大なデータが蓄積されます。これをAI・機械学習で分析することで、レコメンド精度を高めたり、SEOや広告運用を最適化したりできるようになります。AI技術を自社で開発・運用できるかどうかは差別化のポイントになり得るため、AI関連技術を持つ企業のM&Aが増加することも予想されます。
9-4. 規制対応と信頼性の確保
保険や金融商品、医療、法律、福祉などは、今後も規制が強化される可能性がある分野です。比較サイトであっても、商品・サービスの紹介方法が募集行為と見なされれば、専門資格や届け出が求められます。また、ステルスマーケティングなどの不正広告対策や、消費者保護の観点からのコンプライアンス対応も不可欠です。サイトの信頼性を高めることは、結局のところユーザーの利便性や事業の持続性に関わる問題ですから、業界を健全に拡大していくうえでの課題と言えます。
第10章:まとめ
比較サイト・メディア業界は、ユーザーが商品・サービスを選択するうえで欠かせないインフラ的存在となってきました。ネット検索でまず比較サイトをチェックし、複数社の価格や特徴を比較してから申し込むという行動パターンが一般化しており、企業側もいかに比較サイトに情報を載せ、成約率を上げるかに注力しています。
このような環境下で、比較サイトを運営する企業はアクセス数が増えれば大きく成長できる一方、広告費やSEO施策などのコスト負担が高まるリスクや、大手プラットフォーマーの参入による競合激化という課題を抱えています。そこで、M&Aを活用してスケールメリットを追求したり、新領域への参入を一気に加速させたり、あるいは不要な事業を売却してリソースを集中させる動きが活発化しているわけです。
実際、比較.comをはじめとする先行プレイヤーは、多くの旅行や予約関連企業とのM&Aを通じてワンストップサービス化を図ったり、不要と判断した事業を売却するなど、機動的な事業ポートフォリオ再編を行ってきました。また、じげんやマーケットエンタープライズなど、もともと別の分野に強みを持つIT企業が、積極的に比較サイトを買収し、自社グループのサービス連携によるシナジーで成長を目指す事例も増えています。
一方で、MBO(経営陣による買収)によって非公開化するケースや、大手広告代理店がデジタルプラットフォーム企業を買収して自社広告ノウハウと掛け合わせるケースなど、業界構造の変動は多面的に進んでいます。このような動きは、比較サイト・メディア運営が多方面のステークホルダーにとって魅力的であることを示すとともに、すでに成熟期に入りつつある国内市場でさらなるイノベーションを起こすためには、M&Aが効果的な手段となっている証左とも言えます。
今後は、「統合プラットフォーム化」 と 「専門特化」 の両極の戦略がさらに鮮明化していくでしょう。大手企業は利用者や加盟店を一括で取り込むワンストップサービスとしての比較サイトを構築しようとし、ベンチャー企業や中小企業は独自ドメインに特化した比較サイト運営を追求して大手に対抗するか、あるいは将来的に大手に買収されるシナリオを想定して運営するかのいずれかになります。また、国内に限らず、アジアを中心とした海外マーケットへの展開や、AIを活用した高度な比較・レコメンドサービスの導入など、さらなる発展の余地が大きい領域と言えます。
比較サイト・メディア業界は、インターネット広告やEC市場の成長に伴い、今後も消費者の購買行動・契約行動の入り口としての重要性を増していくことが予想されます。そのため、M&Aを通じた業界再編や事業拡張の動きは引き続き活発に続くでしょう。企業がどのような戦略を描き、必要な事業を取得または手放すかのタイミングを見極めることが、今後の業界地図を大きく変えていくと考えられます。
終わりに
比較サイト・メディア業界のM&Aは、事業成長のためのスピード感 や 多角化戦略 を実現するうえで非常に効果的な手段である反面、競合激化 や 広告費高騰 などのリスクもはらんでいます。さらに、M&A後の統合の巧拙 が、成否を分ける重要なポイントとなります。
しかしながら、日々の暮らしやビジネスにおいて、インターネットによる「比較」はもはや切り離せない存在です。ユーザーが「より安く」「より便利に」「より適切なサービスを」選びたいというニーズは今後も拡大し続けるでしょう。そこにビジネスチャンスがある限り、比較サイト・メディア業界のM&Aは多彩な形で進化し続けると考えられます。
以上、比較サイト・メディア業界のM&Aに関して、過去の事例紹介から戦略的な考察、そして今後の展望に至るまで幅広く解説いたしました。本稿が、同業界への理解を深める一助になれば幸いです。

株式会社M&A Do 代表取締役
M&Aシニアエキスパート・相続診断士
東京都昭島市出身。慶應義塾大学理工学部を卒業後、大手M&A仲介会社にて勤務し、その後独立。これまで製造業・工事業を中心に友好的なM&Aを支援。また父親が精密板金加工業、祖父が蕎麦屋、叔父が歯科クリニックを経営し、現在は父親の精密板金加工業にも社外取締役として従事。