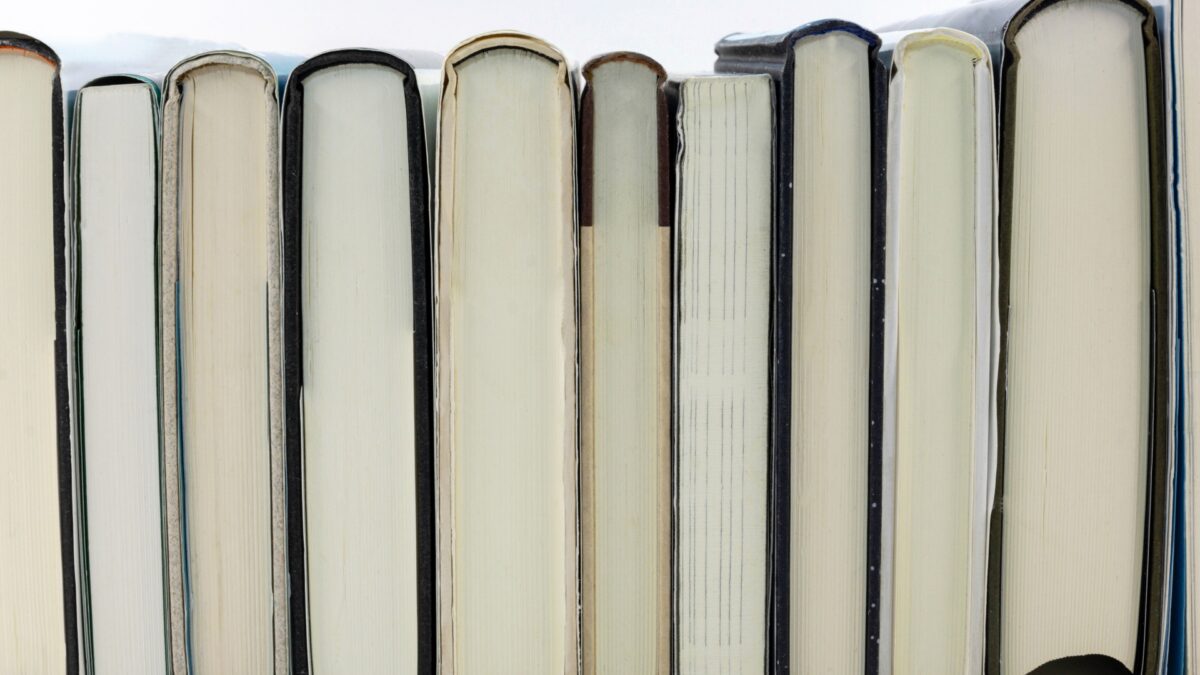- 1. はじめに:出版業界の概況とM&Aの役割
- 2. 出版業界におけるM&Aの主要な背景要因
- 3. 主要なM&A事例の詳細解説
- 3.1. 比較.com<2477>とマイナビ
- 3.2. 武田薬品工業<4502>とメディカルトリビューン
- 3.3. 廣済堂<7868>の連続的な出版子会社の譲渡
- 3.4. 相鉄ホールディングス<9003>と港北出版印刷
- 3.5. 日本創発グループ<7814>の一連の出版社関連M&A
- 3.6. 富士山マガジンサービス<3138>の多角的な買収事例
- 3.7. 凸版印刷<7911>のシンガポール印刷会社TOB
- 3.8. 乃村工藝社<9716>、六耀社子会社化
- 3.9. 日清医療食品<4315>による健康増進関連事業の買収
- 3.10. 大日本印刷<7912>と文教堂グループホールディングス<9978>をめぐる動き
- 3.11. 日本BS放送<9414>による児童書出版社の子会社化
- 3.12. 藤久ホールディングス<7135>の日本ヴォーグ社買収
- 3.13. 中広<2139>のフリーマガジン事業取得
- 3.14. 成学社<2179>の学習図書出版事業取得
- 3.15. 朝日放送グループHD<9405>による「歴史人」事業取得
- 3.16. 堀田丸正<8105>のギフト事業譲渡
- 3.17. 船井総合研究所<9757>によるビジネス社売却
- 3.18. 日本出版貿易<8072>のトーハンによるTOB
- 3.19. 昭和HD(昭和ホールディングス)、ウェッジHD株式の追加取得
- 3.20. 健康コーポレーション<2928>の日本文芸社買収とその後の譲渡事例
- 3.21. 昭文社ホールディングスの希望退職募集
- 3.22. 光村印刷<7916>と新村印刷の統合
- 3.23. 学研ホールディングス<9470>の知育玩具・出版関連買収と事業譲渡事例
- 3.24. 角川グループホールディングス<9477>によるメディアファクトリー買収
- 3.25. 幻冬舎<7843>のMBO
- 3.26. 栄光<9789>の英語教材企業買収
- 3.27. 葵プロモーション(現AOI Pro.)<9607>のゴルフ雑誌事業取得
- 3.28. 出版社の秀和システム、中堅家電メーカー船井電機<6839>をTOBで買収
- 3.29. 三井物産<8031>とヒューマン・アソシエイツ・HDのTOB
- 3.30. 関通<9326>と河出興産の出版物流サービス事業取得
- 3.31. リンクアンドモチベーション<2170>のIR領域買収と出版事業譲渡
- 3.32. メディアドゥ<3678>の積極的な出版社・関連事業買収
- 3.33. ブックオフコーポレーション<3313>のTSUTAYA店舗譲渡
- 3.34. ビーグリー<3981>の出版社買収(ぶんか社など)
- 3.35. ドリームインキュベータ<4310>と枻出版社の一部事業取得
- 3.36. パス<3840>の「DRESS」や化粧品ブランド「エクスボーテ」関連の一連のM&A
- 3.37. テンプスタッフ<2181>による日経スタッフ買収
- 3.38. ノーリツ鋼機<7744>によるハルメクHD買収とMBO譲渡
- 3.39. ジェイ・エスコムHD<3779>による「Soup.」取得など
- 3.40. ソニー<6758>のAWAL事業買収(音楽配信分野)
- 3.41. ショーケース・ティービー<3909>によるオンデマンド出版企業の子会社化
- 3.42. クリーク・アンド・リバー社<4763>の映像・出版周辺領域強化
- 3.43. カイカ<2315>によるネクス・ソリューションズの譲渡
- 3.44. YAMATO<7853>によるフリーマガジン関連企業の売却
- 3.45. フォーバルテレコム<9445>と印刷会社M&A
- 3.46. ウィーヴ<2360>のファンドによるTOB
- 3.47. アイフィスジャパン<7833>の投資助言事業取得
- 3.48. オプト<2389>のゴルフ出版事業「ALBA」譲渡
- 3.49. フォーサイド<2330>の事業多角化と出版業参入
- 3.50. アイティメディア<2148>の音楽情報サイト譲渡
- 3.51. TKC<9746>、TKC出版株式交換
- 3.52. アエリア<3758>のインフォトップ子会社化
- 3.53. INCLUSIVE<7078>によるJコミックテラスの子会社化
- 3.54. TAC<4319>、早稲田経営出版の事業取得
- 3.55. IMAGICA GROUP<6879>による主婦の友インフォスの子会社化
- 3.56. ODKソリューションズ<3839>のエフプラス子会社化
- 3.57. ACCESS<4813>が電子出版ソリューション事業をブックウォーカーへ譲渡
- 3.58. GCAサヴィアングループ<2174>のバイアウト研究所事業取得
- 3.59. SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ<9478>によるファーストアカデミー買収
- 3.60. IBJ<6071>、ウェディング関連出版社の買収
- 3.61. 「Z会」の増進会出版社による栄光ホールディングス<6053>買収
- 3.62. AOI Pro.<9607>(葵プロモーション)の「週刊パーゴルフ」事業譲渡
- 3.63. カヤック<3904>によるビジネス書・社会書の英治出版子会社化
- 3.64. YOZAN<6830>の飛鳥新社譲渡とコンテンツ事業からの撤退
- 4. 事例から見る出版M&Aのパターンと特徴
- 5. 出版業界M&Aのメリット・デメリット
- 6. 今後の展望と課題
- 7. まとめ:M&Aが描く出版の近未来像
1. はじめに:出版業界の概況とM&Aの役割
出版業界では、長期的な市場縮小やデジタルコンテンツの普及に伴い、大きな事業転換を迫られてきました。いわゆる“出版不況”は1996年頃から始まったとされ、紙媒体の売上がピークを迎えた後、徐々に落ち込みが続いています。そこにインターネットの普及や電子書籍・電子雑誌市場の拡大が重なり、従来の紙に依拠した収益モデルだけでは、十分に収益を確保できなくなりました。
さらに2020年代に入ると、コロナ禍による行動制限でEC・デジタルの利用が加速し、電子出版市場は一層拡大しました。一方で、在庫コストや返品リスクを抱える従来型ビジネスに頼る出版社は、厳しい経営環境に立たされるケースが増えています。こうした状況に合わせ、コンテンツのデジタル化や新規市場への投資、あるいは不採算部門の整理を目的として、多くの企業がM&Aを選択するようになりました。
出版業界のM&Aには、大きく分けて次のような目的が見られます。
- 事業の選択と集中
採算の取りづらい紙媒体中心の部門を切り離し、デジタルやIT事業に経営資源を集中する。 - 成長領域への参入
主力事業での頭打ち感が強い企業が、教育事業や海外展開、周辺領域(広告代理業、Webメディアなど)への参入を図る。 - 中堅・中小出版社の事業承継
出版不況や経営者の高齢化により、自社単独での事業継続が困難となり、大手や新興企業に買収・譲渡を行う。 - コンテンツ拡充による付加価値の向上
映像、音楽、ゲームなど、他メディアとの連携を強化するために出版社を買い取り、新たな収益源を模索する。
以下の項目では、これらの目的を踏まえながら、多数の具体的事例を通して出版業界でのM&A動向を紐解いてまいります。
2. 出版業界におけるM&Aの主要な背景要因
2.1. 出版不況と消費者の嗜好変化
日本における出版不況は、雑誌・書籍の売上がピークだった1996年を境に、徐々に下降線をたどってきました。消費者のメディアとの接触形態が多様化し、SNSや動画配信サイトなど、新しい娯楽や情報源に時間を奪われているのが大きな要因です。
このような構造変化により、出版企業が従来の紙媒体ビジネスだけでは立ち行かなくなり、広告収入やEC、デジタルコンテンツ販売など、新たな柱の構築を急務とするケースが増えています。その一環として、事業ポートフォリオの再編や、強みを持つ企業を買収し経営統合するM&Aが促進されているのです。
2.2. 電子出版市場の成長とデジタル化の波
2010年代以降のスマートフォン普及、クラウド技術の発達により、電子書籍・電子雑誌市場は拡大を続けています。マンガアプリの隆盛に象徴されるように、スマホやタブレット上で読むデジタルコンテンツが大きな盛り上がりを見せています。紙の取次を介さないビジネスモデルが増え、出版取次会社はもちろん、紙メディア中心だった出版社自身も変革を迫られました。
電子媒体へのシフトには、在庫コストや返品リスクを軽減できるメリットがあるものの、IT投資やノウハウ面でハードルが高いのも事実です。そこで専門知識を持つIT企業が出版社を買収する、または出版社がIT企業を取り込むといった動きが見られます。
2.3. 事業ポートフォリオ再編の加速
印刷会社や新聞社、人材事業会社など、出版周辺の幅広い企業が、収益性の低い従来型ビジネスから脱却し、IT分野や新規事業へ経営資源を集中させるために、出版部門を切り離す動きも増えています。また、大手企業が抱える出版子会社の連続譲渡もめずらしくありません。
買い手企業にとっては、こうした非中核部門を譲り受けることで、新たな顧客基盤や商品ラインナップを獲得するチャンスとなります。老舗出版社が抱えるブランド力やノウハウは大きな資産であるため、うまく活用すれば新たな市場やビジネスモデルを開拓できるのです。
2.4. シナジー創出の可能性
最近では、出版業と異業種が手を組むケースが目立っています。たとえば、人材企業やコンサルティング会社が出版ノウハウを利用して、独自のメディア戦略を打ち立てる、あるいは教育事業との連携で独自の学習コンテンツを開発するなど、M&Aによって双方の強みを掛け合わせるシナジーが期待されます。
また書店網やフリーマガジンを傘下に収め、広告事業やECと結びつけることで、販売チャネルを広げる動きも顕著です。出版社単独では到達できないマーケットにアクセスし、紙とデジタルの両方を使った多面的なアプローチを狙う事例が増えています。
3. 主要なM&A事例の詳細解説
本章では、挙げきれないほど多数にのぼるM&Aの中から、代表的な事例を中心にご紹介いたします。それぞれのケースが持つ背景、狙い、そして譲渡後の方向性などを概観することで、出版業界全体のダイナミックな動きを立体的に捉えられるでしょう。
3.1. 比較.com<2477>とマイナビ
2013年、比較.comは子会社が運営する国内宿泊予約サイト事業をマイナビへ譲渡しました。比較.comは本来、複数のサービスの価格比較サイト運営で知られていましたが、事業戦略を再定義し、インターネット広告事業やアプリケーションサービス事業に注力するために不要と判断した国内宿泊予約事業を手放したのです。
一方、マイナビは新聞発行・出版事業など幅広いメディアを持っており、旅行や観光メディアとのシナジーを期待して今回の譲受を決定しました。譲渡価額は3,500万円とされています。
3.2. 武田薬品工業<4502>とメディカルトリビューン
2014年、武田薬品工業は医学・薬学関連の出版を手掛ける日本臨牀社を、同業のメディカルトリビューンに譲渡しました。日本臨牀社は医学界で70年の歴史を持つ老舗出版社でしたが、今後はメディカルトリビューンと協業することで相乗効果が高まると判断されました。
製薬会社が自ら医学系の出版社を保有する意義は大きかったものの、昨今の製薬業界の再編や研究開発への集中などの事情もあり、出版部門を手放すことが最善と判断したとみられます。
3.3. 廣済堂<7868>の連続的な出版子会社の譲渡
廣済堂は印刷や人材事業を主力とする企業ですが、出版不況の中で出版部門が苦戦し、コア事業への集中を図るために出版子会社を立て続けに譲渡しています。
- 廣済堂出版の個人譲渡(2019年)
同子会社は5期連続赤字を出していたため、出版不況の影響が大きく、短期改善が見込めないと判断されました。最終的に出版事業の知見を持つ個人へと譲渡されました。 - 廣済堂あかつきの譲渡(2021年)
教科書用図書や学校用図書教材などを手がける廣済堂あかつきも、児童数の減少や新規参入した教科書事業の採算が確保できず、2期連続赤字を計上していました。こちらも第三者個人へ譲渡し、コア領域(印刷・IT、人材、ライフスタイル事業)へ集中する姿勢を明確にしています。
このように廣済堂の事例は、不採算部門の整理による事業構造の転換を物語る典型的なケースといえます。
3.4. 相鉄ホールディングス<9003>と港北出版印刷
相鉄ホールディングスは2012年末、完全子会社の相鉄エージェンシー(広告代理業)株式の90%を港北出版印刷へ譲渡しました。景気低迷や震災後の自粛ムードによる広告市場縮小が重なり、収支改善に時間がかかるとみられたためです。
広告と出版は密接な関係があり、港北出版印刷としては広告代理業を取り込むことで、出版事業とのシナジーが見込めると判断しました。
3.5. 日本創発グループ<7814>の一連の出版社関連M&A
日本創発グループは近年、出版・編集プロダクションや定期雑誌運営企業、印刷関連会社などを相次ぎ買収し、大きく事業領域を拡張しています。
- ワン・パブリッシングの子会社化(2022年)
学研プラスと共同出資で立ち上げたワン・パブリッシングを追加出資により子会社化。「GetNavi」「CAPA」「ムー」などのブランド力を活かしつつ、コンテンツ領域を強化。 - Playce子会社化(2017年)
広告宣伝物や出版物の企画・編集を行うプロダクションを取り込み、女性向け感性を活かした制作やクリエイター育成ノウハウを獲得しました。 - 宏和樹脂工業の子会社化(2017年)
特殊印刷や表面加工に強みを持つ会社を買収し、ポスターやパッケージなどの出版物への加工技術を自社グループに取り込むことで付加価値を高めました。 - ビジネス・生活実用書のアスコム買収(2024年)
出版企業を取り込むことでグループ全体のメディア関連事業を拡充させています。
日本創発グループの一連の動きは、「コンテンツ供給から印刷加工まで一気通貫で手掛ける」垂直統合モデルを目指す狙いがうかがえます。
3.6. 富士山マガジンサービス<3138>の多角的な買収事例
定期購読サービス「富士山マガジン」を運営する同社は、出版・映像関連から教育分野に至るまで複数の事業を積極的に買収し、多角化を進めています。
- しょうわ出版の子会社化(2019年)
社会保険・介護保険関係の加除式出版物を扱い、安定した法人顧客基盤を持つ点に注目して買収しました。 - 「翔進予備校」などの塾事業取得(2024年)
医系学部や難関大向けの理数系塾事業を取り込み、オンライン個別指導塾とのシナジーを目指しています。 - WEB動画サイト運営の103Rを子会社化(2018年)
デジタルメディア化やイベント企画などを強化し、「雑誌の日」イベントの共同運営などを行っています。
こうした多角化戦略は、出版企業の枠を超えて新たな収益源を取り込む好例といえます。
3.7. 凸版印刷<7911>のシンガポール印刷会社TOB
凸版印刷は2008年にシンガポールのSNP Corporation LimitedをTOBで買収しました。出版物、パッケージ、有価証券など幅広い印刷分野を手がけ、特に中国市場で成長を遂げていたSNPを子会社化することで、アジア展開の基盤強化を狙ったのです。
印刷大手が国際展開を図るにあたって、海外企業の買収は有効手段となります。これにより、現地生産拠点や販売ルート、顧客基盤を迅速に手に入れることが可能になります。
3.8. 乃村工藝社<9716>、六耀社子会社化
ディスプレー事業大手の乃村工藝社は2014年、美術やデザイン関連分野に強い六耀社を完全子会社化しました。六耀社は図書の編集・出版サービスを長年手がけており、乃村工藝社は展示会やイベントなどでの販促物制作を強化する狙いがありました。
ディスプレーや空間演出と出版の融合は意外に感じられますが、デザイン関連のコンテンツやノウハウが共通点となり、顧客へのサービス領域を広げることが可能となります。
3.9. 日清医療食品<4315>による健康増進関連事業の買収
2008年、医療機関・高齢者施設向けの食事サービス大手である日清医療食品は、健康関連事業の現代けんこう出版を子会社化しました。特定保健指導や健康増進に関する企画運営を行う同社を取り込むことで、食事・栄養指導とあわせた総合的な健康ソリューションの提供を図っています。
一見すると出版事業とは縁遠いように見えますが、健康増進・保健指導関連の出版物や情報発信を手がける現代けんこう出版のノウハウを得ることで、日清医療食品は医療領域での付加価値を高める狙いがありました。
3.10. 大日本印刷<7912>と文教堂グループホールディングス<9978>をめぐる動き
大日本印刷(DNP)は2010年、文教堂グループHDが実施する第三者割当増資を引き受け子会社化し、一時は筆頭株主として書店チェーンを手中に収めました。その後、2016年に雑誌・書籍取次会社の日本出版販売(日販)へ株式を一部譲渡し、文教堂HDを連結子会社から持分法適用会社へと変えています。
これは書店・取次と連携し、新たな流通プラットフォーム構築を試みる一方、紙媒体市場の縮小に合わせて資本関係を適切に調整する動きとみられます。
3.11. 日本BS放送<9414>による児童書出版社の子会社化
2018年に日本BS放送は理論社、国土社という児童・教育図書を手がける出版社2社を相次ぎ買収し子会社化しました。テレビ放送事業者が児童書分野に乗り出すことで、教育関連コンテンツを手に入れ、番組やイベントなどとの連携を図る狙いがあったと考えられます。
児童書や教育図書は出版業界の中でも比較的堅調とされ、学校図書館や公共図書館などの需要が一定数存在することが魅力です。
3.12. 藤久ホールディングス<7135>の日本ヴォーグ社買収
手芸専門店「クラフトハートトーカイ」を全国展開する藤久ホールディングスは、日本ヴォーグ社(手芸に関する出版・教育事業)を2022年に株式交換で子会社化しました。手芸教室や商品の企画・販売をワンストップで提供するビジネスモデルの構築を目指し、出版・教育のノウハウを取り込んでいます。
手芸分野では高齢化や趣味の多様化の影響がありますが、ECやオンライン講座などの需要増が期待されるため、デジタルとリアル店舗が連携した展開が有望とみられます。
3.13. 中広<2139>のフリーマガジン事業取得
地域生活情報誌を発行する中広は、同業他社が運営するフリーマガジン事業を買収して地域ごとの市場拡大を進めてきました。2015年には群馬県の「月刊パリッシュ」事業、2016年には愛知県の「Cocon」事業などを相次いで取得しています。
フリーマガジン事業は広告収入を柱とするため、地域密着型の展開と拠点拡大が成長の鍵となります。同社は全国的にフリーマガジンのネットワークを構築し、広告効果を高めようとしています。
3.14. 成学社<2179>の学習図書出版事業取得
学習塾運営で知られる成学社は、2013年に私立中高向け進学資料集などを手がける翔文社の出版事業を取得しました。これにより、学校支援の充実と自社学習塾の教学力アップを図っています。
教育関連では、塾や予備校が自ら教材制作・出版に乗り出すことが珍しくなくなっています。学習ノウハウを出版社と連携して商品化することで、新たな収益を生み出す狙いがあるのです。
3.15. 朝日放送グループHD<9405>による「歴史人」事業取得
朝日放送グループHDは、中堅出版社ベストセラーズから月刊誌「歴史人」事業を取得(2020年)しました。「歴史人」は愛好者が多く、イベントや観光コンテンツへの展開などが見込めます。放送局としてはこの強固なファンコミュニティを活用して、新規事業やコンテンツ制作とのシナジーを図りたい狙いがあったようです。
3.16. 堀田丸正<8105>のギフト事業譲渡
アパレル・繊維を中心に手がける堀田丸正は、返礼品・会葬品などのギフト事業を新聞・出版物取次のエヌエスアイに譲渡(2023年)。アパレル主軸に絞るための事業再編とみられます。
一方でエヌエスアイにとっては、既存の取次ネットワークとギフト事業を組み合わせることで、新たな市場開拓や流通の相乗効果を期待できる事例といえます。
3.17. 船井総合研究所<9757>によるビジネス社売却
コンサル大手の船井総合研究所は、子会社として出版事業を手がけるビジネス社を1991年に買収していましたが、2011年にビジネス社を個人(同社取締役)に譲渡しました。メディアの多様化・電子書籍の普及などで競争が激化し、同社が掲げる中期戦略と合致しなくなったと考えられます。譲渡価額は非常に低額(2万4,000円)で、債務超過など財務状況の厳しさがうかがえます。
3.18. 日本出版貿易<8072>のトーハンによるTOB
洋書輸入・和書輸出を主力とする老舗企業の日本出版貿易は、2024年に出版取次大手のトーハンからTOB(株式公開買付)を受け入れ、株式を非公開化する方針を発表しました。出版業界の縮小や英語教育ニーズの高まりで海外事業の拡大に注力する同社が、トーハンとの協力を深めることでデジタルシフトやグローバル展開を加速したい狙いがあるようです。
TOB後は上場廃止となり、アグレッシブな経営改革を推し進めるとされています。
3.19. 昭和HD(昭和ホールディングス)、ウェッジHD株式の追加取得
昭和ホールディングスは2011年、ゲーム・出版事業などを行うウェッジホールディングス株式を追加取得し、子会社化しました。ウェッジホールディングスはアジアを中心とした投資やコンテンツ事業に強みがあり、昭和HDとしては事業拡大の足掛かりを得る考えがあったと推測されます。
3.20. 健康コーポレーション<2928>の日本文芸社買収とその後の譲渡事例
RIZAPグループとも呼ばれる健康コーポレーション(現RIZAPグループ)は、2016年に日本文芸社を20億円で買収。自身のダイエット関連ノウハウや広告と連携させる狙いがあったといわれます。ところが、グループの中期戦略再編の過程で、2021年に日本文芸社をメディアドゥへ譲渡することが決定されました。
RIZAPグループでは美容・ヘルスケア関連への集中を進めるため、短期的にシナジーが見込めない企業については売却する方針をとっており、出版事業が整理対象となった形です。
3.21. 昭文社ホールディングスの希望退職募集
地図出版社として知られる昭文社HDは、出版不況にコロナ禍が重なり経営不振に陥り、希望退職を募集(2022年)しました。地図・ガイドブック事業からのデジタル転換や、旅行・観光需要の先細りが背景とみられます。これも事業再編の一環であり、今後M&Aを含むさらなる動きが出てくる可能性があります。
3.22. 光村印刷<7916>と新村印刷の統合
2018年、光村印刷は包装・パッケージ、証券印刷、出版物印刷などで実績のある新村印刷を買収し、子会社化しました。光村印刷は商業印刷や美術印刷に強みを持ち、一方の新村印刷は包装分野において豊富なノウハウを蓄積しています。相互補完により事業基盤を拡大し、新しい分野への進出も見込めると考えられます。
3.23. 学研ホールディングス<9470>の知育玩具・出版関連買収と事業譲渡事例
学研ホールディングスは児童書出版の老舗として知られていますが、積極的なM&Aや事業譲渡を通じて教育・福祉分野の再編を進めてきました。
- 文理の子会社化(2015年):学習参考書分野を強化
- 学研ステイフルの株式51%を日本出版販売に譲渡(2023年):「学研ステイフル」が手がける知育玩具・文具事業を共同運営し、グローバル展開や商品開発を強化
このように連携先のネットワークを活かしてシェア拡大を狙うのが学研グループの戦略と見られます。
3.24. 角川グループホールディングス<9477>によるメディアファクトリー買収
2011年、角川GHDはリクルート傘下でコミック・小説出版やアニメーション製作を手掛けていたメディアファクトリーを80億円で買収しました。コミックやライトノベル市場で強いシェアを持つメディアファクトリーを取り込むことで、グループ全体として一層のメディアミックス展開を促進し、コンテンツ事業の収益拡大を図りました。
3.25. 幻冬舎<7843>のMBO
2010年、幻冬舎は社長である見城徹氏らによるMBOを公表しました。紙の出版や広告売上が落ち込むなかで、非公開化して機動的な経営改革を行う必要があると判断したと考えられます。当時の株式公開買付価格は1株あたり22万円とされ、公開前株価から50%以上のプレミアムを付けた買付でした。
3.26. 栄光<9789>の英語教材企業買収
学習塾の栄光は2010年、英語教材の販売、出版を行うネリーズやサクソンコートパブリッシングを買収しました。いずれも外国語学習分野に強い企業で、栄光はこれらを取り込み、学習塾にとどまらない総合的な教育サービスを構築する考えを示しています。
3.27. 葵プロモーション(現AOI Pro.)<9607>のゴルフ雑誌事業取得
2011年、葵プロモーションは学研パブリッシングが発行していた「週刊パーゴルフ」などのゴルフ出版事業を新たに設立する子会社を通じて買収しました。翌年には再び同事業を他社へ売却するなど、ゴルフメディアのブランド活用と経営の見直しが進められてきました。
3.28. 出版社の秀和システム、中堅家電メーカー船井電機<6839>をTOBで買収
2021年には、IT・ビジネス書で知られる中堅出版社の秀和システムが、家電メーカー船井電機をTOBで買収するという異例の動きがありました。船井電機は海外展開が強みでしたが、業績の伸び悩みから上場維持が難しくなっており、秀和システム傘下で再建を図る形となりました。
出版と家電という異業種の組み合わせですが、M&Aによって相互のコスト構造を見直すことや、電子書籍リーダー機器などハードとソフトの融合ビジネスを模索する可能性も考えられます。
3.29. 三井物産<8031>とヒューマン・アソシエイツ・HDのTOB
総合商社の三井物産は、メンタルヘルスケア事業を手がけるヒューマン・アソシエイツ・ホールディングスを2021年にTOBで買収し、完全子会社化を目指しました。三井物産は2020年に保健同人社(出版・医療系情報)を買収しており、ヘルスケア分野での包括的サービス構築に動いています。
出版物を扱う保健同人社やメディアを取り込むことで、紙媒体・デジタル媒体の双方を活かした健康支援ビジネスを拡大する狙いがあるようです。
3.30. 関通<9326>と河出興産の出版物流サービス事業取得
物流企業の関通は2023年、河出書房新社の傘下企業が手がける出版物流サービスを新設子会社へ承継し、取得しました。出版物流通の効率化やノウハウを取り込むことで、自社のEC・通販物流に活かす狙いがあります。
3.31. リンクアンドモチベーション<2170>のIR領域買収と出版事業譲渡
コンサルティング事業を主力とするリンクアンドモチベーションは2008年頃、IR支援事業を展開していた日本インベスターズサービスを買収しましたが、株式投資専門誌「株式にっぽん」などの出版事業については後に相乗効果が得られず譲渡しています。これはM&A後の整理・統合で、当初想定したシナジーが想像ほど生まれなかった典型例といえます。
3.32. メディアドゥ<3678>の積極的な出版社・関連事業買収
電子書籍取次サービスで急成長を遂げたメディアドゥは、出版関連会社の買収を次々と行い、電子出版市場で強い立ち位置を確立しようとしています。
- 出版デジタル機構の子会社化(2017年)
親会社が産業革新機構だった出版デジタル機構を79.4億円で買収。電子書籍取次における大手プラットフォームを手に入れました。 - フライヤーの子会社化(2016年)
書籍要約サービスを提供するスタートアップを買収し、電子書籍との相互送客が期待されます。 - 日本文芸社買収(2021年)
RIZAPグループから取得することで、雑誌・書籍の出版力を強化。 - エブリスタ買収(2021年)
DeNA傘下で小説投稿サイトを運営していたエブリスタを買収し、投稿コミュニティの充実化を図る。 - Supadü社買収(2022年)
英国のWeb構築・ECサービス企業を取り込み、海外市場にも展開。
こうした一連の動きは、電子書籍のサプライチェーンを上流から下流まで押さえ、国内外でマルチメディア展開を狙う戦略の一貫とみられます。
3.33. ブックオフコーポレーション<3313>のTSUTAYA店舗譲渡
中古書店チェーンのブックオフは2014年、子会社が展開するTSUTAYAフランチャイズ店31店舗を日本出版販売(日販)へ譲渡しました。ブックオフ自身は中古書籍やメディア商品の販売に特化し、レンタル事業から撤退することで収益性の高いコアビジネスに集中する形です。一方、日販は書店事業とのシナジーを狙い、全国にTSUTAYA店舗ネットワークを広げています。
3.34. ビーグリー<3981>の出版社買収(ぶんか社など)
電子コミック「まんが王国」を主力とするビーグリーは2020年、女性向け漫画で有名なぶんか社や海王社など5社を傘下に持つNSSK-CCを約53億円で買収しました。強力なコンテンツを取り込むことで、自社の電子コミック配信ビジネスをさらに拡大する狙いがあります。
3.35. ドリームインキュベータ<4310>と枻出版社の一部事業取得
戦略コンサルで知られるドリームインキュベータは2021年、アウトドア・スポーツ系を中心とした雑誌「エイ出版社(枻出版社)」の一部事業を取得し、新会社を設立しました。アウトドア分野は根強いファンコミュニティがあり、メディア事業や関連グッズ販売との連携を見込んだ動きといえます。
3.36. パス<3840>の「DRESS」や化粧品ブランド「エクスボーテ」関連の一連のM&A
ITベンチャーとして知られたパスは、女性誌「DRESS」の出版やEC運営会社ギフトや、化粧品ブランド「Ex:BEAUTE」を展開するマードゥレクスを買収するなど、美容関連事業へ積極的に乗り出しました。出版社の読者会員基盤をECやコンサル事業に活用し、新たな売上を創出しようとする試みです。
3.37. テンプスタッフ<2181>による日経スタッフ買収
人材派遣のテンプスタッフは2011年、日本経済新聞社の子会社である日経スタッフを買収しました。主に編集・校正といった特殊技能を持つ派遣スタッフのマッチングを強化し、人材事業の付加価値を高める狙いがあったとみられます。
3.38. ノーリツ鋼機<7744>によるハルメクHD買収とMBO譲渡
ノーリツ鋼機は2012年にシニア向け出版・通販で知られる「いきいき」(現ハルメク)を買収し、さらに「全国通販」を抱える通販企業も取得し、シニア事業を一挙に拡大しました。しかし2020年にハルメクHDの経営陣によるMBOを受け、同社を譲渡しています。シニア女性雑誌「ハルメク」は好調でしたが、ノーリツ鋼機としては選択と集中を進めた結果と考えられます。
3.39. ジェイ・エスコムHD<3779>による「Soup.」取得など
ジェイ・エスコムHDは、女性向けファッション雑誌「Soup.」の出版事業をモール・オブ・ティーヴィーなどから取得(2016年)し、自社メディアと連携して物販ビジネスを狙う姿勢を見せました。ただし雑誌の市場縮小が続く中、買収後の成長戦略次第では難航するケースも考えられます。
3.40. ソニー<6758>のAWAL事業買収(音楽配信分野)
ソニーグループは2021年、英コバルト・ミュージックから音楽配信サービス「AWAL」を買収しました。これは出版ではなく音楽権利ビジネスですが、著作権管理・コンテンツ流通という点で出版と類似性があります。メディアやコンテンツ産業のデジタルシフトを積極的に取り込む事例の一つです。
3.41. ショーケース・ティービー<3909>によるオンデマンド出版企業の子会社化
オンデマンド出版を手がけるgalaxyを買収(2017年)することで、小ロット出版や電子書籍を効率的に提供する体制を整えました。これは書籍のPOD(Print on Demand)技術が広まることで在庫リスクを低減し、多品種を展開する強みを狙う例といえます。
3.42. クリーク・アンド・リバー社<4763>の映像・出版周辺領域強化
クリエイター派遣を主力とする同社は、映像制作やVR事業に関わる会社を相次いで買収し、出版やWeb制作などのトータルソリューション提供を目指しています。2019年には3DCGアバター事業を展開する企業を取り込み、ゲームや書籍のデジタル展開を強化しました。
3.43. カイカ<2315>によるネクス・ソリューションズの譲渡
ブロックチェーン技術などに注力するカイカは、既存のシステム開発子会社を出版社の実業之日本社に売却し、本業に集中しました。IT企業が出版関連企業にシステム開発部門を譲渡するという逆パターンは珍しく、業務提携などの可能性も検討されたのでしょう。
3.44. YAMATO<7853>によるフリーマガジン関連企業の売却
YAMATOはフリーマガジン『ポノポノ』を発行していた子会社を2008年に譲渡し、債権放棄も行いました。経営統合後に期待していたシナジーが得られず、早期の事業撤退を決めた例といえます。
3.45. フォーバルテレコム<9445>と印刷会社M&A
フォーバルテレコムは、グループ会社のトライ・エックスを通じて印刷業のタクトシステムを子会社化し、出版物の制作・出力といった一連の工程を効率化しました。電気通信企業が印刷業と組むことで、法人向けのトータルソリューションを狙います。
3.46. ウィーヴ<2360>のファンドによるTOB
テレビアニメやキャラクター、出版事業を手掛けるウィーヴは2009年、投資ファンドによるTOBを受け、非公開化を目指しました。メディアコンテンツの海外展開など機動的な戦略実行のため、上場維持よりもMBOを選択するケースが多くなっています。
3.47. アイフィスジャパン<7833>の投資助言事業取得
アイフィスジャパンは2015年、ダイレクト出版から個人投資家向け投資助言事業を取得しました。自社の金融情報サービスとの相乗効果を狙い、投資関連コンテンツの拡充を進めています。ダイレクト出版もビジネス書やマーケティング関連の出版が主軸で、投資助言分野の事業整理を決めたようです。
3.48. オプト<2389>のゴルフ出版事業「ALBA」譲渡
インターネット広告のオプトは2005年に「ALBA」ブランドを買収したものの、2008年に経営陣主導のMBOで同事業を売却しました。ネット広告事業への集中を進める一方で、出版事業の再構築には時間とリソースがかかると判断したと思われます。
3.49. フォーサイド<2330>の事業多角化と出版業参入
デジタルコンテンツ配信からスタートしたフォーサイドは2019年ごろに出版事業を始め、その後クレーンゲーム景品企画や家賃保証などへも進出し、多角化を進めています。異業種参入でリスク分散と新規収益源の確保を狙う典型例です。
3.50. アイティメディア<2148>の音楽情報サイト譲渡
ITニュースサイトを主力とするアイティメディアは、かつてデジタルコンテンツ事業の強化を目指して「BARKS(バークス)」という音楽情報専門サイトを保有していましたが、相乗効果に限界があり2012年にグローバル・プラスへ譲渡。自社本業であるIT・ビジネス情報サイトの強化を図りました。
3.51. TKC<9746>、TKC出版株式交換
会計ソフト大手のTKCは関連会社のTKC出版を2019年に株式交換によって完全子会社化しました。会計事務所向けの教材・出版事業を取り込み、財務会計分野でのワンストップサービスを充実させる意図があります。
3.52. アエリア<3758>のインフォトップ子会社化
ゲーム事業・IT事業を展開するアエリアは2015年、オンライン電子出版に特化したアフィリエイト企業インフォトップを子会社化。電子商材やデジタル教材などの販売力を取り込み、新規収益源を確保しました。
3.53. INCLUSIVE<7078>によるJコミックテラスの子会社化
メディア運営支援を手がけるINCLUSIVEは2023年、DeNA傘下の小説投稿サイト運営企業エブリスタを買収したメディアドゥからさらに分社した「マンガ図書館Z」のJコミックテラスを買収。漫画家やクリエイター向けの支援事業を強化し、投稿コミュニティのプラットフォームビジネスを狙います。
3.54. TAC<4319>、早稲田経営出版の事業取得
資格スクール大手のTACは2009年、大日本印刷子会社の早稲田経営出版(Wセミナー)の資格取得支援事業と出版事業を取得し、司法試験や公務員試験などの領域を拡充しました。大手スクールが競合する受験市場で優位に立つため、老舗の知見を吸収する戦略です。
3.55. IMAGICA GROUP<6879>による主婦の友インフォスの子会社化
映像制作会社大手のIMAGICA GROUPは2019年、主婦の友社子会社の主婦の友インフォス(ライトノベルや雑誌「声優グランプリ」など)の株式95%を取得。映像・アニメ分野と出版分野を掛け合わせ、メディアミックスを強化する狙いです。
3.56. ODKソリューションズ<3839>のエフプラス子会社化
教育機関システムを手がけるODKソリューションズは2009年、金融機関向けシステム開発や流通出版向け業務ソリューションを提供するエフプラスを買収し、金融や教育関連のシステム強化を図りました。出版への直接的関与よりは、業務システム面からのサポートとしての買収です。
3.57. ACCESS<4813>が電子出版ソリューション事業をブックウォーカーへ譲渡
通信ソフトウェアで知られるACCESSは2023年、電子書籍関連ソリューション部門をKADOKAWA子会社のブックウォーカーに譲渡しました。IoT事業へ経営資源を集中する一方、出版ソリューションは電子書籍事業大手に引き継いでもらう形です。
3.58. GCAサヴィアングループ<2174>のバイアウト研究所事業取得
M&Aアドバイザリーを展開するGCAサヴィアングループは2008年、非上場企業データなどをリサーチする日本バイアウト研究所の事業を取得し、新会社を設立しています。これは専門誌の刊行や調査データ提供など、出版社的な活動を通してM&A市場の情報を収集・発信するための動きでした。
3.59. SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ<9478>によるファーストアカデミー買収
IT・資格書の翔泳社を中核とする同社は、電気主任技術者試験向け教材を提供するファーストアカデミーを子会社化(2010年)し、資格・検定分野での出版コンテンツ強化を図りました。特化型教材の分野はニッチな需要があり、安定的な収益が期待できます。
3.60. IBJ<6071>、ウェディング関連出版社の買収
婚活支援大手のIBJは2016年、結婚式場紹介雑誌やウェディング関連書籍を発行するウインドアンドサンを子会社化しました。婚活だけでなく式場紹介、イベント企画、旅行など周辺事業をワンストップで提供する“ブライダル総合企業”を目指す動きです。
3.61. 「Z会」の増進会出版社による栄光ホールディングス<6053>買収
通信教育「Z会」を運営する増進会出版社は2015年に栄光HDを買収し、完全子会社化を目指すTOBを行いました。少子化に伴う厳しい環境下、塾事業と通信教育事業を統合し、総合教育グループとしての競争力を高めようとする狙いです。出版企業が学習塾を取り込む動きは近年増えており、教育コンテンツの相互提供とデジタル化が進んでいます。
3.62. AOI Pro.<9607>(葵プロモーション)の「週刊パーゴルフ」事業譲渡
広告・映像制作大手のAOI Pro.は2011年にゴルフ雑誌「週刊パーゴルフ」事業を取得したのち、2014年に別会社ALBAへ譲渡しました。短期間での取得・譲渡となり、当初狙っていたメディア展開が期待どおりには進まなかった可能性があります。ゴルフ業界ではメディアとイベント事業を組み合わせるビジネスモデルが多いものの、雑誌単独での成長には限界があるといえます。
3.63. カヤック<3904>によるビジネス書・社会書の英治出版子会社化
ゲームアプリなどの開発で知られるカヤックは2024年、ビジネス・社会書に強みを持つ英治出版の株式99.9%を取得しました。生涯学習やリスキリングなどの市場が伸びるなか、ビジネス書のコンテンツを活用し、オンライン学習やイベントなど新規サービスとの連携を図ると見られます。
3.64. YOZAN<6830>の飛鳥新社譲渡とコンテンツ事業からの撤退
無線通信のYOZANは2007年に飛鳥新社を子会社化しましたが、WiMAX事業が停滞しコンテンツ活用の展望が無くなったため、2008年に飛鳥新社を元の経営陣に譲渡しました。コンテンツ事業と親和性が高い通信ビジネスモデルを模索するケースでしたが、期待ほどの成果を得られなかった典型例です。
4. 事例から見る出版M&Aのパターンと特徴
このように多数の事例を俯瞰してみると、大きく次のようなパターンが浮かび上がります。
4.1. 出版取次や印刷会社による書店網・出版社買収
大日本印刷や凸版印刷のような印刷大手、または日本出版販売(日販)などの取次大手が書店チェーンや出版社を買収するケースです。従来の紙流通を補完しつつ、新たな付加価値サービスを展開しようという狙いが伺えます。
4.2. 外部業種からの参入と出版社の売却
IT企業(メディアドゥ、富士山マガジンサービスなど)や総合商社(三井物産)のように、出版関連のデジタルシフトやクロスメディア展開を重視して出版社買収を行うケースが増えています。一方、企業側の都合で出版部門を切り離す動き(廣済堂のように印刷事業へ特化する)も顕著です。
4.3. MBO・TOBによる非公開化の実例
幻冬舎やビジネス社のように出版社が単体でMBOを実施し非公開化を図る、あるいはファンドや親会社によるTOBで上場廃止になる例が増えています。大規模投資や迅速な経営判断が必要な現代では、上場のメリットよりも柔軟な経営を優先する場合があります。
4.4. 大手コンテンツ企業による海外企業・デジタル企業の買収
凸版印刷やソニーなど、海外で実績のある企業を買収して国際展開を加速する動きが目立ちます。日本市場の縮小を見越し、海外の成長市場に活路を求める動きは、今後さらに活発化すると予想されます。
4.5. 成長領域への投資と不採算部門の切り離し
廣済堂やRIZAPグループ、ノーリツ鋼機などが代表例です。利益が出ない出版部門を外部へ売却し、コア事業や新領域へリソースを集中する戦略が顕在化しています。
5. 出版業界M&Aのメリット・デメリット
5.1. メリット
- 経営資源の最適化
不採算部門を切り離し、資金や人材をコア事業・成長事業へ集中できる。 - シナジー創出
買い手側が出版のノウハウやブランドを得て、自社のコンテンツや流通網と組み合わせられる。 - スピーディーな事業拡大
ゼロから開発するより企業買収によって既存の顧客や販路、商品ラインナップを迅速に獲得できる。 - 事業継承問題の解決
後継者不足や資金難に苦しむ中堅・中小出版社が、大手企業の下で再建や拡大を目指す。
5.2. デメリット
- 企業文化の相違
出版社特有の編集プロセスや文化が、買い手企業と噛み合わず統合が難航するケースがある。 - 買収コストやリスク
過大な買収額を支払い、思うほどの収益が得られずのれん償却負担となることもある。 - 専門人材の流出
M&A後に編集者や作家が退社・契約解除し、コンテンツ力が急落する可能性。 - ブランド毀損のリスク
新親会社の経営方針が読者の反発を招き、出版社の長年のブランド価値が損なわれることがある。
6. 今後の展望と課題
6.1. デジタル化によるビジネスモデル変容
紙媒体の売上が縮小する一方で、電子書籍やオーディオブック、マンガアプリなどの市場はなお拡大を続けています。今後は出版物のデジタル化に加え、月額定額制やオンラインサロン的なコミュニティとの連携など、多様な収益モデルが登場すると考えられます。その際、新技術を持つ企業とのM&Aやアライアンスはますます重要となるでしょう。
6.2. コミュニティとファンビジネスの創出
書籍や雑誌は単に「読む」だけでなく、そのテーマを愛好するファンがコミュニティ化しやすい特性を持ちます。イベントやSNSを通じたファンダム形成がビジネスチャンスとなることから、放送局やIT企業が出版メディアを買収してファンの獲得を狙う動きが広がる可能性があります。
6.3. グローバル市場に向けた動き
日本のマンガやアニメ、ゲーム、小説といったコンテンツは世界的にも高い評価を受けています。翻訳版の需要も高まっており、今後は海外出版社やプラットフォームとの合弁や買収を通じてグローバル市場に進出する例が増えるでしょう。
6.4. 出版関連領域との連携(教育、映像、音楽など)
教育・学習分野ではオンライン講座や資格取得支援サービスが拡大しており、出版社が持つノウハウやテスト問題データは高い価値を持ちます。映像・音楽・ゲームとのクロスメディア展開も加速するため、異業種との連携を模索する動きがさらに増えると思われます。
7. まとめ:M&Aが描く出版の近未来像
出版業界は従来型の紙媒体ビジネスから脱却を迫られ、新たな収益モデルを模索してきました。そのなかで、M&Aは大きな役割を果たしてきています。多くの事例が示すように、**「事業の選択と集中」と「デジタル・新規分野への積極投資」**という2つの軸で出版企業は再編されているのです。
- 選択と集中: 廣済堂のように赤字続きの出版部門を切り離し、印刷や人材事業に集中する動き
- 積極投資: メディアドゥのように電子書籍取次の上流から下流までをM&Aで一気に押さえ、主導権を握る動き
こうした再編の波はまだしばらく続くものと思われます。特に印刷会社や新聞社などが保有する出版子会社が、将来的に売却されるケースは増えるでしょう。一方、書籍や雑誌、コミックのデジタル化はまだ伸びしろがあり、海外を含めた相互買収の可能性も十分に考えられます。
さらに、出版や印刷企業だけでなく、コンサルティング会社、IT企業、メーカー、金融機関など異業種からの参入や、社内ベンチャーの分離独立、MBOなど、多様なパターンが混在するのも出版業界の特徴になりつつあります。消費者が情報を得る手段が広がる今だからこそ、知識や情報を編集し価値を提供する出版社の役割は依然として大きいといえます。
M&Aを通じて生き残りを図る出版企業と、新たなビジネスチャンスを求めて出版業界に参入する企業の双方が混ざり合い、出版業界の構造は大きく変貌を遂げています。印刷・取次・流通・編集の垂直統合を目指す動きや、IT・デジタル企業との水平的連携など、出版の垣根を越えたコラボレーションが今後も活発化していくでしょう。

株式会社M&A Do 代表取締役
M&Aシニアエキスパート・相続診断士
東京都昭島市出身。慶應義塾大学理工学部を卒業後、大手M&A仲介会社にて勤務し、その後独立。これまで製造業・工事業を中心に友好的なM&Aを支援。また父親が精密板金加工業、祖父が蕎麦屋、叔父が歯科クリニックを経営し、現在は父親の精密板金加工業にも社外取締役として従事。