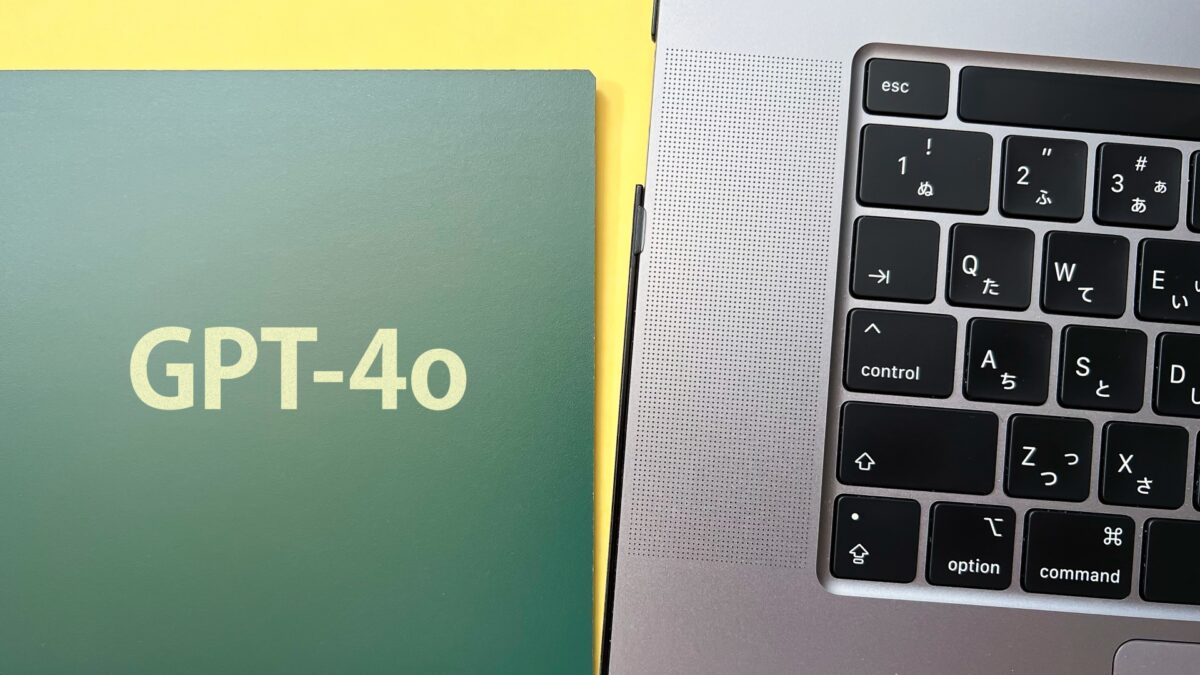- 生成AI業界におけるM&Aの概況と今後の展望
- 1. 東京通信グループ<7359>、画像生成サービス「Picrew」運営のテトラクローマを子会社化
- 2. ワールド<3612>、持ち分法適用関連会社でファッション業界向けDX支援のOpenFashionを子会社化
- 3. データセクション<3905>、The ROOM4Dからデータ分析コンサルティング・システム開発事業などを取得
- 4. データ・アプリケーション<3848>、生成AI活用システム受託開発のWEELを子会社化
- 5. トリプルアイズ<5026>、自動車向け機械・ITシステム設計開発のBEXを子会社化
- 6. コマースOneホールディングス<4496>、生成AIによるコンテンツクリエイティブ制作の既読を子会社化
- 7. クリーク・アンド・リバー社<4763>、生成AIクリエイター支援のリヴァイを子会社化
- 8. サイオス<3744>、子会社の金融機関向け経営支援システム事業などを住信SBIネット銀行<7163>に譲渡
- 9. エフ・コード<9211>、生成AIコンサルのSpinFlowを子会社化
- 10. エルテス<3967>、放送局向けアプリ開発のクロスオーバーソリューションズを子会社化
- 11. クラウドワークス<3900>、生成AI活用した記事作成ツールなどを開発するAI techを子会社化
- 12. AHCグループ<7083>、IT活用による福祉支援事業のパパゲーノを子会社化
- 13. HEROZ<4382>、bizyから営業コンサルティング・テレマーケティング事業を取得
- 14. AVILEN<5591>、生成AI関連システム受託開発のLangCoreを子会社化
- 生成AI業界M&Aの全体的な傾向と展望
- まとめ
生成AI業界におけるM&Aの概況と今後の展望
近年、生成AI(Generative AI)は、テキストや画像、さらには音声・動画といった多種多様なコンテンツを自動生成する技術として大きな注目を集めております。特にチャットボットや画像生成サービスなどに代表されるように、さまざまな企業が生成AIを活用することでビジネスの高度化や新規事業の創出を図っています。そうした中で、企業同士が互いの強みを組み合わせてシナジーを生み出すM&A(合併・買収)は、生成AI分野において急速に増加傾向にあります。
本記事では、2023年から2025年にかけて公表された国内の生成AI関連企業のM&A事例を取り上げ、その背景や目的、そして今後の展望について解説いたします。生成AI技術がどのように産業へ浸透し、各社がどのようなシナジーを求めているのかを、できるだけ丁寧にご紹介してまいります。
生成AI業界の背景と成長ドライバー
まず初めに、生成AIが注目される背景について整理いたします。AI技術全般が注目され始めたのは、機械学習やディープラーニング技術の発展が大きく関係しており、特に2010年代後半からはさまざまな研究成果が実用化フェーズに移行してきました。その中でも生成AIは、従来の「判断」や「分類」が中心だったAI技術とは異なり、クリエイティブなコンテンツを「創り出す」ことができる点が特徴です。この特性は、エンターテインメント領域のみならず、広告・マーケティング、開発支援、教育、ヘルスケアなどの幅広い業種で革新的な価値を提供すると期待されています。
具体的な成長ドライバーとしては、
計算資源(GPUやクラウドサービス)の進化
大規模学習に必要となるコンピューターリソースがクラウド上で容易に利用可能となり、大規模モデルの開発コストが低減しました。
大規模言語モデル(LLM: Large Language Models)の普及
ChatGPTやその他のLLMが登場し、自然言語生成のレベルが飛躍的に向上しました。
画像生成技術の発展
GAN(Generative Adversarial Networks)をはじめとする先端技術により、高精度な画像や動画の自動生成が可能となりました。
ビジネスニーズの多様化
コンテンツの大量生産や、コスト効率を高めるための自動化など、企業ニーズが高まり、生成AIを導入する動きが加速しました。
これらの要素が相互に作用し合い、生成AI分野は国内外問わず急激な成長を続けています。その結果、市場規模拡大に伴い競合も激しくなり、技術獲得や顧客基盤の強化を目的としたM&Aが頻繁に行われるようになっているのです。
国内におけるM&Aの特徴
国内企業は、生成AI分野のスタートアップや専門企業を早期に取り込みたいという思惑を強く持ち始めています。AI関連技術は日進月歩であり、社内で一から開発体制を整えるには時間もコストもかかります。一方で、既存のマーケティング領域やDX事業を展開している大手・中堅企業が、成長分野である生成AIのケイパビリティを早期に獲得する手段としてM&Aを選択するケースが増えているのです。
以下では、具体的な国内M&A事例をご紹介し、それぞれの取引の狙いと今後の展開について詳しく述べてまいります。
1. 東京通信グループ<7359>、画像生成サービス「Picrew」運営のテトラクローマを子会社化
取引概要
- 発表日:2023年11月7日
- 取得企業:東京通信グループ
- 被取得企業:テトラクローマ(売上高3億1900万円、営業利益1億9300万円、純資産2億7800万円)
- 取得価額:5億7800万円(今後2年間の業績に応じて最大4000万円を追加支払)
- 取得予定日:2023年12月1日
テトラクローマが運営する「Picrew(ピクルー)」は、クリエーター投稿のパーツを自由に組み合わせ、ユーザーがオリジナルのイラストやアイコン、キャラクターを生成するサービスとして有名です。国内外200カ国以上で利用され、累計利用者は1億人を超えるとのことで、非常に高い知名度とユーザーベースを有しています。
狙いとシナジー
東京通信グループは、広告事業やメディア事業をはじめとしたデジタル領域でのビッグデータを多数保有しており、それを活用することで生成AIサービスのさらなる発展を図りたい意向です。また、Picrewという既に確立したプラットフォームと東京通信グループのマーケティングノウハウが組み合わさることで、ユーザーエンゲージメント強化や新規ビジネスモデルの開発につながる可能性があります。
具体的には、ユーザーが生成したキャラクターやイラストをSNSやアプリで二次利用する際のデータ分析や、広告配信への活用、あるいはゲーム会社との連携による新たなコンテンツ提供など、多角的な展開が見込まれます。東京通信グループのもつ顧客企業とのパイプを活かして、大手企業が独自キャラクターを生成AIを使って大量かつ容易に制作できるサービスを展開するなど、さまざまなシナジーが期待されます。
2. ワールド<3612>、持ち分法適用関連会社でファッション業界向けDX支援のOpenFashionを子会社化
取引概要
- 発表日:2025年1月15日
- 取得企業:ワールド
- 被取得企業:OpenFashion(2014年設立)
- 取得価額:非公表
- 取得予定日:2025年2月28日
ファッション業界大手のワールドは2018年よりOpenFashionに出資し、持ち分法適用関連会社として参画していましたが、今回は追加取得により株式比率を100%とし、子会社化を決定しています。
ファッション業界と生成AIの関係
ファッション業界では、生成AIを活用したデザイン自動化や、ECサイトでのバーチャル試着サービス、データを活用したトレンド予測などが盛んに行われるようになっています。OpenFashionはDX(デジタルトランスフォーメーション)のソリューションプロバイダーとして、これらの技術とファッション企業をつなぐ架け橋的な役割を果たしてきました。
ワールドとしては、グループ内デジタル事業を加速させると同時に、外部のファッション企業や関連産業にも横展開できるデジタルプラットフォームの構築を目指しています。なお、OpenFashionが提供中の生成AI支援ツールは、子会社化に伴い新会社へ移管される予定とのことで、今後はグループ外へも積極的にサービスを提供していく方針のようです。
3. データセクション<3905>、The ROOM4Dからデータ分析コンサルティング・システム開発事業などを取得
取引概要
- 発表日:2023年7月28日
- 取得企業:データセクション
- 被取得事業:The ROOM4Dのデータ分析コンサルティング・受託開発事業、子会社The ROOM DoorのSES事業
- 取得価額:非公表
- 取得予定日:2023年9月1日
データセクションはSNS分析やビッグデータ解析を得意とする企業として知られており、近年は生成AI分野のプロジェクトにも注力しています。一方、The ROOM4Dおよびその子会社The ROOM Doorの当該事業は、データ分析・関連システム開発やSES事業を行っており、今後の成長が期待できる領域です。
成長性と人材確保の意図
生成AI分野は、技術開発だけでなく、運用やコンサルティングに熟練したエンジニアやデータサイエンティストの確保が不可欠です。データセクションは、本事業取得によって、エンジニアリングリソースを大幅に拡充し、競争力を高める狙いがあります。データ分析や機械学習の知見が蓄積しているThe ROOM4Dグループの人材が加わることで、新規事業開発のスピードアップや提供サービスの多様化が期待されます。
4. データ・アプリケーション<3848>、生成AI活用システム受託開発のWEELを子会社化
取引概要
- 発表日:2024年6月25日
- 取得企業:データ・アプリケーション
- 被取得企業:WEEL(売上高6880万円、営業利益424万円、純資産274万円)
- 取得価額:非公表
- 取得予定日:2024年7月26日
- 取得手法:株式取得(88.46%)+簡易株式交換(11.54%)
データ・アプリケーションは、データ連携やETL(Extract, Transform, Load)ソフトウェア等の開発を手がける企業であり、2024年からの3カ年中期経営計画の中で「事業領域の拡大・開拓」を掲げています。
目的と期待される効果
WEELが持つ生成AI活用のシステム受託開発・コンサルティング領域のケイパビリティを取り込むことで、データ・アプリケーションが保有する既存顧客(主にエンタープライズ企業)のニーズに、新たな付加価値を提案できる体制を強化します。具体的には、データ連携基盤と生成AIを組み合わせることで、
大量データを自動的に学習し、リアルタイムで需要予測や異常検知を行うソリューション
DX推進に向けたコンサルティングから開発運用までのワンストップ体制
などを構築することが可能になります。こうした統合的なサービス提供が実現すれば、競合他社との差別化が図れ、かつ顧客ロイヤルティを高められると期待されます。
5. トリプルアイズ<5026>、自動車向け機械・ITシステム設計開発のBEXを子会社化
取引概要
- 発表日:2024年5月27日
- 取得企業:トリプルアイズ
- 被取得企業:BEX(売上高15億5000万円、営業利益8600万円、純資産4億4300万円)
- 取得価額:6億5300万円
- 取得予定日:2024年7月1日
BEXは1980年創業の老舗企業で、自動車分野における機械設計やITシステムの開発を行っています。トヨタ自動車グループとの取引基盤が安定しており、技術力にも定評があります。
自動運転やDX分野への活用
近年、自動車業界では自動運転技術やMaaS(Mobility as a Service)の普及を背景に、生成AIが果たす役割が拡大しています。具体的には、自動運転用のアルゴリズム開発や、設計データの自動生成、シミュレーション工程の自動化など、さまざまな領域でAI活用が進むと見込まれています。
トリプルアイズとしては、BEXの自動車分野における豊富な開発実績と、自社が得意とするAI技術を組み合わせることで、今後の自動車産業のDXをリードするポジションを目指す考えです。具体的には、車両設計の標準化や専門タスクの自動生成、生産工程の効率化につながるAIシステムを開発し、国内外メーカーへの提供を拡大させる可能性があります。
6. コマースOneホールディングス<4496>、生成AIによるコンテンツクリエイティブ制作の既読を子会社化
取引概要
- 発表日:2024年11月14日
- 取得企業:コマースOneホールディングス
- 被取得企業:既読(売上高1840万円、純資産△1730万円)
- 取得形態:第三者割当増資の引受(取得比率60%)
- 取得価額:非公表
- 取得予定日:2024年11月14日
既読は2019年設立で、マーケティング戦略設計からクリエイティブ制作までを一貫して提供する企業です。特徴的なのは、生成AIを活用してSNS広告やECサイト向けに最適化したクリエイティブを効率的に制作できる点です。
EC事業者向けAIサービス強化
コマースOneホールディングスが手がけるEC支援事業においては、商品写真の編集や広告バナーの作成など、クリエイティブ制作の工数が大きな負担となっています。既読を取り込むことで、このクリエイティブ制作を大幅に自動化・効率化し、自社サービスの付加価値を高める狙いがあるとみられます。
加えて、生成AI技術をさらにブラッシュアップすることで、EC店舗の運営者が自らAIを使ってマーケティング施策を企画実行できるプラットフォーム構築にもつながる可能性があります。
7. クリーク・アンド・リバー社<4763>、生成AIクリエイター支援のリヴァイを子会社化
取引概要
- 発表日:2024年2月29日
- 取得企業:クリーク・アンド・リバー社
- 被取得企業:リヴァイ(横浜市)
- 取得価額:非公表
- 取得予定日:2024年3月13日
リヴァイは2023年5月設立の比較的新しい企業ですが、生成AIに関する情報発信や勉強会(「リヴァイ塾」)の運営、コンサルティング、人材紹介など、生成AIを活かした幅広いサービスを展開しています。
クリエイターと生成AIの融合
クリーク・アンド・リバー社はクリエイター派遣や代理業務で多くの実績をもつ企業であり、大手広告代理店や放送局などと取引関係があります。今回のリヴァイ買収により、AIを使ったクリエイティブ制作を行う人材の育成や派遣が円滑になると期待されます。
また、すでにエージェンシー契約を結んでいるクライアント企業に対して、生成AIの導入コンサルティングやワークフローの自動化など、高付加価値のサービスを提供できるようになります。広告・映像制作現場での生成AI活用は今後さらに需要が高まるとみられており、同社の事業領域拡大につながるでしょう。
8. サイオス<3744>、子会社の金融機関向け経営支援システム事業などを住信SBIネット銀行<7163>に譲渡
取引概要
- 発表日:2024年10月4日
- 譲渡企業:サイオス(子会社のサイオステクノロジー保有事業を会社分割)
- 譲受企業:住信SBIネット銀行
- 譲渡価額:5億円
- 譲渡予定日:2024年12月2日
サイオスは今回、子会社サイオステクノロジーが手がける金融機関向け経営支援システム事業を別会社(プロフィットキューブ)に切り出した上で、プロフィットキューブ株式を住信SBIネット銀行に譲渡する形をとっています。
事業の選択と集中
この譲渡の背景には、サイオスがSaaSやサブスクリプション型ビジネス、そして生成AI分野への注力を強めたいという戦略があります。金融機関向け経営支援システムは歴史ある事業ですが、コロナ禍を経て金融機関の業務形態やニーズが大きく変化する中で、より専門性の高いプレーヤー(今回のケースでは住信SBIネット銀行)が活用したほうが事業価値を高めやすいと判断したものと思われます。
サイオスはリソースを最先端のAI事業へ振り向け、DX支援や生成AIサービスの提供など、成長分野に経営資源を集中することで収益拡大を狙う構えです。
9. エフ・コード<9211>、生成AIコンサルのSpinFlowを子会社化
取引概要
- 発表日:2024年11月5日
- 取得企業:エフ・コード
- 被取得企業:SpinFlow(売上高2億8800万円、営業利益1億100万円、純資産1億円=2024年4~9月の半期実績)
- 取得比率:50.1%
- 取得価額:1億8100万円
- 取得予定日:2024年11月5日
SpinFlowは2024年4月設立の企業で、生成AIを活用したコンサルティングやリスキリング研修サービスを提供しています。設立から日が浅いながらも、次世代スキル教育の需要増を背景に急速にサービス提供規模を拡大中です。
エフ・コードのDX推進との連携
エフ・コードはマーケティングオートメーションやUX改善など、企業のデジタルマーケティングを支援するサービスを展開しています。SpinFlowの生成AIノウハウを獲得することで、顧客企業が抱えるデジタル人材不足や業務改善ニーズにより総合的に対応できるようになると期待されます。
特に、リスキリング研修の需要は多くの企業が直面する課題であり、AIを使いこなせる人材の育成支援は、今後の重要テーマとなっています。エフ・コードはSpinFlowを子会社化することで、この領域でのビジネスチャンスを確実に捉えたい考えです。
10. エルテス<3967>、放送局向けアプリ開発のクロスオーバーソリューションズを子会社化
取引概要
- 発表日:2024年11月21日
- 取得企業:エルテス傘下企業
- 被取得企業:クロスオーバーソリューションズ(盛岡市、売上高2億9700万円、営業利益7010万円、純資産9670万円)
- 取得価額:4億500万円
- 取得予定日:2024年11月28日
クロスオーバーソリューションズは2017年設立で、放送局向けアプリ「ReTSTA(リトスタ)」を主力に、全国11の放送局に導入実績をもっています。プッシュ通知やアンケート企画、災害時のライブ配信など、テレビ局独自のサービスをアプリ内で完結できるのが強みです。
音声読み上げ生成AIとのシナジー
エルテス傘下のJAPANDXは放送局向け音声読み上げAIの開発を進めており、クロスオーバーソリューションズのアプリ技術と掛け合わせることで、より高度なサービスを放送局に提供できるようになります。具体的には、番組の一部を自動で音声化して配信する機能や、ユーザーの属性に合わせたパーソナライズ音声コンテンツの配信などが挙げられます。
放送業界はローカル局を含めDXが急務となっており、これらの技術を導入することで放送局のファンコミュニティ強化や新たな収益源創出が期待できます。エルテスとしても、AI技術と放送局のプラットフォームを融合させることで、全国規模のビジネス拡大を図る狙いがあります。
11. クラウドワークス<3900>、生成AI活用した記事作成ツールなどを開発するAI techを子会社化
取引概要
- 発表日:2024年3月27日
- 取得企業:クラウドワークス
- 被取得企業:AI tech(売上高1450万円、営業利益△588万円、純資産△502万円)
- 取得形態:株式交換
- 取得予定日:2024年4月25日
- 株式交換比率:クラウドワークス1:AI tech6.0233
AI techは2022年1月設立で、生成AIを活用した記事作成ツール「オーダーメイド AI」を展開しています。クラウドワークスは国内最大級のクラウドソーシングプラットフォームを運営しており、多くのフリーランスや企業と契約しているのが強みです。
クラウドソーシング事業との統合効果
生成AIを用いた記事作成支援ツールは、クラウドソーシング市場において非常に有用です。特に、ライティング案件では受注するワーカー(ライター)と発注する企業の間で、品質や納期が重要視されます。AI技術を活用することで、ライターの作業効率向上や文章品質の均一化が期待できます。
また、クラウドワークス上で新たなサービスを開始することで、既存ユーザーの利便性向上や新規顧客獲得につながるとみられます。クラウドワークスはすでに多様な業種のフリーランスが登録しており、そこにAIのサポートが加わることで、案件の幅や対応力が格段にアップするでしょう。
12. AHCグループ<7083>、IT活用による福祉支援事業のパパゲーノを子会社化
取引概要
- 発表日:2024年11月15日
- 取得企業:AHCグループ
- 被取得企業:パパゲーノ(売上高3910万円、営業利益△423万円、純資産371万円)
- 現在の持株比率:10.9% → 100%
- 取得価額:1億1680万円
- 取得予定日:2024年12月1日
パパゲーノは2022年3月に設立されたベンチャー企業で、福祉事業所向けにITを活用した業務支援サービスを提供しています。特に、生成AIなど先端技術を活用し、福祉現場の負担軽減を目指す「AI支援さん」というアプリを開発・運営しています。
福祉業界DXの加速
AHCグループは保育園運営支援や障害者福祉支援などを幅広く手がけており、今後は福祉領域のDXをさらに進めるためにパパゲーノを完全子会社化することを決定しました。障害者向け就労継続支援B型事業所の運営経験ももつパパゲーノを取り込むことで、IT・AI技術と福祉支援の双方を高いレベルで融合できる体制が整います。
少子高齢化が進む日本では、福祉・介護分野の人材不足が深刻化する中で、AIやITを活用した業務効率化ニーズが増大しています。今回のM&Aは、社会課題の解決という観点からも大きな意義があると言えるでしょう。
13. HEROZ<4382>、bizyから営業コンサルティング・テレマーケティング事業を取得
取引概要
- 発表日:2024年8月6日
- 取得企業:HEROZ傘下のVOIQ
- 被取得事業:bizyの営業コンサルティング事業・テレマーケティング事業
- 取得価額:4000万円
- 取得予定日:2024年8月9日
HEROZは将棋AI「Ponanza」の開発など、AI技術の高度な研究開発で知られている企業です。傘下のVOIQはAIによる音声通話自動化や営業支援に強みを持っています。
営業支援×生成AIのシナジー
営業コンサルティングやテレマーケティング領域は、スクリプトや顧客情報の管理など、人間が行うには煩雑な作業が多く存在します。生成AIを活用すれば、問い合わせ内容に応じた応答をリアルタイムに提供したり、顧客情報を分析して次に取るべきアクションを自動提案するといった高度なサポートが期待できます。
今回の事業取得によって、VOIQは営業活動の効率化・自動化をさらに押し進めることが可能になります。特に、多岐にわたる営業シナリオをAIが学習することで、業務コスト削減や成約率向上につながるサービスを幅広い業界へ提供できるようになるでしょう。
14. AVILEN<5591>、生成AI関連システム受託開発のLangCoreを子会社化
取引概要
- 発表日:2024年10月11日
- 取得企業:AVILEN
- 被取得企業:LangCore(売上高7380万円、営業利益4590万円、純資産5310万円=2024年1~6月半期分)
- 取得価額:4億500万円
- 取得予定日:2024年11月30日
LangCoreは2023年6月に設立されたAIベンチャーで、課題特定からアプリケーション開発まで一貫して提供できるのが特徴です。AVILENはAI教育やAIコンサルティングで実績を積んでおり、LangCoreを取り込むことで生成AI関連の受託開発力を大幅に強化します。
総合AIサービス企業への布石
AVILENは企業向けAI人材育成サービスを大きな収益源としている一方、受託開発のリソースは比較的限定的でした。LangCoreのチームを取り込むことで、クライアント企業の課題抽出からPoC(概念実証)、システム開発・運用保守までワンストップで提供できる体制を構築できるようになります。
生成AIは導入企業が急増しているものの、開発から運用までを包括的に支援できる専門家はまだ十分ではありません。AVILENはこうしたビジネスチャンスを見越して、LangCoreの買収に踏み切ったと考えられます。
生成AI業界M&Aの全体的な傾向と展望
1. 技術獲得だけでなく人材確保がカギ
今回ご紹介した事例を見ても、生成AI関連サービスを提供する企業の買収・資本提携は、単に技術や特許を獲得するだけでなく、そこで働くAIエンジニアやデータサイエンティストといった高度な人材を確保するという意味合いが非常に大きいことがわかります。特に日本国内では、AI人材の需要に対して供給不足が続いており、大手企業が新規事業を立ち上げる際には、M&Aが人材獲得の近道となっているのです。
2. DX推進の文脈での需要拡大
企業がDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進する中で、データの利活用が避けては通れないテーマとなっています。その結果、大量のデータを活用してクリエイティブな成果物を生み出す生成AIには強い期待が寄せられています。各社は自社の既存事業との親和性を高めるために、専門性をもつスタートアップや中小企業を積極的に取り込もうとしており、今後もこの流れは加速していくと考えられます。
3. 社会課題解決型のM&Aも増加
特に福祉・介護分野のように人材不足が深刻な業界では、生成AIやロボティクスの導入による効率化が社会課題の解決につながるため、今後も積極的なM&Aが期待されます。AHCグループによるパパゲーノ子会社化のように、単なる事業拡大ではなく、社会的意義を伴う買収も増えていくでしょう。
4. 今後の課題と注意点
もっとも、生成AIの活用にあたっては、著作権や個人情報、データの偏りによるバイアスなど、さまざまなリスクも存在します。企業が生成AIを導入する際には、これらの法的リスクや倫理的懸念に対して適切に対応するガバナンス体制が求められます。M&Aを行う企業も、被取得企業のコンプライアンスや技術の透明性をしっかりと評価する必要があります。
さらに、生成AI分野の技術進歩は極めて速く、今日の技術優位が明日には陳腐化する可能性もあります。そのため、買収後の研究開発投資や人材育成を継続的に行い、獲得した企業や事業との統合作業をいかにスムーズに進めるかが重要となるでしょう。
まとめ
ここ数年で公表された国内の生成AI関連M&A事例を概観すると、さまざまな業界で生成AI技術を取り込む動きが活発化していることがはっきりとわかります。広告・マーケティングやメディアだけでなく、自動車、ファッション、福祉といった領域にも生成AIが広がりつつあり、今後も産業構造そのものを変える大きな力となることが予想されます。
企業が生成AIを導入する際には、多角的な検討が必要です。大企業の側はスピーディに技術・人材を獲得できるM&Aや資本提携の手法を取るケースが増え、中小・スタートアップの側も、資金力や販売チャネルをもつ大企業との連携で事業をスケールアップするチャンスとなっています。一方で、技術や人材の取り込みに成功しても、組織文化の違いや開発方針の不一致などで、必ずしも思うようにシナジーが得られないリスクも存在します。
そのため、買い手企業には、生成AI技術を単に「買う」だけでなく、自社のどの事業・領域とどう組み合わせれば真の価値を引き出せるのかを明確に設計する力が求められます。また、売り手企業側にとっても、買収後に自社の技術やサービスがどのような形で発展するのかをしっかりイメージし、条件交渉に臨むことが重要です。
これから先、生成AI技術はさらに高機能化・多機能化していくと予想され、M&A市場も一層活況を呈する可能性が高いでしょう。企業の経営戦略やイノベーション創出の現場で、生成AIがどのように使われ、それによってどのような新たな価値が生まれていくのか。今回ご紹介した各事例の行方を追いながら、今後の生成AI業界の動向に注目してまいりたいと思います。

株式会社M&A Do 代表取締役
M&Aシニアエキスパート・相続診断士
東京都昭島市出身。慶應義塾大学理工学部を卒業後、大手M&A仲介会社にて勤務し、その後独立。これまで製造業・工事業を中心に友好的なM&Aを支援。また父親が精密板金加工業、祖父が蕎麦屋、叔父が歯科クリニックを経営し、現在は父親の精密板金加工業にも社外取締役として従事。