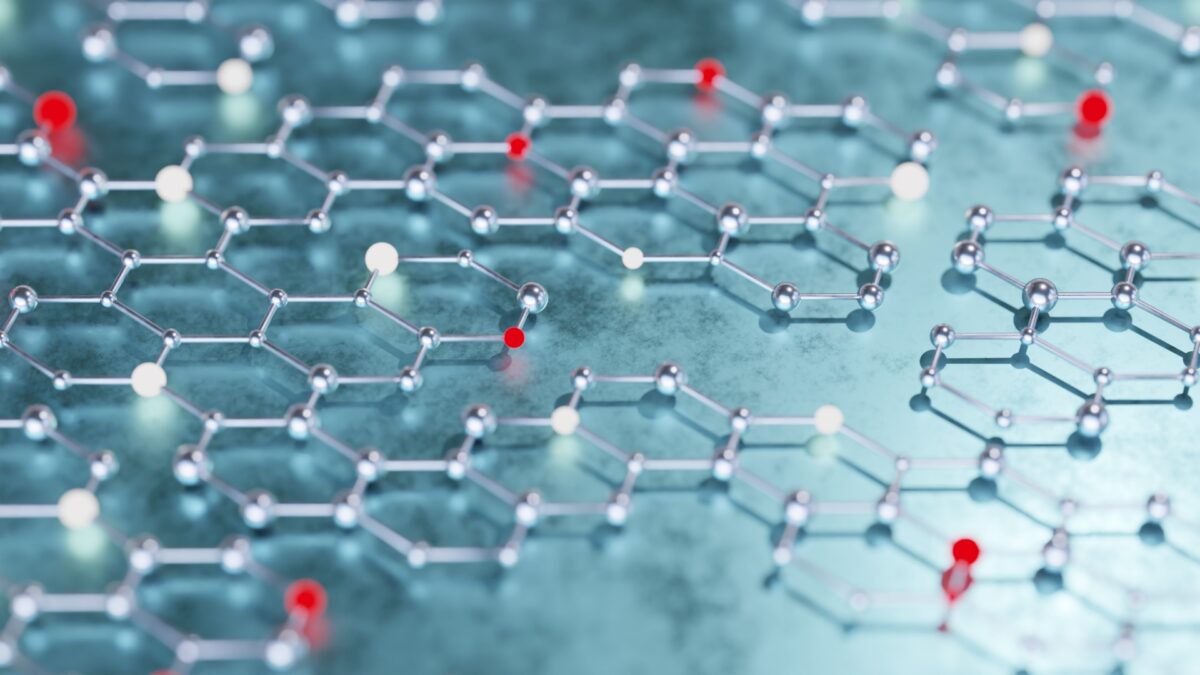1. はじめに:創薬業界におけるM&Aの位置づけ
医薬品の研究開発には膨大なコストがかかり、かつ成功率は決して高くありません。世界的には10~15年単位の長い年月と莫大な費用を投じても、最終的に承認されるのは一部の化合物だけという現実があります。こうしたハイリスク・ハイリターンの業界において、企業は自社のパイプライン(開発中の新薬候補)を強化するために、他社の技術や研究開発力、あるいはすでに実績のある医薬品を取得する手段としてM&Aを積極的に活用してきました。
とりわけ近年は、ブロックバスター級(世界年間売上高10億ドル以上)の新薬を生み出すには、従来の枠にとらわれないオープンイノベーションが必須とされます。その一方で特許切れ(パテントクリフ)による収益の急激な落ち込みを回避するため、製薬企業は外部の有望ベンチャーを買収したり、大型の国際M&Aを行うことで、研究開発領域をシナジー的に拡充させようとしています。このように、創薬業界におけるM&Aは企業の将来に直結する重要な戦略的選択となっています。
2. 背景と動機:なぜM&Aが重要視されるのか
2-1. 新薬開発コストの増大とリスク分散
新薬を一つ世に出すまでにかかる研究開発費は、近年の試算では数千億円に上るともいわれています。また、第3相臨床試験まで進んだとしても、承認に至らないケースは少なくありません。成功すれば巨大な利益を得る可能性があるものの、失敗すれば多大な投資が無駄になってしまいます。こうしたリスクの高さから、大手製薬企業は一社で全てのプロジェクトを抱えるのではなく、M&Aを通じて外部のパイプラインを取り込み、リスクを分散する動きが加速しています。
2-2. ポートフォリオ強化とニーズの多様化
医療ニーズはがん、中枢神経系疾患、免疫疾患、遺伝性の希少疾患など、極めて多岐にわたります。パイプラインを自前だけでカバーするには限界がありますが、M&Aで専門領域を得意とするバイオベンチャーを取り込めば、企業としてのポートフォリオが一気に充実します。また、創薬技術面でも低分子医薬、抗体医薬、遺伝子治療や細胞治療など多彩なプラットフォームが開発されています。こうした多様な領域へ同時にチャレンジするためにも、M&Aは魅力的な手段となっています。
2-3. グローバル競争とスピードの加速
医薬品産業は国境を超えたビジネスです。各国の規制や特許制度などは異なりますが、世界中の患者さんを対象に製品を販売するグローバル視点が欠かせません。国際競争が激しくなる中、創薬プロセスをいかにスピーディーに進め、いかに早く承認を得るかが成否を左右します。そのため、研究開発や申請ノウハウを持つ海外企業を直接買収し、現地拠点を確立することが、グローバル展開をスムーズにするメリットになります。
2-4. オープンイノベーションと外部連携
近年の創薬分野では、産学連携やスタートアップとの協業がさらに促進されています。製薬大手がベンチャー企業に出資したり、共同開発契約を結んだりするのは一般的となりました。さらに研究開発の上流から後期臨床試験までを包括的に自社だけで行うよりも、有望な技術を持つ企業を買収してしまう方が効率的と判断するケースが増えています。M&Aはオープンイノベーションの最終手段ともいえます。
3. 国内創薬M&Aの特筆すべき特徴
3-1. 日本企業のグローバル化と事業領域拡大
2008年以降、日本の大手製薬企業による海外企業買収が活発化しました。武田薬品の米ミレニアム・ファーマシューティカルズ買収(2008年)、そして2019年にはアイルランドの製薬大手シャイアーを6兆円超の巨費で買収し、大きなインパクトを与えました。それ以前も第一三共によるランバクシー買収など、日本企業が海外大手を手に入れる動きが広がりました。その背景には、国内市場の伸び悩みや高齢化による医療費圧迫などで、早い段階から海外売上比率の向上を目指す必要に迫られていたことが挙げられます。
3-2. 希少疾患・がん領域・再生医療など先端領域への注力
新薬開発で主戦場となるのはがんや免疫領域ですが、近年は希少疾患、再生医療、遺伝子治療、核酸医薬といった先端領域が特に注目を集めています。こうした難易度の高い領域では、研究開発の初期から知見を深めているバイオベンチャーのノウハウが極めて重要です。そこで、国内大手製薬企業がベンチャーを買収して一体化し、スピーディーな研究開発を目指すケースが増えました。
3-3. 大型M&Aとベンチャー買収の二極化
一方で、シャイアーのような数兆円規模の大型M&Aがある一方、100億~数百億円規模、あるいはそれ以下の比較的小規模なM&Aも多数行われています。とりわけ創薬ベンチャーや特定の技術プラットフォームを有する企業を取り込む手段としては、数十億円程度での買収が多く見られます。M&Aによってパイプラインとプラットフォーム技術を同時に獲得できることは、大手にとっても大変魅力的です。日本国内のみならず、欧米、アジアなど多地域にわたり買収ターゲットが広がっている点も特徴的です。
4. 主要M&A事例の概観
ここからは、近年実際に行われた代表的なM&A案件を概観いたします。それぞれの買収目的、特徴的な契約形態(アーンアウト条項やTOBなど)、事後の事業展開について簡単に整理します。
4-1. 武田薬品工業:ニンバス・ラクシュミ買収、シャイアー買収を経て
- ニンバス・ラクシュミ買収(2022年12月発表)
武田薬品は米国の創薬ベンチャー「ニンバス・セラピューティクス」の子会社ニンバス・ラクシュミを、約40億ドルで買収しました。標的は免疫疾患領域で期待される経口阻害薬プログラム「NDI‐034858」。今後の開発進捗や売上実績に応じて、追加の成功報酬が支払われる仕組みとなっています。
武田は2019年に巨額を投じてアイルランドの製薬大手シャイアーを買収して以来、財務的な課題やパイプラインの拡充に注力してきましたが、今回のニンバス買収は再び米国ベンチャーへの大型投資といえます。
4-2. 大塚ホールディングス:アステックス・ファーマシューティカルズ、Mindset Pharma、ジュナナ・セラピューティクスなど
- アステックス買収(2013年)
大塚製薬を中核とする大塚HDは、米国バイオベンチャーのアステックスをTOB(株式公開買付)で買収。フラグメント分子設計という技術領域を取り込み、がん領域のパイプラインを強化しました。 - Mindset Pharma買収(2023年)
カナダの創薬スタートアップ「Mindset Pharma」を約91億円で買収。次世代向精神薬の研究開発を行う企業であり、5‐HT2Aアゴニストを用いたうつ・PTSD領域の治療薬に期待がかかります。 - ジュナナ・セラピューティクス買収(2024年発表)
米ボストンの創薬企業ジュナナを約1208億円で買収。自己免疫疾患や希少疾患をターゲットにした低分子阻害剤パイプラインを獲得。さらに進捗次第で最大490億円を追加支払いする契約構造です。
4-3. 大日本住友製薬:ロイバント・サイエンシズ、ボストン バイオメディカルの買収
- ロイバント買収と戦略提携(2019年)
欧州創薬ベンチャー「ロイバント・サイエンシズ」との戦略提携で、ロイバント本体への出資とともに新薬開発子会社5社を買収。婦人科、希少疾患、遺伝子治療など幅広い領域のパイプラインを取り込みました。 - ボストン バイオメディカル買収(2012年)
がん幹細胞に特化した研究開発を進める米国ボストン バイオメディカルを子会社化。将来的に大きな収益が見込める領域に向けた先行投資として注目を集めました。
4-4. 富士フイルムホールディングス:Cellular Dynamics買収
- iPS細胞開発・製造企業の買収(2015年)
富士フイルムは米国バイオベンチャー「Cellular Dynamics International, Inc.」をTOBで買収し子会社化。写真フィルム技術で培った精密化学のノウハウを再生医療・創薬支援に転用し、再生医療分野へ積極参入しています。
4-5. 日清紡HD・エレコム関連のディー・クルー・テクノロジーズ買収
- 先端技術の補完(2022年)
日清紡ホールディングスはエレコム傘下のディー・クルー・テクノロジーズを子会社化。AIや量子コンピューター、創薬向けカスタムプロセッサーといった先端技術の開発経験を活かし、マイクロデバイス事業とのシナジーを狙っています。
4-6. その他事例(免疫生物研究所、明治HD、三洋貿易、新日本科学、塩野義製薬など)
- 免疫生物研究所:スカイライト・バイオテック買収(2013年)
生活習慣病領域の研究・創薬支援を行うスカイライト・バイオテックを子会社化。今後も高まる生活習慣病領域への需要を見越した動きです。 - 明治HD:化血研のワクチン事業買収(2017年発表)
化血研による不適切製造問題を受け、新会社KMバイオロジクスを設立する形での事業再編。国内ワクチン需要が高まる中での再編案件です。 - 三洋貿易:KOTAIバイオテクノロジーズ買収(2023年)
バイオ創薬支援・遺伝子解析受託を行う企業を子会社化してバイオ関連事業を強化。 - 新日本科学:Satsuma Pharmaceuticals買収(2023年)
偏頭痛薬の開発を手がけるナスダック上場のバイオベンチャーをTOBで子会社化し、世界的な開発権を獲得。 - 塩野義製薬:UMNファーマ買収(2019年)
ワクチン事業参入に向けてバイオ医薬品メーカーをTOBで子会社化。 - …など多数事例があります。
5. 詳細事例解説:最近の代表的なM&A動向
ここでは特に2022年~2024年に発表された新しい買収案件を取り上げ、その背景や特徴に触れます。
5-1. 大塚HDとカナダMindset Pharmaの買収
概要
- 大塚HDの子会社である大塚製薬が米国現地法人を通して約91億5400万円でMindset Pharmaを買収
- MindsetはうつやPTSD向けの次世代向精神薬を開発
考察
大塚製薬は抗精神病薬「エビリファイ」で世界的に成功を収めた企業ですが、特に中枢神経領域のパイプライン強化を狙ってきました。Mindsetが開発する次世代向精神薬は、既存薬で十分な治療効果を得られない患者層に新たな選択肢をもたらす可能性があります。精神疾患への社会的関心が高まる中、ブレークスルーを期待しての投資といえます。
5-2. 大塚HDのジュナナ・セラピューティクス買収
概要
- 大塚HDがジュナナ・セラピューティクスを約1208億円で買収
- 自己免疫疾患や希少疾患に特化した低分子阻害剤「JNT-517」などを開発
考察
ここでもアーンアウト(成功報酬型)方式が採用され、開発進捗に応じて追加で490億円程度支払う契約となっています。創薬の成功確率にリスクがある中、一部の買収金額を「実際に成果が出たとき」に支払う仕組みを取り入れるのは近年の主流です。これにより、高額買収のリスクをある程度コントロールできます。また低分子創薬は大塚HDにとっても得意な分野ですが、ジュナナ社が抱える独自技術と研究成果を取り込むことで、創薬速度を加速することが期待されます。
5-3. 武田薬品によるニンバス・ラクシュミ買収
概要
- 40億ドル(約5485億円)での買収
- 乾癬、炎症性腸疾患など免疫疾患領域で経口阻害薬開発プログラムを推進
考察
武田はシャイアー買収によって一躍“世界トップクラス”の製薬企業となりました。しかし、それと同時に大きな負債を抱え、資産売却などで財務改善も進めてきたところです。それでも有望パイプラインを取り込むことは将来的に不可欠であり、ニンバス買収はまさに免疫領域におけるグローバル展開の一手となります。
また、開発が成功し売上高が一定額を超えた際に追加で合計20億ドル支払う“マイルストーン”条項が設定されており、「成功報酬型」の買収手法がここでも取り入れられています。
5-4. 大日本住友製薬とロイバントの戦略提携
概要
- 約3300億円を投じてロイバントとその子会社5社を買収
- 婦人科がん、希少疾患、遺伝子治療など多方面のパイプライン
考察
大日本住友製薬は精神疾患領域での実績(米国でのLATUDA成功など)に加え、がん領域などにも積極拡大を狙っていました。ロイバントは多数の子会社を軸に、さまざまな疾患領域で新薬開発を進める「バイオファンド」的な色彩が強い企業です。一度に複数の開発パイプラインを手に入れるために、大型資金を投入したといえます。実際、婦人科がん領域などはこれまで大日本住友がカバーしていなかった領域であり、ポートフォリオの拡充という観点でも非常に大きな買収でした。
5-5. 小規模・ベンチャー買収の意義(免疫生物研究所、そーせいグループなど)
事例:免疫生物研究所がスカイライト・バイオテックを子会社化
生活習慣病領域に絞った研究開発ノウハウを得ることで、自社の抗体技術と組み合わせて新規アッセイ開発や創薬支援を強化する狙いです。
事例:そーせいグループがJITSUBOや英国Heptaresを買収
そーせいグループはバイオベンチャーですが、特にGPCR関連技術に強みを持つHeptares買収(2015年頃)で大きく注目を浴びました。ペプチド医薬の領域など、自社にない技術を持つベンチャーを取り込むことで、研究開発の幅が一気に広がります。
こうした小規模M&Aは金額ベースでは巨額ではなくとも、成功すれば大企業に匹敵するほどのインパクトをもたらす可能性があります。日本発ベンチャー同士でもシナジーを狙ったM&Aが進んでおり、今後もますます活発化が予想されます。
6. M&Aの成否を分けるポイント
6-1. シナジー創出と研究開発能力の統合
研究開発のスピードアップやパイプライン強化はM&Aの最大目的ですが、買収後に相乗効果を生み出すためには、技術プラットフォームと研究開発組織をどう融合させるかが重要です。大手企業の豊富な資金・ノウハウと、ベンチャー企業の独自技術や研究体制の強みを最大化しなければ、せっかくの高額投資が空振りに終わるリスクがあります。
6-2. 組織・文化の融合とガバナンス
企業文化の違いや研究者同士の摩擦が障壁となるケースは少なくありません。特に海外企業のM&Aでは、言語や価値観の違いも大きく、PMI(Post Merger Integration:買収後の統合プロセス)をいかにスムーズに進めるかが成功のカギを握ります。また、アーンアウト条項がある場合、買収先に十分な開発インセンティブを残すことも不可欠です。
6-3. アーンアウト条項・追加対価支払いの意味
創薬分野のM&Aでは、買収金額の一部を将来のマイルストーンや売上高達成に応じて支払うアーンアウト形式が一般的になっています。これは買い手にとってはリスクヘッジ、売り手にとっては成果を出せば大きく報酬を得られる仕組みです。一方、実際には開発遅延が起きるなどのトラブルも多いため、契約の細部設計が重要になります。
6-4. 規制当局の承認と独禁法対応
M&Aを行うにあたり、各国の独占禁止法や競争法などの審査をクリアしなければなりません。とりわけ世界的な製薬企業同士の合併・買収となると、EUや米国など複数の地域での承認が必要になり、手続きは複雑化します。また、新薬開発を進めるにあたってはFDA(米食品医薬品局)やEMA(欧州医薬品庁)などの承認手続きも絡むため、グローバルな法規制対応力が求められます。
7. 創薬M&Aの今後の潮流と展望
7-1. 希少疾患・中枢神経系・免疫・細胞治療・核酸医薬の注目
近年の大型買収や提携の多くが、がん領域や免疫・希少疾患領域、あるいは遺伝子治療や再生医療といった先端領域を狙っていることは明らかです。特に希少疾患は患者数が少ないものの、治療選択肢が乏しく“アンメット・メディカル・ニーズ”が高い分野です。開発が成功すれば高い収益が期待できるうえ、企業の社会的評価も高まります。中枢神経系領域も治療が難しい疾患が多く、潜在市場は大きいとみられています。
7-2. オープンイノベーションのさらなる拡張
大学や研究機関とベンチャー企業、大手製薬企業が連携する構図がますます当たり前になりつつあります。M&Aはその連携の最終段階とも言えますが、初期段階から共同研究やライセンス契約、出資など多角的な形で関係を築き、成果が出始めた段階で買収するケースも多いです。これにより、企業はリスク管理をしつつ将来有望な技術を確保できます。
7-3. バイオテック企業とIT企業の連携
創薬においてAIやデータサイエンス、DX(デジタルトランスフォーメーション)が重要視され、IT企業が創薬プロセスに参入する例も増えています。日本ではまだ大規模な事例は限定的ですが、海外ではGoogle(アルファベット社)傘下のVerilyやMicrosoftと製薬企業との連携が進んでいます。今後は製薬大手がAIベンチャーを買収する、あるいはIT企業がバイオベンチャーを取り込むといったM&Aも考えられます。
7-4. ヘルスケア全体のDX化と創薬支援の拡大
デジタル技術を使った創薬支援(CRO・CMOなど)ビジネスも大きく伸びています。各種データ解析や臨床試験の効率化など、デジタルヘルス分野との融合が進むことで、M&Aの射程も広がっています。単に新薬の候補物質を獲得するだけでなく、研究開発フロー自体を効率化する企業群との統合も狙われています。
8. まとめ:M&Aが拓く創薬の未来
創薬分野はリスクとチャンスが表裏一体の世界です。日本企業はこれまで国内需要に頼るビジネスモデルが主流でしたが、人口減少や高齢化による薬価抑制策の強化など、国内だけでは持続的成長が難しくなりました。そのため、グローバルに事業領域を拡大するうえで、有望パイプラインや先進技術を持つ企業をM&Aで取り込む戦略が、ますます重要になってきています。
一方、M&Aには巨額の資金が動き、組織や研究体制の再編が必要となるため、失敗すれば大きな痛手を被るリスクもあります。買収後のPMIにおいて、研究者同士のコラボレーションを促進し、当該技術を自社のポートフォリオへいかに組み込むかが鍵を握ります。
近年の事例からは、アーンアウト条項を盛り込んだ大型買収が増え、がん領域や希少疾患、中枢神経系、遺伝子治療、細胞治療など最先端の領域に資源が集中していることが見てとれます。また、ベンチャー企業側も大手製薬の資金力や販売ネットワークを活用して研究開発を加速しやすくなるため、買収は「ウィンウィン」の関係になり得ます。
今後、日本発のバイオベンチャーが海外の大手に買収される例も増えるでしょうし、その逆も起こり得ます。IT企業や異業種による創薬参入も活発化しており、多様な連携・提携・買収が進むと考えられます。いかにスピード感をもって優れた技術を確保し、グローバルでの治験・承認を勝ち取るかが、企業の将来を左右します。
M&Aはゴールではなく、むしろスタートです。今後も日本の製薬企業が世界市場で存在感を高め、患者さんに必要とされる革新的な新薬を生み出すための手段として、M&Aはさらに進化を遂げるでしょう。各社がどの領域に注力し、どんなベンチャーを買収するかを注視していくことは、今後の創薬業界を展望する上で欠かせない視点となります。

株式会社M&A Do 代表取締役
M&Aシニアエキスパート・相続診断士
東京都昭島市出身。慶應義塾大学理工学部を卒業後、大手M&A仲介会社にて勤務し、その後独立。これまで製造業・工事業を中心に友好的なM&Aを支援。また父親が精密板金加工業、祖父が蕎麦屋、叔父が歯科クリニックを経営し、現在は父親の精密板金加工業にも社外取締役として従事。